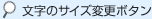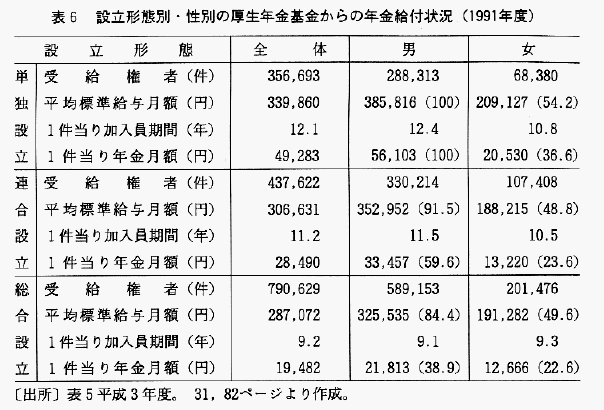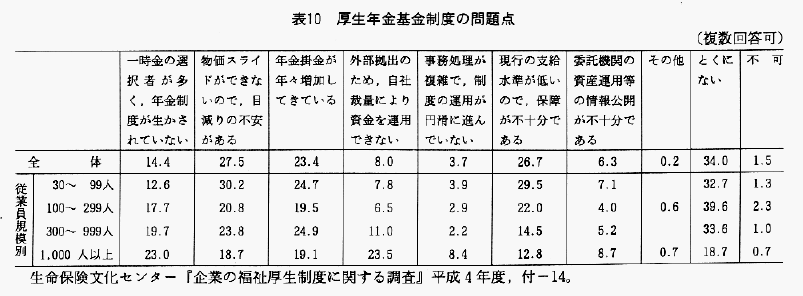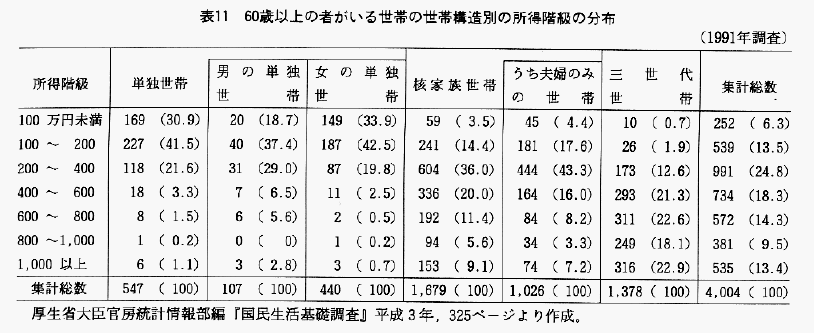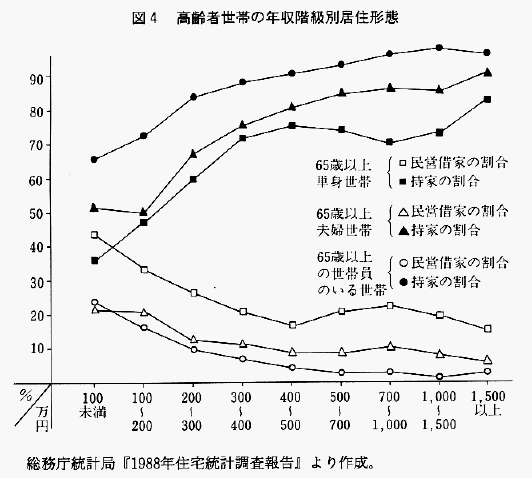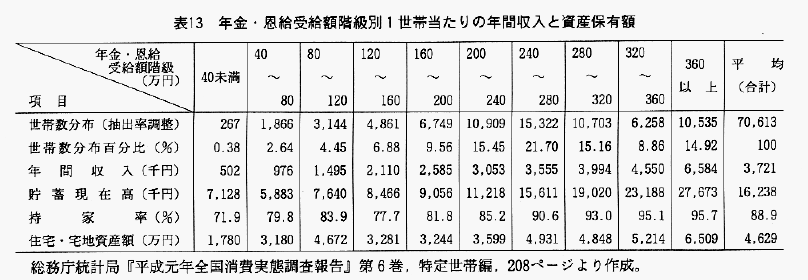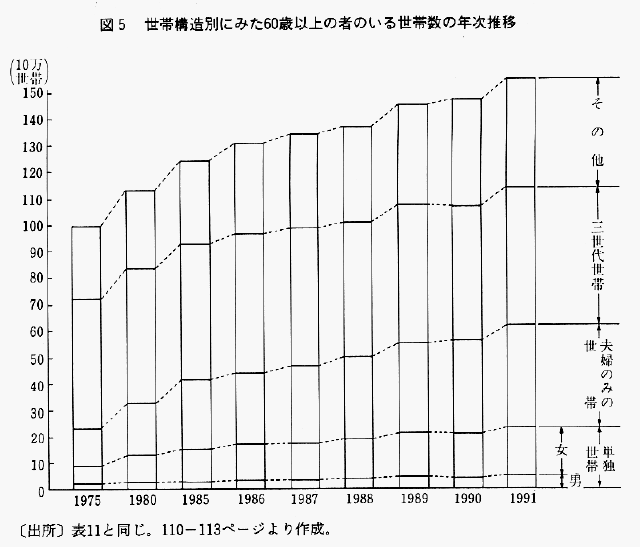第9号
公私年金分担の実態と年金制度改革への提言
醍醐 聰
醍醐 聰(東京大学教授)
1946年生まれ。京都大学大学院経済学研究科博土課程中退。名古屋市立大学経済学部助教授,京都大学経済学部助教授,東京大学経済学部助教授を経て,89年より現職。日本会計研究学会,日本会計史学会,公益事業学会に所属。
主な著書は「公企業会計の研究」(国元書房),「日本の企業会計」(東京大学出版会)等。
当初,本稿では,最近問題にされている年金資産の運用問題,特に筆者の専攻と関わる運用規制と運用評価をめぐる簿価・時価主義の問題を論じる予定であった。しかし,研究をすすめるにつれ,それ以前に,今日の年金制度設計に多くの検討課題があるように思われた。そのため,研究は次第に筆者の専攻からかけ離れてしまった。それだけに,本稿は,年金制度に関する不十分な理解からくる初歩的な誤りを含んでいるかもしれない。専門家の方々から,ご教示をいただければ幸いである。
1 年金制度改革構想への疑問
年金制度改革の作業が大詰めを迎えている。その内容は多岐にわたっているが,ポイントは,人口の急速な高齢化が進む中で,高齢世代の受給と現役世代の負担のバランスを図りながら,公的年金財政をいかにして長期的に安定させるかという点にある。そのための方策として,厚生年金の支給開始年齢を現行の60歳から段階的に65歳に引き上げる構想の実現が有力視され,それとの対応で,60歳代前半層の雇用の促進,企業年金の一層の普及と効率的な資産運用を図るための規制緩和等を進めるものとされている(注1)。
そこで,こうした年金制度改革構想を吟味していくと,いくつかの特徴が浮かび上がってくる。
ひとつは,給付設計面ではさしたる見直しはなく,議論が財源対策面に傾斜しているという点である。焦点の厚生年金の支給開始年齢の引き上げも,給付設計の変更には違いないが,その眼目は予想される厚生年金財政の逼迫を給付の繰り延ベという形で緩和しようとする一種の財源対策にある。
第二の特徴は,年金原資を負担する現役世代と年金給付を受ける高齢世代の世代間所得のバランスを制約条件として年金財政のありうべき姿を検討するというアプローチが際立っているという点である。賦課方式の公的年金が世代間扶養の社会契約であってみれば,制度設計にあたって現役世代の負担と高齢世代の受給のバランスを配慮すべきは当然である。しかし,だからといって,現役世代と高齢世代という二分法で改革構想を議論できるほど年金制度を取り巻く状況は単純ではない。
なぜなら,ひとくちに現役世代と高齢世代といっても,それぞれの世代に属する個人や世帯の経済的属性は一様でないし,宮島洋氏も強調するように,両世代は負担と受益のサイクルにおいて独立の経済主体ではなく,家族レベルで程度の差はあれ介護と遺産相続という逆方向の所得移転で結節している。しかも,その家族レベルでの負担と受益のサイクル自体において,家族間で顕著な格差があることも確かである(注2)。
そうであれば,年金をめぐる負担と受益のバランスも,現役世代と高齢世代という単純な二世代モデルではなく,各世代内部での家族もしくは世帯を単位とした保有資産と所得水準の差異にも着目して検討することが必要になる。
目下の年金改革構想にみられる第三の特徴は,公的年金は高齢期にも最低生活水準を維持するに足る所得を保障するという役割に徹し,それを上回る高齢期の豊かな生活の確保は私的裁量(自助努力)に委ねるという公私年金役割分担論を基盤にしている点である。しかし,公私年金の役割分担とはいっても,わが国の公的年金の一種である厚生年金では報酬比例部分が大きなウェイトを占めている。例えば,1989年度時点でみると,35年加入,平均標準報酬月額288,000円の民間男子サラリーマンのモデル老齢年金額は月額195,492円であったが,その内訳は定額部分82,926円,報酬比例部分 96,566円,加給部分16,000円となっている。ほぼ半分が報酬比例要素なのである。
となると,定額の基礎年金による平準化効果が働くとはいえ,高齢者が受給する私的年金はもとよりのこと,公的年金の水準も,勤労時代にどれほどの給与水準の企業にどれだけ勤続したかで歴然たる格差が生じる仕組みになっているのである。この事実を顧慮せず,年金を公私に単純に二分し,それぞれの役割分担を構想することは大きな問題をはらむ可能性がある。
また,個人レベルでの自助努力といっても,大半の勤労者にとって個人年金の原資は勤労時代の所得水準に制約されるし,退職後の自助努力といっても,経済的リソースなしに成り立つわけではない。勤労時代を中・低位の所得水準で経過し,さしたる運用可能資産を保有するわけでもない高齢者にとって,ありうべき自助努力といえば就業の継続しかないのである。しかし,高齢者のそうした自助努力に応じる雇用環境が現在わが国でどれほど整備されているのだろうか。こうした条件の整備を怠りながら,高齢者の自助努力を説くとしたら,無責任のそしりを免れない(注3)。
ところで,以上のように,目下提起されている年金制度改革案の特徴とそこに伏在する危うさをたどっていくと,筆者が感じた疑問の多くは改革を構想する際の前提となる現状認識のずれに帰因するように思われてならない。つまり,今回の改革構想に給付設計面でのこれといった改革が含まれていない背景には高齢期のミニマムな所得保障という公的年金の所期の目標は既に達成されているという現状認識があり,現役世代の負担と高齢世代の受給のバランスが殊の外強調される背景には,わが国の高齢者はもはや経済的弱者とはいえず,現役世代と比べても,かなりの生活水準を享受するに至っているという現状認識があるように思われるのである(注4)。
たしかに各種のモデル年金に基づいてみる限り,現役男子の直近の標準報酬月額に対する老齢年金月額の割合は1980年まではほぼ60%台で推移し,1980年の改正以後は68%という水準を保っている。しかも,この数値は税・社会保険料を控除する前のグロスの所得の比較であり,これら項目を控除後のネットの所得でみると,5対4になっているという試算もある(注5)。
しかし,このようにモデル年金を指標にした公的年金のパフォーマンス評価や,一部の高齢者の生活実態に過度に焦点を合わせた高齢者富裕論には,次のような疑問がある。
①そもそも年金制度の充実度は給付水準の高低だけで測られるものではなく,どれだけの高齢者を支給対象としてカバーしているか,被保険者の受給権はどこまで保護されているか,老後の所得保障という目的に照らして不可欠な物価スライド制,終身年金制がどれほど定着しているか,といった要素も含めてトータルな制度設計が問われなければならない。にもかかわらず,昨今の年金制度改革論では,負担と受給のバランスや給付水準の推移への強い関心に比べて,こうした制度問題に対する関心が希薄であるように思われる。
②また,給付水準自体についても,上記のようなモデル年金は文字どおり標準的なケースを表すにとどまる。重要なことはそのモデル年金がどれほどの受給者をカバーしているかである。この点では,先に述べたように公的年金でも報酬比例部分が大きなウェイトを占めているだけに,各受給者への給付額には相当なバラツキがあるはずである。であれば,標準給付額や代替率だけで年金給付水準の充実度を評価したのでは現状認識を歪めることになりかねない。
③ひとくちに高齢者といっても,その中には資産保有や所得水準,居住状態の面でじつに多様な個人,世帯が含まれている。したがって高齢世代の生活実態を把握するのに平均値は禁物であり,累積度数分布なり相対度数分布なりに関心を払う必要がある。
そこで以下,この稿では,まず次の2節で,わが国の現行の年金制度の体系を素描しながら,そこにおける公と私の相互浸透を検証する。次いで3節ではわが国の現在の厚生年金の給付状況の実態を企業規模別格差という視点から吟味する。また4節では高齢者世帯の資産と所得の実態を確かめる。そのうえで,5節で,年金制度改革の望ましい姿を給付構造と税制の面から検討したいと思う。
2 公的年金への私的給付方式の浸透
二階建ての年金制度
図1は1986年の制度改革以後の三階建てとも称されるわが国の年金制度の体系を示したものである。まず,国民年金(基礎年金)は全国民共通の基礎的な年金給付を行う公的年金であり,被保険者は,20歳以上〜60歳未満の自営業者(第1号被保険者),民間サラリーマン,公務員等(第2号被保険者)およびその妻(第3号被保険者)から構成されている。保険料は定額で段階的に引き上げられる仕組みになっており,1993年度時点では月額 10,500円である。ただし,第3号被保険者はその属する被用者年金制度が基礎年金への拠出金として負担するので個々には負担しない。
この基礎年金を一階部分とすると,二階部分にあたるのが厚生年金保険と共済年金からなる被用者年金制度である。このうち,厚生年金保険は民間事業所で常時使用される65歳未満の勤労者を主な被保険者とし,標準報酬月額に所定の保険料率を乗じた額を事業主と被保険者が折半して保険料を負担することになっている。
一方,この厚生年金保険からの主たる給付は,一階部分の老齢基礎年金の支給用件を満たしたものに,各基礎年金に上乗せする形で支給される老齢厚生年金であるが,年金額は,
{平均標準報酬月額×(10/1000〜7.5/1000)×被保険者期間の月数}×物価スライド率+加給年金額
という算式で計算される。
次に,国家公務員,地方公務員,私立学校教職員,農林漁業団体職員を対象にした各共済組合の詳しい説明は省略するが,ここでも掛け金・負担金の額は標準報酬を基準に算定され,長期給付(退職共済年金等)は当該組合員の全期間標準報酬を基準として算定されている。
説明は前後するが,以上二階部分にあたる二つの被用者年金制度は20歳以上〜60歳未満の被保険者と被扶養配偶者の数に応じて基礎年金(一階部分)の給付に要する費用を負担する仕組みになっており,国庫負担は原則として基礎年金拠出額の1/3相当分に限定されている。
しかし,厚生年金のすべてが厚生年金保険から支給されているかというとそうではない。図2で示したように老齢厚生年金のうち報酬比例部分(物価スライド分と再評価分は除く。)は1966年に創設された厚生年金基金(以下,基金と略す。)によって支給が代行されているのである。また,それとの見合いで基金の加入員は厚生年金保険ヘの保険料納付を免除されている。とはいえ,基金は厚生年金保険のたんなる代行機関ではなく,代行部分の1.3倍以上の独自の年金給付を設計するところに意義があるとされている。なお,基金は企業の退職一時金の年金化と厚生年金保険事業の機能及び費用負担を調整する性格を持つことから調整年金とも呼ばれていることは周知のとおりである。
しかるに,基金は後述のように一定範囲の事業所を単位として設立されるため,特定の基金を次々と脱退した被保険者の場合は各基金への加入期間が短く,年金給付額も少額となる。そこで,こうした基金からの中途(短期)脱退者に対する年金給付の原資をプール(移換)し,それらを通算して納付するのが便宜といえる。そのために設立されたのが図2で示した厚生年金基金連合会(以下,連合会と略す。)である。なお,1989年度から,脱退一時金も連合会に移換し,年金化することが可とされた。
ところで,このように国民年金の第2号被保険者には老後の所得保障の手段として二階建ての年金給付構造が設計されているのに対し,自営業者等,国民年金の第1号被保険者の場合は従来は基礎年金だけであった。この点のアンバランスを解消するため,1991年4月に自営業者等についても二階部分にあたる国民年金基金が創設された。当基金は,第1号被保険者に基礎年金への上乗せ年金を支給することを目的とする点でも,中途脱退者の年金原資をプールし,それを通算して支給する国民年金基金連合会が存在する点でも,厚生年金基金と共通するが,強制加入でない点に違いがある。
以下では,国民年金の第2号被保険者(民間サラリーマン)に係る厚生年金に対象を絞って,この年金制度における負担と給付の特徴をもう少し掘り下げて観察してゆくことにしたい。
公的年金への報酬比例方式の導入
わが国の年金制度に関する解説では,基金は老齢構成年金の報酬比例部分の給付を代行する限りでの公的性格と,それを超える上乗せ年金の支給を目指すという意味での私的(企業年金)としての性格を併せもつと指摘されてきた。しかし,こうした基金による公的年金代行については,早くからその限界や問題点も指摘されてきた。かつて,ILOの社会保障に関する委員会は,公的な社会保障制度を適用除外して,私的な職域年金で代行させるやり方は許すべきではないとの見解を表明している。賦課方式の公的年金と事前積立方式の企業年金は所詮,水と油の関係というのがその理由であったらしい(注6)。賦課方式とは世代間の順送り扶養であり,家族扶養の集団化,社会化であるのに対し,事前積立方式は自らが勤労時代に積み立てた貯蓄で老後の収入を賄い,後の世代に負担をかけない自助努力といえるからである(注7)。
確かに,年金が老後の所得保障というなら終身給付を建前とするはずであるが,わが国の企業年金,特に適格年金制度は有期年金が主流である。また,勤続期間が短いものについても受給権が付与されなければ企業年金とはいえないとの指摘があるが(注8),わが国の基金ではほとんどが定年退職を年金支給要件としている。
原則に立ち返っていうと,「社会保障給付が普遍的または最低生活保障を目的とした場合は税を財源とし,集団内において連帯的でありかつ負担と給付の対応が求められる従前所得保障型給付の場合は保険料方式を財源とするのが望ましい」(注9)といえる。ところが,わが国では,老後の最低生活保障という目的をもつ公的年金給付の相当部分を,負担と給付の対応を原則とする事前積立方式の企業年金によって代行させる仕組みになっているのである。
こうみてくると,私的年金としての基金の公的側面を指摘するだけでは皮相に思えてくる。むしろ,公的年金に一部私的給付方式が浸透している点こそ注視すべきでないだろうか。
ここで,「公的年金への一部私的給付方式の浸透」というのは,二階部分の厚生年金保険が負担と受給の対応を原則とする報酬比例方式で設計されているという事実を指している。厚生省のデータによると,1992年3月末現在の老齢年金の1件当たりの平均支給月額は約15万400円となっているが,そのうち老齢基礎年金は39,633円となっており(注10),加給部分を別にすると,1件当たりの老齢年金のほぼ3/4が再評価分,物価スライド分も含め,報酬比例要素なのである。ここで,報酬比例ということは,勤労時代の平均標準報酬と勤続(加入)期間比例ということであり,過去の給与水準と勤続が老後の所得の水準をも左右するということである。これでは公的年金の財政方式は世代間扶養の仕組みであるといっても,実質は被保険者の勤労時代の報酬実績がものをいう「自助努力」依存方式に大きく傾斜していることになる。
つまり,「加入期間比例・拠出額比例という,私的年金と同様の考え方で公的年金の給付を設計してしまったため,『未来からの補助金』部分も私的年金と大差のない考え方で事実上,給付されることになってしまっているのであ」(注11)り,これでは,「金持ちがいっそう金持ちになることに現行の年金制度が事実上,手を貸」(注12)す一方,「経済的に恵まれない高齢者には年金制度からの経済的支援も少ない」(注13)ということになるのである。
しかし,公的年金がこのように逆進的な所得分配をもたらしているとしたら,社会福祉としての公的年金制度の正統性はどう信認されるのであろうか。勤労世代と高齢世代の世代間の負担と受給の公平もさることながら,勤労時代の所得の格差が高齢世代にも持ち込まれる現行の年金給付方式の帰結にもっと関心が向けられてしかるべきではないだろうか。
そこで,次の節では,モデル年金を用いて年金給付の水準だけを論じたのでは見えてこないわが国の現在の年金給付の実態を,基金を主たる対象にして吟味してみたい。
3 厚生年金基金による給付の実態
1992年9月に東京大学社会科学研究所の主催で「福祉国家と市場メカニズム」をテーマとして開催された国際シンポジウムにおいて,招待研究者のひとりとしてロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの講師ポール・ジョンソンがイギリスにおける年金制度の現状と問題点についての報告をしている(注14)。
そのなかでジョンソンは,イギリスでは1988年末現在の年金受給者のうち560万人が,彼らの生活水準を貧困線より引き上げるため,資力調査による給付を受けていた事実などを挙げて,今日のイギリスの年金制度は定年退職後の高齢者に対して適当な所得保障をすることに失敗していると結論づけている。
注目すべきはジョンソンが,イギリスの年金給付水準の全般的な劣悪さを指摘するだけでなく,それ以上に,イギリスにおける年金生活者の家計の経済状態に大きな格差が生じていることを指摘している点である。彼は表1のデータにもとづいて,年金生活者の家計の収入分位上位20%では社会保障給付が総所得に占める割合は1/4にとどまるが,絶対額では最下位グループが受給する額をかなり上回っていること,家計間の所得格差をもたらす最大の要因は職域年金受給額の圧倒的な格差にあること,を示している。
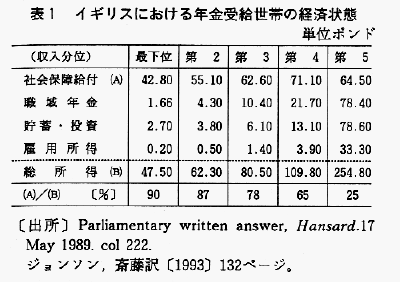
つまり,ジョンソンによれば「職域年金の受給権が生じるための従前の労働市場における経験およびこれに付随した能力は,老後の生活において高収入を得るための鍵となる要素」なのである。その結果,「現状の職域年金はある意味では主として最もその必要のない人々に対し,定年後にかなりの収入を与えているのではないか」,「高齢者の貧困は,男性に比べて長期にわたる継続的な勤務歴をもつ傾向が少なく賃金も低い女性においてとりわけ深刻ではないか」——彼はこう推論している。
ではジョンソンが指摘したこのような年金給付の逆進性はわが国でもみられるのだろうか。この点を確かめるために,以下本節では,企業年金の給付水準を母体企業の規模別に分析し,報酬比例要素が大きなウェイトを占める被用者年金の給付にどの程度の格差が生じているかを探ってみたい。
ところで,母体企業の規模別に年金給付の実態を調査・集計した資料としてまとまっているのは,労務行政研究所が隔年で刊行している『退職金・年金事情』である。ここでは,その最新版である平成5年版を用いる。調査は1992年10月7日から同年12月28日にかけて,全国8証券市場上場会社約2,160社と,資本金5億円以上で従業員500人以上の主要非上場会社約740社,計約2,900社を対象になされた。ただし,そのうち回答があったのは277社(約9.6%)で,回答率はかなり低い。集計にあたっては,対象会社の規模が従業員数1,000人未満,1,000〜2,999人, 3,000人以上と三区分されている。規模別に集計対象会社の内訳をいうと,1,000人未満82社,1,000〜2,999人106社,3,000人以上89社である。
さらに別の資料として,厚生年金基金連合会が刊行している『厚生年金基金事業年報』がある。その最新版は平成3年度分で集計結果の発表がかなり遅れている。当資料はすべての基金の毎年度の業務と決算の状況をカバーしているが,すべて集計値ないしは度数分布データであり,個々の基金ベースのデータはもとより,規模別のデータも含まれていない。
しかし,当資料に含まれている設立形態別のデータから,母体企業の規模別の年金給付の実態をある程度まで把握できる。というのも,基金はその設立母体の別に応じて,単独設立,連合設立,総合設立に区分されている。このうち,「単独設立」とは従業員500人以上の企業が単独で設立する基金であり,「連合設立」とは主力企業を中心として株式の相互持ち合い等をつうじて有機的連携性のある2以上の企業が共同で設立する基金である。また「総合設立」とは,同種同業の企業が同業組合,健康保険組合等を組織母体として設立するか(同種同業型),同一都道府県内の工業団地,商店街に所在する企業が事業共同組合,商店街振興組合または健康保険組合等を組織母体として設立する基金(地域型)である。
したがって一般には,単独設立が大企業を,連合設立が大企業たる親会社を中心とした企業グループを,それぞれ母体にするのに対して,総合設立は主に中小企業を母体にしている。このことは1事業所当たりの加入員数がそれぞれ289人,328人,40人となっているという事実からもうかがえる。そこで以下では,基金の設立形態を母体企業の規模のおおまかな代理変数とみなして,基金の給付状況を設立形態別に分析してみたい(注15)。
まず,給付水準以前に,受給資格,支給(保証)期間といった受給権に係る事項をみておく必要がある。労務行政研究所の調査(以下,労政研調査,と略す。)によると,表2のとおり,全産業・全企業ベースでは,定年退職を受給要件とするのは約28%で,約71%が自己都合退職者にも受給資格を認めている。これを,規模別にみると,退職事由,勤続・年齢どちらの要件についても規模間の差異はほとんどみられない。
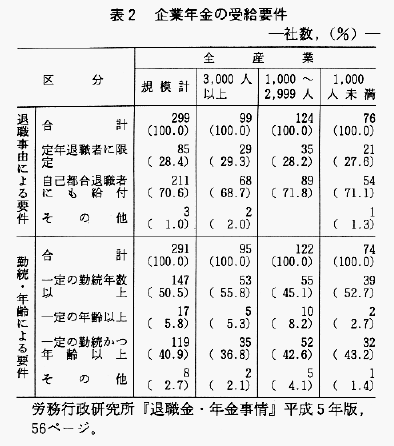
また,もうひとつの受給要件である勤続・年齢要件をみると,過半の企業が一定年数以上の勤続を要件として課し,その年数では20年が最も多い。これに一定の勤続以上かつ一定の年齢以上を要件とするケースを加えると,90%強の企業がなんらかの勤続・年齢要件を採用していることになる。この傾向には規模間の差異はみられない。
次に年金の支給期間をみると,全体では終身が36%,有期が58%となっている(表3)。しかし,これを規模別にみると,終身の割合は3,000人以上では43%で有期と同じであるが,1,000人未満では23%にとどまっている。

また,有期の場合,支給期間はどれほどかをみると,5年,10年の割合が3,000人以上では46%であるのに対し,1,000〜2,999人では66%,1,000人未満では84%となっており,この面でもかなりの規模間差異がみられる(表3)。
しかし,年金支給期間は年金の種類別でさらに大きな差異がみられる。適格年金では有期が87%を占めているのに対し,調整年金では逆に終身が89%を占めている。
このように適格年金において有期制が多いのは,その大半が退職一時金の取り崩しで年金制に移行した(移行型)ため,給付の設計が原資の確保によって制約される度合が強いためと考えられる。これに対し,調整年金は厚生年金保険の給付を代行する制度上の原則からして,当然に終身制が大半となっている。
ところで,たとえ終身制であっても,受給期間前や受給期間中に本人が死亡したとき給付が打ち切られるとしたら,その後の被扶養者には大きな打撃となる。そこで,表4で示したように全体の88%の企業は終身,有期とは別に受給権者が死亡した場合の保証期間を定め,その間は受給権者の被扶養者等に年金を支給することにしている。問題は保証期間の長短であるが,表4によると,3,000人以上では15年が63%を占めているのに対し, 1,000人未満では10年というのが71%となっている。
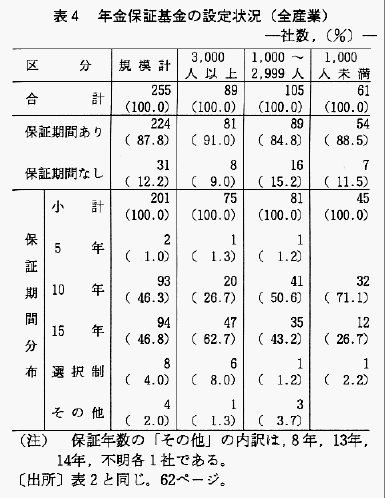
以上が労政研調査(平成5年版)を利用した企業年金の受給権の実態分析である。それらをまとめると,受給要件の面では全体として一定以上の勤続または(および)年齢を要件とする企業が規模のいかんを問わず大半を占めていること,支給期間の面では規模が小さくなるほど有期制が増えるとともに保証期間が短くなっていることがわかる。
ただし,労政研調査には,①集計数が少ない。②もともと制度設計に差異が少なくない調整年金,適格年金,独自年金が調査対象に混在している,といった限界がある。そこで次には,前記の『厚生年金基金事業年報』(以下,『基金年報』と略す。)を用いて,厚生年金保険の給付を代行する厚生年金基金(調整年金)に対象を絞って,給付の状況を設立形態別に吟味してみたい。
図2で示したように,基金は公的年金としての厚生年金保険のうちの老齢厚生年金の一部を代行給付する機能と,代行部分を超えるプラスアルファを給付する上乗せ機能を担っている。このうち,さしあたって問題なのは,基金が代行する給付水準とはどの程度のものか,基金はこの代行機能をどの程度果たしているかである。
この点を探る資料として,『基金年報』が1987年度版以降毎年度掲記している設立形態別の年金支給額と,そのうちの代行相当額が参考になる。それを1件当たり月額に換算するとともに,基金からの給付額が代行相当額の何倍に当たるかを示したのが表5である。この倍率が1を超える部分がプラスアルファと称されるものであり,30%以上を要請されている。単独設立の給付が2倍以上となっているのに対して,総合設立では30%を下回り,中途脱退者への代行部分の給付を受け持つ連合会のプラスアルファは10%台にとどまっている。
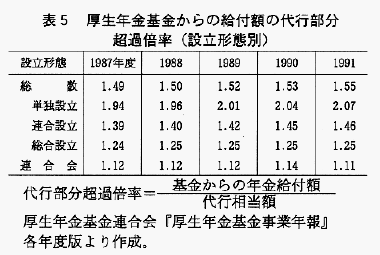
このように,設立形態の違いでプラスアルファに大きな開きが生じたわけは,給付額の算定要素とされる基礎率(とくに加入年数)と標準報酬が設立形態間でかなり乖離しているためであろう(表6参照)。
ただ,ここで確かめておかなくてはならないのは,プラスアルファの多寡以前に,そもそも要代行額がどの程度のものだったかである。要代行額が高齢者の必要最低所得を保障するのに十分な水準に達していてこそ,それを代行した上でのプラスアルファの多寡を論じる意味がある。もし,要代行額が高齢者が必要とする最低限の所得以下の水準でしかなかったとすれば,プラスアルファの相当部分は実質上,公的年金に上乗せをする機能ではなく,公的年金を補完・代行する機能を担っていることになる。
しかるに表7をみると,基金の1件当たりの代行相当額は月額18,500円にすぎず,プラスアルファを含めた総額でも月額は28,676円にとどまっている。
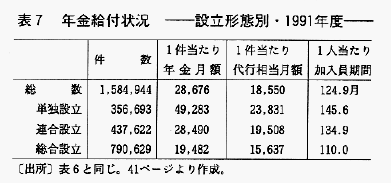
これでは,高齢者にとってプラスアルファは公的年金への上乗せどころか,公的年金の補完でしかない。こうした現状について,厚生省は,「設立後日が浅い基金が多いこと,加入期間が短い者がいること等によるもので,将来は,平均年金額も高くなっていくものと見込まれる」(注16)と楽観している。しかし,それは今後の平均値の緩やかな傾向であり,毎年度の中途脱退率がこの11年間,男8〜9%台,女15〜17%という状況のもとでは平均値だけで議論をするのは適切でない。
そうした問題を留保したうえで,次に基金の「上乗せ機能」がどの程度の水準に達しているか確かめるために,基金が代行部分を超える加算年金をどの程度給付しているかを調べたのが表8である。それによると,1991年度の1件当たり加算年金給付月額は単独設立では74,607円,連合設立では39,509円,総合設立では11,116円で,代行部分の給付以上に設立形態間の開きが大きくなっている。

しかし,問題は給付水準の格差だけではない。それ以前に,厚生年金保険受給権者のうち,加算部分の受給権も持つ者の割合が設立形態間で大きく異なっているという事実を見落としてはならない。表9で示したように,単独設立と総合設立とではその割合に3倍近い開きがある。と同時に,基金の全受給権者の8割以上が加算部分の受給権を持っていないという点も注視されるべきであろう。これは,加算部分の受給資格について,勤続要件等の面でかなり厳しい要件が付けられているためと考えられる。
このようにみてくると,基金による代行部分の給付額の絶対的水準がきわめて低い現状では,基金が行う独自の加算給付は公的年金に対する上乗せというより,代行部分の補完という性格をもつ。しかし,その加算給付自体も受給権の面で基金の受給権者総数の8割以上を排除し,加算給付の水準も設立形態間で大きな格差が生じている実態からすると,代行部分の補完機能を十分果たすにはほど遠い状況にあるといえる。表10において,集計対象企業のほぼ 1/4が,「現行の給付水準が低いので,保障が不十分である」と答えていること,またそう回答した企業が小規模企業に特に多いことは,こうした状況を裏付けているように思われる。
4 高齢者世帯の経済実態
しかし,企業年金に受給権の限界や給付水準の格差が拭えないとしても,近年の基礎年金の充実と,標準報酬月額の再評価制の採用,年金額の完全自動物価スライド制の実施等により,わが国の老齢年金は1992年度には月額で平均15万円を超えるに至っている。また,今後40年加入が一般化するに伴い,年金額はさらに増大して,妻が国民年金に25年任意加入していた場合,夫婦の年金総額は勤労世代の平均賃金の97%以上に達すると見込まれている。こうした数値をみる限り,給付の面ではわが国の公的年金(基金による代行も含む)はほぼ満足すべき水準に到達しているといえそうである。むしろ,40 年加入が一般化した段階での給付費の増大に備えて1985年度以降20年間かけて,定額給付部分の単価と報酬比例部分の乗率の逓減による給付水準の引き下げが実施されつつある。
しかし,何度もいうが月額15万円といっても,それは受給権をもつ者の平均値である。老後のミニマムな所得の保障という公的年金の原点からいえば,受給権をもたない者をかやの外において,平均値で議論するのは禁物である。そこで,この節では,高齢者世帯の所得の分布状況,公的年金による下支えの実態をさぐり,併せて高齢者世帯の居住状況を確かめてみたいと思う。
高齢者世帯の経済実態をめぐって,最近,筆者には大変気がかりな論調が台頭している。「高齢者はもはや経済的弱者ではない。」「『高齢者かわいそう論』は時代遅れである」といった論調がそれである。例えば,高山憲之氏は高齢夫婦世帯1世帯当たりの年間収入,消費月額,貯蓄残高,宅地住宅資産額の平均値,最頻値,中央値等を挙げて,1989年現在での「各指標の平均値(年間収入430万円,消費月額23万円弱,貯蓄残高2,000万円弱,宅地・住宅保有額6,500万円等)をみるかぎり高齢夫婦世帯はもはや貧乏ではない。」むしろ,「高齢者は現在,ストック・エコノミーの主役である。」(注17)と評している。もっとも,同氏は平均値だけで高齢者の実相を的確に映しだすことはできないことを十分心得て,中央値や最頻値を併記したわけである。
しかし,それでもなお,筆者は高山氏によるデータの取捨選択と解釈の中で疑問に思える点が少なくない。
①疑問の第一は,対象世帯として高齢夫婦世帯(ここでは世帯主が60歳以上の男子で,年金を受給しながら妻と2人だけで生計を営む世帯)が特に断りなく選ばれている点である。厚生省大臣官房統計情報部編『国民生活基礎調査』平成3年版(以下,基礎調査という。)によると,60歳以上の者がいる世帯のうち世帯構造別でみると,夫婦のみの世帯が24.8%,三世代世帯が33.3%,単独世帯が15.3%となっている(図5参照)。また,60歳以上の者のみの世帯でみると,夫婦のみの世帯が52.2%,単独世帯が43.2%となっている。
この事実からすれば,高齢者世帯の所得水準を調査する際に,高齢夫婦世帯,それも世帯主が60歳以上の男子である夫婦のみの世帯を取り出すのは問題なしとしない。むしろ,大いに問題ありというべきである。というのも,対象は65歳以上ではあるが,表11で示したデータからわかるように,単独世帯では,その31%が年収100万円未満の所得階級に属し,累計では72%の世帯が年収200万円未満の階級に属しているのに対し,夫婦のみの世帯では全体として単独世帯より所得分布がかなり上位にシフトしている。その結果,1世帯当たりの平均所得金額は夫婦のみの世帯では381万円であるのに対して,単独世帯の場合は174万円で,2倍以上の開きがある。また,三世代世帯ではその64%が年収600万円以上の階級に属し,1世帯当たりの平均所得金額は809万円となっている。
とすれば,高齢者世帯の中から,特定の属性をもつ高齢夫婦世帯だけを取り出して,所得水準を云々するのは実態認識を歪める恐れが大きいのである。
②疑問点の第二は,対象世帯の選択を不問にしたうえでではあるが,「年間収入180万円未満の世帯が20%あった」という事実と,「年間収入600万円以上がほぼ6世帯に1世帯の割合であった」という事実がどうして,「高齢者夫婦世帯はもはや貧乏ではない」という結論につながるのかという点である。これらの事実からいえそうなことは,公的年金の給付は,それに収入の大半を依存する世帯にとっては,なお,きわめて低い水準にある一方,それを必要としない高齢者世帯にもかなりの額が支給されている可能性があるということである。この点を基礎調査でもう少し裏付けてみよう。
図3は公的年金も含めた1991年度の世帯別の所得金額の相対累積度数分布を,三つの世帯類型別に分けて捉えたものである。これをみると,高齢者世帯ではその49%が年間所得200万円未満の階級に属し,68.4%の世帯が平均所得金額(289.8万円)以下となっている。高齢者世帯内部での所得格差は一般勤労世帯におけるよりも顕著であることが読み取れる。
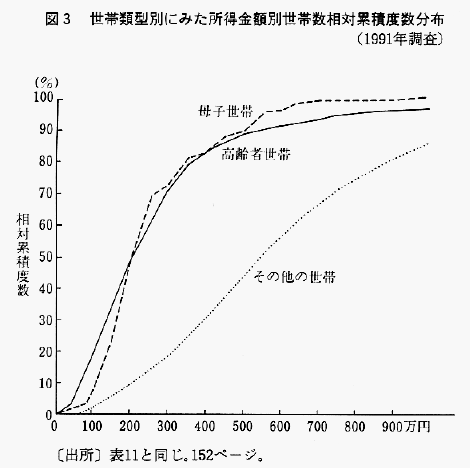
次に,高齢者世帯において公的年金・恩給が総所得に占める割合を所得階級別に表したのが表12である。それによると,公的年金・恩給を受給する世帯のうちの47%が年収200万円未満であり,年収50万円未満の世帯の88%,50〜100万円の世帯の60%がそれぞれ公的年金・恩給のみを所得源としている。
言い換えると,公的年金・恩給に100%依存する高齢者世帯の約23%は公的年金・恩給を受給してもなお,年収100万円未満の状態にあるのである。また,年収600万円以上の高齢者世帯のうち約55%が,総所得の20%以上を占める公的年金・恩給を受給しているわけである。このことは,公的年金・恩給が,それのみに所得を依存する世帯の約1/4には月額約8万円以下しか給付されない半面,公的年金・恩給に頼る必要がさほどない高齢者世帯には月額で最低でも約12万円が給付されていることを意味する。公的年金の給付にも報酬比例要素が入っている現行制度のもとでは,後者のような事実が生じても驚くには当たらないが,あるべき年金給付の設計,年金財政を検討する際には,こうした実態を直視すべきであろう。
③1989年現在,高齢夫婦世帯の持家率89%,宅地・住宅資産の平均値6,488万円,最頻値1,400〜1,499万円というデータも,高齢者世帯の経済・生活実態を判断する資料としては,いささか粗雑と思われる。平均値と最頻値の大きな乖離自体,高齢者世帯内部での資産格差の一端を窺わせるが,ここでは高齢者世帯の居住実態を世帯構造別,所得階級別に調べてみよう。
1990年の国勢調査によると,65歳以上の親族がいる一般世帯(以下,この世帯構造を一般高齢者世帯という。)は全国で 10,729,464世帯であったが,そのうち高齢夫婦世帯(いずれかが65歳以上の夫婦1組だけの世帯)と単独世帯の割合はそれぞれ19.8%, 15.1%であった。しかるに,同国勢調査によると,一般高齢者世帯の持家率が85.4%であったのに対して,高齢単独世帯の持家率は62.7%であった。
また,5年ごとの調査のため,データは古くなってしまったが,総務庁統計局『1988年住宅統計調査報告』によると,高齢単独世帯の持家率はどの年収階級でみても,一般高齢者世帯よりかなり低い。とくに目につくのは,高齢単独世帯の54%が属している年収100万円未満の世帯の持家率が 37.2%ときわめて低く,民営借家率が44%ときわめて高いという事実である。高齢夫婦世帯の場合は,単独世帯よりも総じて持家率は高いが,それでもこの世帯総数の約45%が属している年収200万円未満の世帯の持家率は51%にとどまっている(図4参照)。しかし,こうして民営借家に滞留する低所得の高齢者世帯,とりわけ高齢単身者は,火事や病気の際の対応の煩わしさ等を理由に民営借家への入居を断られたり,契約の期限切れを理由に立ち退きを迫られる場合が多いため,住生活の不安定さが著しい(注18)。
こうした実態を見ると,ひとくちに高齢者世帯といっても,この世代の居住状況は世帯構造・所得階級のいかんで実に区々なのであり,高齢者世帯全体の持家率の高さや宅地・住宅資産の平均保有額の大きさだけで,高齢者世帯を「ストック・エコノミーの主役」とみなすのは実態認識として粗雑といわなくてはならない。
5 公的年金制度改革への提言
制度改革の目標
ここでいう「年金制度」とは給付とその財源調達の体系を指す。この意味での年金制度は次のような目標を満たすことが求められる。
①高齢者が必要とする最低所得の保障
②保険料を拠出する勤労世代と年金を受給する高齢世代との間の世代間の公平,ならびに,高齢世代内の公平
③年金財政の長期的安定
④他の社会福祉政策との統合・連携
このうち,①は自明のようであるが,近年,社会福祉論の分野では,社会福祉ニードを貨幣的ニードと非貨幣的ニードに区分したうえで,年金等の貨幣的ニードは選別主義でそれを特に必要とする者に重点的に給付する一方,在宅福祉サービス等の非貨幣的ニードは普遍主義に則り,経済的要件を課さずにニードに応じて誰もに給付すべきであるという思想が有力になっている(注19)。
こうした社会福祉の思想潮流に照らすと,上記①の目標はどう理解されるのであろうか。折しも,公的年金のうちの所得比例年金はミーンズ・テスト(資力調査)による選別的給付に切り替えるべきであるとの主張が一部から提起されている。このような主張をしているのは野口悠紀雄氏であり,その論旨は次のとおりである(注20)。
高齢世帯内での資産格差を是正するうえでも,勤労世代による今後の社会保険料負担の増大を抑制するうえでも,一定額以上の資産(当面は不動産)を保有する高齢者には年金給付を一部カットすべきである。その場合,年金の一部をカットされた高齢者は保有する不動産をリバース・モーゲッジやセール・リースバック等の方式で現金化して老後の生計を十分成り立たせることができる。その際,野口氏が選別支給すべきというのは公的年金のうちの報酬比例部分(厚生年金)である。しかも,野口氏は報酬比例年金については任意加入制にし,脱退の自由を認めるよう主張している。
このようなラジカルな主張がなされる背景には,(a)「基礎年金は普遍主義原則による給付であり,すべての高齢者に最低保障額の年金を支給する。それは一般財源によって賄われる」(注21)という理解と,(b)所得比例年金は建前は修正積立方式であるが,実際は「給付の大部分は,積み立てた保険料ではなく,その時点の各世代の負担(社会保険料負担と税負担)によって賄われている。」(注22)しかも,現行のままでは現役世代の厚生年金の生涯負担に対する生涯給付の割合は1を大きく割り込む「逆ざや」になるのは必至である,という強い危機意識,がある(注23)。
(b)については,この後の目標②のところで検討することにし,ここでは,(a)のような年金制度の理解を前提にした所得比例年金選別支給論の当否と実行可能性を吟味しておきたい。
まず,普遍主義の原則にもとづいて支給される公的年金を基礎年金部分に限定するという理解の当否が問題である。社会保険庁調べによると,基礎年金給付費の90%を超える老齢基礎年金の1992年度末現在の1件当たりの本来支給額の月額平均は43,645円である。この額自体,高齢者の最低生活を保障する水準には程遠いうえに,1992年度の老齢基礎年金の1件当たりの実際給付額の月額平均は39,632円となっている(注24)。これはピーク時の8割近い水準から低減してきたとはいえ,同年度現在なお50.8%の受給者が老齢基礎年金の繰り上げ支給を選択しているためである(注25)とすれば,理念としてはともかく,給付の現実をみる限りでは,基礎年金のみが高齢者の最低所得を保障する公的年金であるとはとうていいえそうにない。むしろ,最低所得を従前所得の一定割合と理解するなら,普遍的に保障されるべきは,基礎年金に所得比例年金のうちの相当部分を加えた額であると考えるのが妥当である。この意味で,所得比例年金を一律に基礎年金と区別して選別支給の対象にすべしという野口氏の提言は現状ではとうてい受け容れられないであろう(注 26)。
そうであれば,野口氏の提言は,基礎年金の給付水準の大幅な引き上げと一体のものとして主張される場合にこそ,積極的で現実味をもった提案になるといえるかもしれない。筆者もこの後で述べるように基礎年金の引き上げに大きな意義を認めるが,それと報酬比例年金の選別支給・任意加入制を連動させるのは実行不可能と考える。
まず,選別支給となると,提言にもあるようにミーンズ・テストが不可欠となるが,これを公正に実施できる見込みはきわめて薄い。というのも,ミーンズ・テストの対象を提言のように不動産のみとすると,そこでも指摘されているように資産の保有形態を変更してテストを回避しようとする受給者の行動を誘発する可能性がある。しかし,それ以前に,保有資産を活用して自助努力で老後の必要所得を賄える高齢者には所得比例年金の支給を削減する代わりに,制度からの脱退も認めるというのであれば,活用可能資産を不動産に限定する理由はない。むしろ,不動産よりもはるかに流動化しやすい金融資産をカウントするのが当然である。しかし,所得税法上,有価証券譲渡所得の捕捉さえなされていない現状において,有価証券保有についてのミーンズ・テストが実行できるとはとうてい考えられない。
また,現行の二階建ての公的年金制度の給付費負担構造に照らしても,二階部分を任意加入制にするのは不可能と考えられる。先の引用文にあるように提言は,基礎年金は一般財源で賄われているとの理解を前提している。しかし,ここでの「一般財源」が税負担を意味するのであれば,それは本稿の 2節でも述べたように1/3に限定されており,残りは被用者年金制度が被保険者とその被扶養配偶者の数に応じて負担する拠出金で賄われている。
となると,二階部分の被用者年金を選別支給・任意加入制に変更したなら,報酬比例で高額の保険料を負担しながら,将来給付を削減されることが確実な勤労世代の加入者が制度から脱退し,基礎年金の財政が一段と悪化するのは必至であろう。これでは,基礎年金の増額どころでなくなる。
結局,こうした自己撞着は,負担と受給の対応を基礎にして設計された給付の局面へ選別主義を導入することによって,所得再分配目的を達成しようとしたことに起因している。そうであれば,給付は普遍主義で設計することを所与として,所得再分配政策は税制の次元で実行することを検討すべきであろう。これについては,後ほど触れることにしたい。
次に②の目標を吟味しよう。年金制度における公平の問題を考える際には,世代間,世代内の公平を適正に定義することが重要である。これについては,野口悠紀雄氏の次のような整理がある(注27)。
(a)ある時点における年金受給者相互間および保険料納付者相互間の公平
(b)ある時点における年金受給者と保険料納付者の間の公平
(c)生涯をつうじての年金受給と保険料負担をめぐる世代間の公平
このうち(a)は制度間格差なり制度間調整といわれる問題や職業婦人と専業主婦の間の公平等を指す。(同一時点の世代内公平)
(b)は同時代の年金受給世代と保険料拠出世代の可処分所得のバランス等を指す。(同一時点の世代間公平)
(c)は世代ごとの生涯の給付・拠出比率あるいは内部収益率の格差として扱われてきた問題である。(異世代の生涯収支の均衡)
このうち,行政当局が主に問題にしてきたのは(b)であったが,多くの経済学者が問題にしてきたのは(c)であった。しかし,(a)(b)(c)は等しく「公平」といっても,各々の検証可能性,政策的含意が異なるうえに,問題有意性(そのことについて「公平」「不公平」を論じる意義がどれほどあるか)も違っている可能性がある。ここでは議論が集中してきた(c)の問題有意性を検討しておきたい。
経済学者の念入りなシュミレーションを待つまでもなく,完全賦課方式のもとでは,特別な措置が講じられないかぎり,年金制度の成熟化の途上で世代間の内部収益率に格差が生じるのは自明である。しかし,このことを根拠に世代間の格差を力説し,公的年金制度に危機意識を募らせる経済学者の見解に筆者は同調できない。その理由は,次のような堀勝洋氏による経済学者への反論に網羅されている(注28)。
第一に,加入者の超長期の生涯収支を,スライド率一定,割引率一定と仮定して試算し,世代間の収益率格差を云々することにどれほどの信頼性があるのか疑問である。
第二に,世代間の順送り扶養という社会契約のもとに賦課方式で運営されている公的年金を世代間の内部収益率のバランスで評価するのは,完全積立方式で運営される私的年金の評価と混同するものである。
第三に,これが最も重要と思われるが,世代間の公平を問題にするなら,公的年金という限られた領域での所得移転だけでなく,家族における可視的(親子間の双方向的な扶養,遺産相続等),不可視的(老人介護等)な所得移転,あるいは社会資本の移転等も含めて論じられる必要がある。こうした指摘の正しさを認めながら,なおも公的年金の内部収益率の世代間格差を(自明のものとして)取り上げて,ことさらに世代間の利害対立を描く経済学者の態度を筆者は不可解に思う。
むろん,だからといって公的年金の制度設計にあたって,世代間の公平が意味をなさないというわけではない。問題は,それを異なった社会・経済環境のもとで経過する異世代の加入者の生涯の収支を指標にして論じる点にある。しかも,各世代自体がその内に多様な経済的属性のコーホートを抱えているとなれば,なおさら(c)の意味での世代間の公平を問題にすることには限界がある。
世代間の公平をいうなら,むしろ,(a)の意味での公平を問題にする方が,保険料拠出世代と年金受給世代の所得のバランスの比較可能性の点でも,世代間の利害調整のための指標という点でも,意味があるだろう。現実の行政上でも,同時代の世代間の所得のバランスを目安に年金給付水準の見直しがなされてきたことは周知のとおりである。ただ,当該所得を税・社会保険料負担控除前の所得でではなく,控除後の可処分所得でバランスを測るべきであるという指摘は合理的である。
最後の目標④は二つの内容を含んでいる。ひとつは年金と他の社会福祉政策(ここでは特に医療福祉)との統合,連携をどう図るかという問題であり,もうひとつは社会保障としての年金給付を税制をつうじた財政福祉(tax expenditures)とどのように関係づけるかという問題である(注29)。後者は目標③で扱う年金税制のあり方につうじるテーマである。
基礎年金の拡充
では本稿の3節で示した厚生年金の給付の状況,4節で示した高齢者世帯の所得と居住の実態をふまえる,本節の冒頭で提示した①〜④の目標と整合的な年金制度改革とはどのようなものであろうか。
表13は平成元年の『全国消費実態調査報告』に収録されたデータにもとづいて主な年間収入が年金・恩給である世帯を,年金・恩給受給額の多寡を基準にして10の階級に区分し,各階級の一世帯当たりの経済諸指標の平均値を表したものである。
それによると,①一世帯当たりの年金・恩給受給額(年額)は40万円未満から360万円以上まで広く分布していること,②階級ごとの年金・恩給受給額と年間収入,貯蓄現在高,住宅・宅地資産額の間には整然とした正の相関関係がみられること,③年金・恩給受給額と持家率の間にも,下位の階級で変則がみられるものの総じて階級が上位にすすむにつれ持家率が上昇するという関係があること,がわかる。
このことは,本稿3節の冒頭で紹介したLSEのジョンソンがイギリスでの年金給付について指摘したのと同じ傾向,すなわち,現状の公的年金は最もそれを必要としない高齢者世帯により多く配分され,それを最も必要とする高齢者世帯にはわずかしか配分されていない,という逆進性がわが国にも厳然とみられることを物語っている。
そこで,救貧的な選別主義に回帰することなく,公的年金のこのような逆進的配分を是正するとしたら,基礎年金の給付水準を引き上げることによって,公的年金のなかでの報酬非比例部分のウェイトを高める以外ない。
より現実に即していうと,基礎年金の給付水準の引き上げには次のような重要な意義が認められる。
①1980年代以降の福祉見直し,福祉における公私の役割分担論の流れのなかで,年金の分野でも1985年の制度改革により,厚生年金への国庫負担は打ち切られ,企業年金による公的年金の補完,上乗せが強調されてきた。
しかし,厚生年金基金による補完・上乗せの実態は本稿の3節で示したように,設立形態間で大きな格差がみられるとともに,全体として上乗せはもとより代行給付もいたって不満足な水準にある。また,給付の水準以前に企業年金は受給権の面でも実質価値の保障という点でも大きな限界をはらんでいる。
そればかりか,公的年金そのものも私的年金と同じ報酬比例要素が大きなウェイトを占め,勤労時代にどのような給与水準の企業に,どれだけ勤続したかが老齢厚生年金の受給水準を左右する仕組みになっているのである。
であれば,報酬非比例の基礎年金の給付水準を引き上げることは,企業年金には期待できない公的年金固有の役割(特別な要件を付けない受給権の保障,終身給付制,物価スライド・再評価制による実質価値の保障,受給者間の所得水準の平準化等)を復元・強化する意義をもつ。
②報酬・勤続に依存しない基礎年金を引き上げることは高齢の女性,特に近年増加の傾向にある女性単独世帯の最低所得保障という点で重要な意義をもっている。
表6に表されているように,基金よる給付状況において,女性の受給額は同性内での設立形態間の格差に加えて,各設立形態内での対男子との格差が著しい。単独設立の男の平均受給額を100とすると,総合設立の女の平均受給額は22.6となっている。
その最大の要因が平均標準給与の男女間格差にあることはいうまでもないが,給付水準の格差以前に中途脱退等による加入員資格喪失率も男 11.7%に対して,女は19.7%ときわめて高い。これによって,受給権の面でも男女間に大きな開きが生じていることになる(注30)。
ところで図5によると,近年単身の高齢者世帯が増加する傾向にあるが,その大半は女性の単独世帯である。これは主として平均寿命の男女間の開きによるものと思われるが,今後これに加えて非婚の女性の増加や離婚率の上昇に伴って,高齢女性の単独世帯はさらに増加するものと見込まれる。
しかるに,前出の表11でこの種の世帯構造の所得水準の分布をみると1/3が年収100万円未満の階級に属している。このような結果をもたらした要因を検証した資料は見当たらないが,女性の勤労時代の低い給与水準が報酬比例年金に反映したことも一因であろう。
またサラリーマンの専業主婦で,夫の受給期間前に離婚した単身女性の場合,遺族基礎年金,遺族厚生年金の受給権はない。
以上のような実態を考慮すると,勤労時代の就業実績に依存しない基礎年金のウェイトを高めることは女性,とりわけ単身女性の高齢期の最低所得を保障するという点で大きな意義をもつといえる。
③先に本節で筆者は,基礎年金=普遍主義,所得比例年金=選別主義という給付方式は実行不可能であると述べた。しかし,そのことは年金に代表されるような貨幣的ニードを真のニードに応じて重点給付するという考え方を全面排除するものではない。基礎年金といっても普遍主義があてはまるのは加齢による所得稼得能力の低下・喪失という普遍的なリスクを対象とした社会保険である老齢基礎年金であり,より個別・具体的なリスクを対象にした障害基礎年金はげんに選別主義で給付されている。
ところが,現行の障害年金は同じ障害の発生であっても,65歳以前(受給期間前)に発生したときは1級でいうと年額906,600円の障害基礎年金が給付されるとともに,厚生年金保険でも老齢厚生年金の25%相当が障害厚生年金として支給されるのに対し,65歳以降に発生したときは給付の対象になっていない。つまり,寝たきりや痴呆といった高齢障害は障害年金の対象とされず,それらの介護に要する費用は障害年金で保障されていないのである。
かといって,現在の老齢基礎年金もこうした高齢障害のケアに要する費用を保障することを予定しているわけではない。しかも,在宅ケアの場合,介護にあたるのは多くの場合女性であるが,そのために女性は有給の仕事をやめたり,不定期の職に変更したりする例が多い。その結果女性は,勤労時代に所得を減じるばかりでなく,高齢期に報酬比例,勤続比例の年金も喪失したり,減じたりすることになる(注31)。
こうした現実を考えると,65歳以降の高齢期に特有の障害も障害基礎年金の支給対象に含めるよう制度を改革することが強く望まれる(注 32)。これは,選別主義か普遍主義かという主義の次元の問題ではなく,選別支給の対象を切実な実態に照らしてどう見直すかの問題である。
受給段階課税の徹底と年金制度への増収の還元
ここまでの行論において筆者は,公的年金が高齢者世帯の所得と資産保有に関して逆進的に給付されている現状を注視しながらも,公的年金を低所得世帯に選別支給するのは実行困難であり,現行の二階建ての給付・負担構造となじまないと述べてきた。
そこで,公的年金の給付を通じた逆進的な所得分配を是正する実行可能な方法はなにかを考えていくと,年金受給の段階での課税のあり方が問われることになる。
わが国の現行の年金課税は拠出段階非課税,積立金運用益非課税,受給段階課税という支出税的な方式を建前にしている。しかし実際は,公的年金等特別控除の措置が採用・拡充され,老年者控除を合わせると,他に所得がないかぎり,65歳以上の老齢年金受給者はほとんど課税範囲に入らないという状況になっている(注33)。
こうした公的年金等特別控除の根拠は,老後の所得保障という社会保障給付に課税はなじまないという発想以外見当たらない。しかし,低所得層は公的年金受給分を課税ベースに算入してもしなくても課税最低限を超えることはないから,特別控除が低所得の高齢者を優遇しているわけではない。
むしろ,表11〜13で示したような逆進的給付のもとで現行のような公的年金等特別控除を採用すると,所得控除による税負担軽減の効果は限界税率の高い高額所得層に傾斜的に現れることになる(注34)。
しかし,たんに高齢者であるというだけで課税上優遇され,垂直的公平が無視されるのは問題である。むしろ,給付が受給者の経済状態を問うことなく普遍的に,あるいは報酬比例的になされている以上,課税上は特別控除を全廃して受給額すべてを課税ベースに算入し,累進税率を適用することが要請される。
こうした年金の受給段階課税の徹底は,①財政福祉としての税務上の特別控除が社会保障としての年金給付の逆進性を固定ないしは累進している現状を改め,高齢世代内での垂直的公平を確保するという意味でも,②あらゆる世代の所得をその源泉のいかんを問わず税務上で同等に扱うことにより,同時代の勤労世代と高齢世代の世代間公平を確保するという意味でも,大きな意義をもっている。
さらに,その結果得られる税の増収分を基礎年金への国庫負担の引き上げという形で公的年金制度へ還元するならば,本節で先に提言した基礎年金拡充の実行可能性を財源面で担保することにもなるであろう(注35)。
6 結びにかえて
本稿を終えるにあたって,三浦〔1992〕177ページで引用されている朝日新聞1981年7月11日付の社説のなかの「社会的弱者に強く,政治的強者に弱い」というフレーズが筆者の印象に鮮明に残っている。これは前日提出された臨時行政調査会の「行政改革に関する第一次答申」に対する論評の一節である。1980年代以降のわが国における年金制度改革(論)に,こうしたフレーズがあてはまるところがなかったかどうか,考えてみたい気がする。
経済学者のこれまでの年金制度改革論でも,本稿で指摘した給付の逆進性や税務上の特別控除の高額所得者優遇効果が既に精粗の差はあれ指摘されてきたし,それを是正する提言も部分的にはなされてきた。
しかしその一方で,経済学者は世代間の受給・負担比率の格差の試算に精力を注ぎ,現行の賦課方式が現役世代にとっていかに不利なものであるかを力説して,世代間の負担と受給のアンバランスの是正を唱導してきた。そして,その過程では,モデル年金や統計上の平均値にもとづいた高齢者富裕論が繰り返されてきた。
しかし筆者は,現役・高齢という世代の二分法に立脚した年金制度の現状認識と,それをふまえた政策提言が,福祉の現場での切実なニーズをどれほど汲み上げたものなのか,所得分配上の社会的公正にどこまで寄与するものであるか,疑問に思えてならない。
この点ではむしろ,社会福祉の現場を直視した論稿,特に,堀〔1991〕,都村〔1984〕,都村〔1990〕,三浦〔1992〕から,さらにまた,自らの家族内での両親介護の体験をスプリング・ボードにした宮島〔1992〕から,多くの啓発を受けた。そして,末尾の一言になってしまったが,本誌『会計検査研究』とのかかわりでいうと,第4号(1991年9月刊)に掲載された飯塚正史氏の論文「社会保障で日本は沈まない」から受けた同じ趣旨の,しかし,より強烈な刺激が本稿を書き続ける筆者自身のスプリング・ボードとなった。このことを付記して結びにかえたいと思う。
参考文献
厚生省年金局数理課監修〔1993〕『目でみる年金』平成5年版,社会保険研究所。
厚生統計協会〔1992,1993〕『保険と年金の動向』(『厚生の指標』臨時増刊)
厚生年金基金連合会〔1993〕『厚生年金基金事業年報』平成3年度,厚生年金基金連合会数理部。
小柳長明〔1990〕「高齢単独世帯の居住状況とその政策課題」『国民生活研究』第30巻第2号。
佐々木伯朗〔1992〕「厚生年金基金についての研究ノート」『証券研究』第101巻。
ジョンソン・ポール.斎藤美彦訳〔1993〕「イギリスにおける年金改革:問題点と可能性」『社会科学研究』(東京大学社会科学研究所)第45巻第1号。
総合研究開発機構〔1992〕『長期的な税制のあり方に関する研究』第4段階報告。
醍醐聰〔1992〕「土地保有利得税の会計学的考察」『経済論叢』第150巻第1号。
高山憲之〔1981〕「厚生年金における世代間の再分配」『季刊現代経済』1981年夏。
高山憲之〔1992〕『年金改革の構想』日本経済新聞社。
高山憲之〔1993〕「年金改定方式見直しを」『日本経済新聞』1993年10月18日,「経済教室」。
戸塚達也〔1992〕「企業年金の新たなる発展に向けて」『週刊社会保障』No.1703。
都村敦子〔1984〕「社会保障と税制」社会保障研究所編『リーディングス日本の社会保障3 年金』有斐閣,1992年,収録。
都村敦子〔1990〕「高齢社会と家族援助」金森久雄・伊部英男編『高齢化社会の経済学』東京大学出版会,1990年,所収。
日本生産性本部〔1992〕『ストック格差是正のための所得再分配政策』
野口悠紀雄〔1984−a〕「公的年金における受給・負担構造の世代間格差」『季刊現代経済』1984年春。
野口悠紀雄〔1984−b〕「公的年金の厚生省試算に異議あり」『エコノミスト』1991年3月12日。
野口悠紀雄〔1990〕「現行の『厚生年金』,ここが問題だ」『プレジデント』1990年9月。
藤井良治〔1992〕「年金制度の課題と将来」『週刊社会保障』 No.1701。
Brian,Abel—Smith and Kay Titmuss(ed.) 〔1990〕,The Pilosophy of Welfare ,Selected Writing of Richard M.Titmuss,Allen&Unwin.
堀勝洋〔1991〕「公的年金と世代間の公平」『季刊・社会保障研究』第26巻第4号。
三浦文夫〔1992〕『〔増補〕社会福祉政策研究』全国社会福祉協議会。
宮島洋〔1992〕『高齢化時代の社会経済学』岩波書店。
村上清〔1989〕「厚生年金基金による代行の将来」『生命保険経営』第57巻第6号。
山崎泰彦〔1991〕「社会保障の新しい財源政策」『季刊・社会保障研究』第27巻第1号。
[注]
1)例えば,年金審議会「国民年金・厚生年金保険制度改正に関する意見」1993年10月12日。
2)これについては,宮島〔1992〕第3章で詳しい検討がなされている。
3)この点,宮島〔1992〕42ページ参照。
4)例えば,厚生統計協会〔1992〕41−42ページ,高山〔1992〕86−93ページ。
5)高山〔1993〕を参照。
6)村上〔1989〕3ページ。
7)村上〔1989〕4ページ。
8)戸塚〔1992〕48ページ。
9)藤井〔1992〕99ページ。
10)厚生統計協会〔1993〕179,185ページ。
11)・12)・13)高山〔1992〕138ページ。
14)この報告は,ションソン,斎藤美彦訳〔1993〕として公にされている。
15)このような問題意識から設立形態別に基金の業務内容,資金運用の実態を分析した文献として,佐々木〔1992〕がある。
16)厚生統計協会〔1993〕189ページ。
17)高山〔1992〕91ページ。
18)この点については醍醐〔1992〕33−34ページを参照いただきたい。また,高齢者世帯の住宅問題については,小柳〔1990〕が詳細な検討をしている。
19)こうした社会福祉の思想潮流については,三浦〔1992〕第14章でサーベイがなされている。
20)ここでは野口〔1984−b〕,野口〔1990〕,日本生産性本部〔1990〕を参照。日本生産性本部〔1990〕は,日本生産性本部の委嘱を受けて,経済政策研究所内に組織された野口氏を主査とする研究チームがまとめた報告書であり,その大要は野口氏自身の見解に相当するとみなしてさしつかえないと思われる。
21)日本生産性本部〔1990〕63ページ。
22)日本生産性本部〔1990〕61ページ。
23)野口〔1984−a〕,野口〔1990〕。
24)厚生統計協会〔1993〕179ページ。
25)厚生省年金局数理課監修〔1993〕29ページ。
26)高齢者世帯の最低所得保障に当たる公的年金を基礎年金に限定する野口氏の解釈については,堀〔1991〕415ページでその非現実性が指摘されている。
27)野口〔1984−a〕5ページ。
28)堀〔1991〕。
29)福祉を,社会福祉(social welfare),財政福祉(fiscal welfare),職域福祉(occupational welfare)という三つのカテゴリーに整理したのはリチャード・ティトマスである。(Brian,Abel‐Smith and kay Titmuss(ed.)〔1990〕,p.45.)
30)厚生年金基金連合会〔1993〕37ページ。
31)都村〔1990〕259−260ページ参照。都村はこの論稿のなかで厚生省の『人口動態社会経済面調査報告』(1987年)にもとづいて家族内における高齢者介護の実態を詳しく分析している。それによると,親族介護者の男女比は5対95で介護を担っているのはほとんど女性であること,介護者が子の配偶者の場合,その19.7%が介護のために勤めをやめ,20.1%が介護のために休職・休暇をとっていること等を紹介している。
32)こうした提言は,既に小林〔1990〕,高山〔1990〕186−187ページにおいてなされている。
33)これについては,都村〔1984〕346ページ,宮島〔1992〕257ページ参照。
34)データは古いが,都村〔1984〕は,1980年当時の老年者年金特別控除と老年者控除が年金受給者にもたらした税制上の給付を所得階級別・配偶者の有無別に概算している。
35)こうした提言は既に都村〔1984〕355−356ページにおいてなされている。なお,他にも,公的年金特別控除の廃止を主張する論者は多い。高山〔1992〕157ページ,宮島〔1992〕第11章,総合研究開発機構〔1992〕26ページ等。