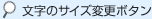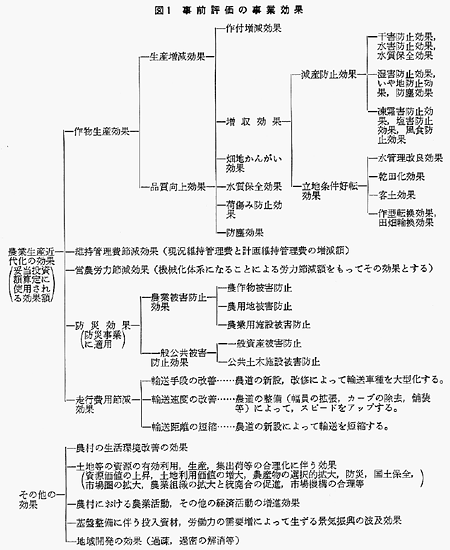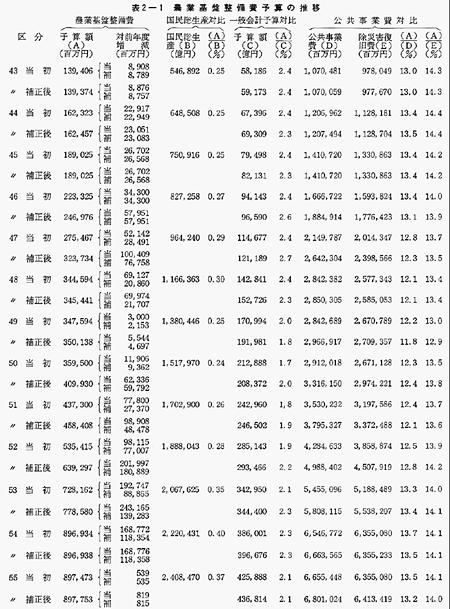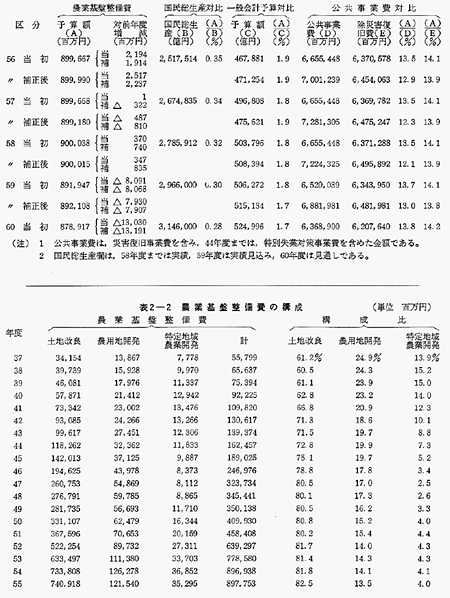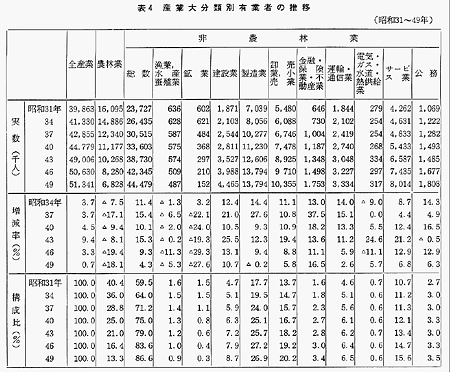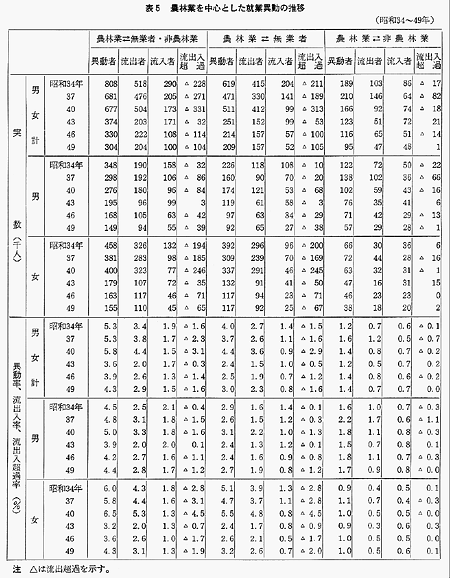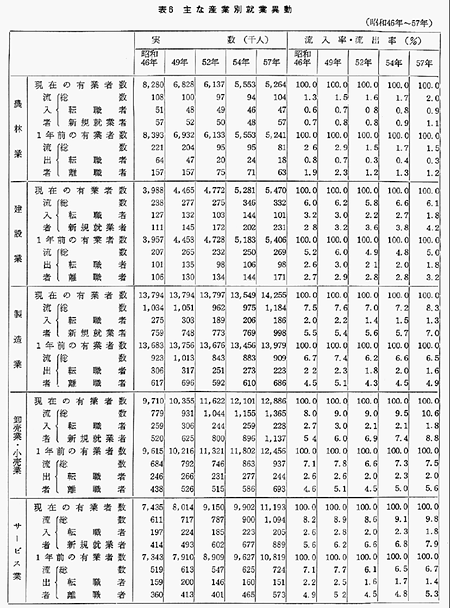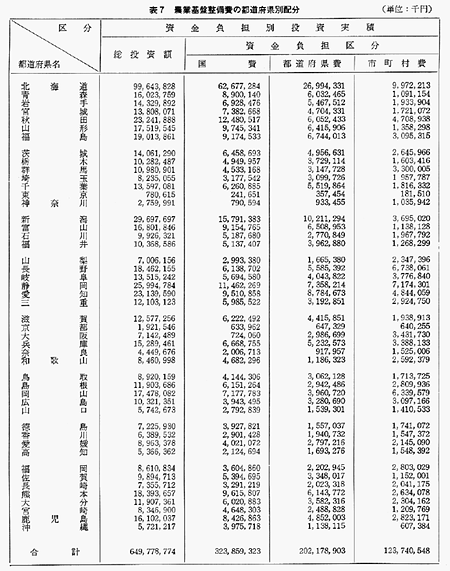第7号
会計検査と政策評価
——土地改良事業の事例をめぐる政策分析論的考察——
伊藤 大一
伊藤 大一
(埼玉大学教授)
1930年生まれ。東京大学法学部卒業。北海道大学法学部教授,オックスフォード大学セントアントニーズ・カレッジ客員研究員を経て,1987年より現職。同大学行動科学情報解析センター長。行政学及び政策分析専攻。日本行政学会,日本政治学会,公益事業学会及び英国王立行政学会所属。主な著書に「現代日本官僚制の研究」東京大学出版会,1980年;「政策科学の基礎知識」(共著),ぎょうせい,1985年:「Dynamic and Immobilist Politics in Japan」(co-author)Macmillan, 1988年;「Promotion and Regulation of Industry in Japan」(co-author)Macmillan, 1991年がある。
Ⅰ 業績検査にたいする期待と現実
会計検査は政策評価にどこまで踏み込めるか,また,踏み込むべきか——これは,現在,多くの国で会計検査機関が直面している深刻な「原則上」の問題である。たとえば,英国会計検査院(National Audit Office)のドゥワー(David A. Dewar)氏は,「経済性・効率性・有効性検査(=業績検査)の対象範囲はどんどん拡大し,またその検査方法もますます深く掘り下げたものとなっている。ただ,このような仕事——とくに有効性検査——にたずさわる調査官は誰でも,遅かれ早かれ,政策にかかわる事項をどのように扱うつもりなのかと問われることになるだろう。各省をはじめとする検査対象機関としては,検査院が政策問題を正当な検査権の範囲内にあるものと考えているのかどうか——また,どこまでをそうだと考えているのか——を知りたいと思うだろう。かれらとしては,もし検査院が個々の政策決定のメリットを直接的に批判しているように思われたときには,必ずや強い拒否反応を示すに相違ない」と述べている(注1)。
日本の場合も,事情はほぼ同じであろう。たとえば,会計検査院の委託調査(平成3年度)である『政策評価に関する調査研究』によると,「わが国会計検査院では,合規性検査,経済性・効率性検査に加えて,検査の観点を有効性にまで拡大することによって,業績検査のうち事業のもたらす直接的な結果に対する検査,すなわち成果達成度検査の段階までを行ってきている」という。だが,そうはいっても,「こうした有効性の観点からの業績検査は,現状においては,政策・事業の間接的効果を含む総合的な効果(outcome)ではなく,事業の直接的な結果である中間産出物(output)の利用率等に着目し,それが十分でないと判断される場合に,その事業の当初計画された目的を達していないと判定するケースが主となっている」ことは否定できない(同書,49-50頁)。いうまでもなく,これは——後に触れる検査「技術上」の問題もさることながら——政策問題をどこまで「正当な検査権の範囲内にあるもの」と考えるかという「原則上」の問題について,検査対象機関の反応を予測しつつ,会計検査院が慎重な立場をとっていることの現われなのである。
いったい,どこで線を引いたらよいのか。「検査院として正当に弁護することができ,しかも(政策評価という)有意義な仕事を不当に禁圧することなく,経済性・効率性・有効性検査の展開を可能にするような,弾力的ではあるが,しかし譲ることのできない線」とは,具体的にどのようなものであろうか。
この問いに一般論の形で答えることは,それほど難しいことではない。すなわち,一方,「検査院は,政策目的(policy objectives)のメリットを問題にするために在るのではない」。いかなる政策目的を追求するかは,検査対象機関がそれぞれの権限と責任において決定すべきことなのである。しかし同時に,他方,検査院として,政策が適正に形成されているか,またそれが経済的・効率的かつ有効に実施されているかといった点に関心をもつということはしごく当然なことである。すなわち,「検査院は政策手段の選択とその運用にかかわるのである」——と。だが,果たして,これで実際に役に立つ目安が与えられるであろうか。ドゥワー氏も言うように,「政策目的のメリットと政策手段の運用とを区別してみたところで,両者の間にはなお広大な中間地帯が横たわっており,そこにはルールらしきものはほとんど存在していない」のである(注2)。
おそらく,会計検査が政策評価にどこまで踏み込めるか——また,踏み込むべきか——について,実際に役に立つ限界基準を一般的なタームで表わすことは,すくなくとも今の段階では,まず不可能に近い。それは政策問題の性質によっても違ってくるし,それぞれの政策を担当する行政機関の基本的なスタンスによっても違ってくる。たとえば,上記『政策評価に関する調査研究』によると,干拓事業に対する会計検査においてはかなり踏み込んだ有効性評価が行われているというが,これはたまたま好条件が重なり合った結果であって,この検査事例を直ちに一般化することは困難であろう(同書,50頁)。
むしろ,今の段階でなしうること——また,なすべきこと——は,会計検査と政策評価のインターフェイスをいくつかの個別局面に分解し,それぞれの局面について実際に役に立つ限界基準を見つけ出していくことであろう。つまり,基準作成のための各論的な作業である。このような作業が実証的に積み重ねられることによって,いつの日か,限界基準を一般的なタームで表わすことが可能になるのではないか。
ところで,このような個別局面の一つに,「政策目的の明確化」ということがある。すなわち,業績評価の基本形は政策目的が現実にどれだけ達成されたかを評価するところにある。そのさい,達成状況を直接的な成果で測るか総合的な成果で測るかにより評価の深度に違いが出てくるものの,評価の基本形自体には変りがない。それはあくまでも目的を基準とする評価なのである。したがって,目的が明確に定められていることは,政策評価の大前提であるといってよい。ところが,実際には,肝心なこの政策目的が明確に定められていない場合が少なくない。このような場合には,検査院として,先ずそのことを明らかにする必要がある。すなわち,「政策目的およびそれに関連する下位レベルの目的ないし目標に重大な明確性の欠如がある場合,検査院がその点に注意を喚起し,必要とあればこれを公にすることは原則上可能である。これは政策目的のメリットに批判を加えることにはならない」(注3)。のみならず,このような場合,検査院の側で,すすんで何が政策目的であるか——というより,むしろ,何が政策目的であると考えるべきか−を明らかにすることも,状況の如何によっては,許されるであろう。これがここにいう「政策目的の明確化」である。
では,この「政策目的の明確化」が許される——あるいは,むしろ,求められる——のは具体的に如何なる状況の下においてであろうか。ドゥワー氏によると,「明確性の欠如」が生ずるのは,とくに(1)政策が複数の官庁により共管的に決定される場合,および(2)何年もの時間を経て,当初の決定とは異なる新たな決定が下された場合,であるという(注4)。だが,このような場合に,検査院の側で何が政策目的であるかを明らかにすることには,リスクが伴う。それは,事実上,異なる見解のいずれか一方に与することにより,政治的対立の渦中に巻き込まれる惧れがあるからである。
これに対し,(3)何年もの時間を経て,事情が変わり,当初の目的が目的としての意味を失ってしまったにもかかわらず,新たな目的が設定されない場合——これは上記(2)の変形ともいえるが——には,どうであろうか。この場合には,検査院が検査結果に基づいて,担当官庁に代り,政策目的が何でありうるか——またあるべきか——を明らかにしても,政治的対立に巻き込まれる惧れは小さいであろう。しかも,実際には,連続性の意識が強く,政策の変更が容易ではない行政の世界において,このような場合は決して稀ではない。そこで,ここでは,この決して稀ではない事例を一つとり上げ,そこにおいて検査院がどのように政策評価機能を発揮しうるか——また,発揮すべきか——を考察してみることにしよう。
なお,あらためてことわるまでもないが,会計検査はどこまで政策評価に踏み込めるか,また踏み込むべきかという「原則上」の問題とは別に,「技術上」の問題がある。つまり,政策事項に踏み込むことが技術的に可能かどうか——とくに,政策評価を可能にする評価技術が開発されているかどうか——という問題がある。もちろん,実務の面では,この両者を区別することは必ずしも容易ではない。技術的に不可能であるということがしばしば政策評価への踏み込みを原則的に拒否することの根拠に用いられてしまうからである。しかし,理論的には,この両者を区別して考える必要があろう。
ところで,政策事項への踏み込みが技術的に可能であるための必要条件は,ドゥワー氏も指摘しているように,調査官が個別の政策の決定と実施にかかわる知識,ノウハウを,ある程度,当該政策を担当する官庁の職員と共有しているということであろう。すなわち,「何よりも先ず,主要な事業なり政策なりの検査に当たる者は,関連のある政策問題について,つねに多くのことを知っている必要があるという点を認識することが大切である。もし検査対象機関が置かれている政策のコンテクストといったものが十分に理解されていないならば,効果的な検査を実施することもできないであろう。調査官としては,優先順位の決定を左右するような諸々の環境,意思決定一般および検査対象になった特定の分野に関する意思決定に影響を及ぼすような諸々の要因について,十分な理解をもっている必要があるのである」(注5)。
Ⅱ 土地改良事業における問題状況
ここでとり上げる事例は,土地改良事業に関するそれである。土地改良事業における政策評価については,行政管理庁(当時)の委託による先駆的な調査研究がある(注6)。それによると,農業基盤整備事業のうちで既耕地を対象とする狭義の土地改良事業——予算額でみると,昭和42年度以降,農業基盤整備費の70%以上を占め続けている——は土地改良法で定められた土地改良長期計画(閣議決定)に従って実施されるものであり,実際には,第1次計画(昭和40-49年)以来,今日に至るまで3次にわたり計画が作成され,実施に移されてきた。
そして,この事業の特色は,「事業の適否決定の前段で行われる調査の段階で,各事業の経済効果の検討と測定が必ず行われ,現行基準で事業の総経費に対する効用比,すなわち経済効果が1以上でなければ採択されないことになっている」点にある,という。すなわち,いわゆる直接効果——図1でいえば,「農業生産近代化の効果」——のみを効果に見立て,便益に算入したうえで,費用便益分析の手法を用いて事業効果の事前評価を行うことが制度化されているのである。もっとも,これに対しては,費用便益分析という「従来の経済評価方式に組み込まれた便益が公共的利益に結びつくということの説得力が疑問視されることもしばしばであり,各事業を総合的に評価するシステムの確立の必要が指摘されている」という。だが,現実には,そのようなシステムはまだ見つかっていない。そこで,この調査研究も「特定の土地改良事業の適否なり優先順位を決定するさいの事前評価方式として従来の経済評価方式に基本的に代替しうるものは見当らない」という農水省の主張をそのまま受け容れる結果になっているのである(注7)。
問題は,おそらく,土地改良事業の目的をどう考えるかにある。もしそれが「農業生産近代化の効果」——とくにその中心をなす「作物生産効果」——を増大させるところにあるとすれば,「従来の経済評価方式」でも政策評価を行うことが十分可能であろう。だが,「作物生産効果」を増大させることが,果して,「公共的利益」に合致するであろうか。もし合致しないとすれば,それはもはや目的としての資格をもちえないことになる。費用の大半を国や自治体の予算でまかなっている土地改良事業として,その目的はあくまでも「公共的利益」に合致するものでなければならないからである。
会計検査問題研究会の『業績検査に関する研究報告書』(平成2年)は,この点について,一歩踏み込んだ考察を加えている。すなわち,そこでは,先ず「評価の原則的手法は費用便益(効果)分析である」という前提のもとで,各種の公共事業を事前評価が行われているものと,行われていないものとに区分している。治水・一般有料道路・土地改良・林道・沿岸漁場・新幹線鉄道などは前者に属する。後者に属するものとしては,治山・海岸・住宅・環境衛生・公園・造林・工業用水・離島電気・鉄道防災などがある。そして,下水道・一般道路・漁港・港湾・空港・鉄道などはその中間型態として位置づけられている。
この区分は重要である。なぜなら,事前評価が行われていない事業においては,たとえ「明確性の欠如」はないとしても,政策目的が操作的なタームで表示されることは稀で,それだけ検査結果に基づき政策目的を事後的に読み込む余地が広いからである。このような場合には,検査院の側で何が政策目的であるかを明らかにしても,政治的対立に巻き込まれる惧れは小さいであろう。これに対し,事前評価が行われている事業においては,政策目的が操作的なタームで表示されているから,その読み込みを行う余地は狭められてくる。当然,検査結果に基づいて独自に政策目的を明確化することには,大きな政治的リスクを伴うことになろう。
では,具体的に,土地改良事業の場合,この政治的リスクの問題にどう対処したらよいであろうか。『業績検査に関する研究報告書』は,ここで,二元的なアプローチを試みている。すなわち,それは,一方で,現行の事前評価に使われている「農水省モデル」をそのまま受け容れ,「土地改良事業によって農家に帰属する直接的な経済効果」のみを効果とみなし,便益として計算するという方式の枠内で,事後評価を行っている。これは,行政管理庁の委託調査が「農業生産近代化の効果」の枠内で行われたのにほぼ対応する。そして,その中心は——行政管理庁の委託調査と同様——作物生産効果にあるとされているのである(図2参照)。
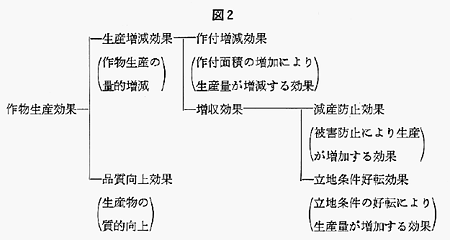
この点で行政管理庁の委託調査との間に違いがあるとすれば,それは評価基準の一つである所得償還率——いま一つの評価基準は総事業費と総効果額の比率を表わす投資効率である——に関連して,農家の自己負担に注意を向けている点であろう。すなわち,「この評価基準は農家負担金が農業経営の健全性を損うことがないかどうかを判定するために設けられたもので,農家経済ベースに着目して,平均的農家の限界貯蓄性向である0.4を基準値とし,事業採択の判断に用いている」——と(注8)。この自己負担の問題は,後に見る「隠された目標」との関連で重要な意味をもってくる。
このように「農水省モデル」の枠内で事後評価を行うことの意味は,言うまでもなく,それにより事前評価における計画値と実績値との間のズレ(=開差)があるかどうか,あるとすればどの程度であるかが明らかにされることにある。つまり,「有効性の観点から事業目的の計画に対する達成度の測定・評価を行う場合には,必ずしもすべての効果を把握する必要性はなく,法律で規定される事業目的を所与として,これに基づき事前の計画段階で計測されている農家に帰属する直接効果が実際どれだけであったかを検証することが第一義的に必要とされる」というわけである(注9)。開差があることが明らかになれば,そこからさらに,それが実施過程を含む政策それ自体——その欠陥——に起因するものであるのか,それとも事前評価のためのモデル——その欠陥——に起因するものであるのかが追究されることになろう。その結果,もし前者であれば,政策とくにその実施方法の軌道修正が行われることになり(=事後評価の実体的効用),後者であれば,「原モデルの修正」——技術的な調整——が試みられることになる(=事後評価の手続的効用)。
これはこれで十分意味のあることであろう。だが,『業績検査に関する研究報告書』はこれだけでは満足しなかった。すなわち,それは,他方で,「農水省モデル」の枠を越えて,独自の——より根本的な——立場から事後評価を行うことの必要性を訴えている。言い換えれば,農水省により設定された事業目的を所与とすることなく,むしろ検査結果に基づいて独自に目的を設定することの重要性を訴えているのである。
具体的には,それは,先ず,直接効果以外の「間接効果」に注目し,行政管理庁の委託調査とは異なる視点から,その内容を整理・再構成した(図3参照)。そのうえで,この「それ以外の効果」について,次のような重要な指摘を行っている。「現行の基準では,主に農家への直接的な効果を計測・算定しているため,国民経済的観点での価格低減効果や生産安定効果等は評価されていない状況である。これは,土地改良法の事業目的が農家経済レベルであることからは妥当と考えられる。しかしながら,農業環境が法律制定時(昭和24年度)の食糧増産から現在の減反政策へと変化してきており,また,土地改良事業には農家の受益者負担はあるものの,政府の財政援助措置がなされていることに鑑み,農水省において一部試行的評価がなされているように,今後は国民経済的見地からの効果を評価することも考慮する必要があろう」(注10)。
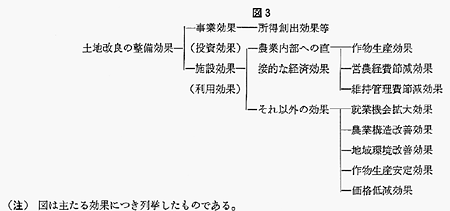
これは,正論である。実際,さきに触れたように,土地改良事業が公共事業として本格化したのは昭和40年代である。たとえば,表2-1,表2-2は昭和60年版の『国の予算』(財政調査会編),398-9頁からとったものであり,予算の推移を厳密に調べるためには数字をデフレートしてみる必要があるが,とりあえずはこの名目的な数字の動きからも,農業基盤整備費の対公共事業費比にはほとんど変化がなく,他方,農業基盤整備費のうちで土地改良費が占める割合は着実に増加していることが読みとれるであろう。つまり,この期間,土地改良事業費は実質的にも増加していると考えられるのである。
ところが,この期間は,他方で,米が生産過剰に陥っていく時期でもあった。米の生産と消費に関する細かい数字の引用は差し控えるが,たとえば,昭和46年には早くも食糧管理法に基づく政令で米の買入れ予約限度数量が設定されている。そして,昭和53年には水田利用再編対策指導要綱が制定され,いわゆる減反政策が行政指導の形をとって,本格的に実施されることになった。
これらの事実が意味していることは明白である。『業績検査に関する研究報告書』が示唆しているように,作物生産効果を中心とする「農家への直接的な効果」がもはや政策目的としての合理性を失ってしまったということである。土地改良事業は,実は,何か別の政策目的を実現するための手段として用いられていると考えざるをえない。そうでなければ,事業費の実質的な増加という上述の事実を合理的に説明することはできなくなってしまう。それはたんなる「後向きの所得補償」にすぎなかったということになってしまうのである。だが,このように事情が変わり,当初の目的が目的としての意味を失ってしまったにもかかわらず,新たな目的は未だに設定されていない。だとすれば,ここで,検査結果——または調査結果——に基づき,新たな政策目的が何であるかを実証的に明らかにするということが十分意味をもつことになろう。あるいは,建前上は未だに作物生産効果などが政策目的とされているというのであれば,それに代る本音の政策目的——マートン(R. K. Merton)の表現を借りれば,「表向きの目標」(manifest function)に代る「隠された目標」(latent function)——を明らかにするというように言い換えてもよい。いったい,それはどのようなものであろうか。
Ⅲ 「隠された目標」を検出することの意味
さきの引用からもうかがわれるように,『業績検査に関する研究報告書』としては,新しい政策目的として「国民経済的観点での価格低減効果」などを考えているようである。たしかに,将来的には,それは新しい政策目的にふさわしいものであると言えよう。だが,昭和40年代以降今日に至るまで,食糧管理制度のために市場メカニズムが正常に機能していない状況の下では,現実問題として,価格低減効果などは「隠された目標」たりえないと考えるべきである。
そもそも「隠された目標」があるかどうか。もしあるとすれば,それはどのようなものであろうか——この問題を解明するうえで有用な手掛りを提供してくれるのは,多くの場合,当該事業の実施にたずさわっている実務家の直感的な判断である。このような判断は,分析的な裏付けを欠くためにそれだけで政策評価を形作ることにはならないけれども,経験とファーストハンドな観察に裏打ちされているだけに,「一面の真理を衝いている」ことがすくなくない。
では,土地改良事業の場合はどうであろうか。私はこの事業を専門に研究したことはないけれども,いわゆる農業県を訪れる機会に恵まれたときには,努めてその実施にたずさわっている方達に会い,それが現実にどのような機能を果たしていると考えておられるかを聞き出そうと試みてきた。その結果を要約すると,土地改良事業には,「作物生産効果」という表向きの目標とは別に,次のような二つの目標が含まれている——と直感的に判断されている——ことが明らかになる。
一つは,農地集約化効果である。もともと農地を集約化して農業の生産性を向上させることは基本法農政の目標であったが,いわゆる自作農主義がネックになって,その実現ははかばかしくなかった。昭和43年の農地法改正はこのネックの解消を狙ったもので,実際,農地は多少集約化の方向に向かうが,ただこの変化は,実務家の直感的な判断によると,農地法改正の成果というより,むしろ土地改良事業の推進に伴ってもたらされたものではないかというのである。なぜそういうことになるのか,その因果関係を確定することは必ずしも容易ではないけれども,これが検討に値する見方であることには異論の余地がない。
いま一つは,離農抑止効果である。すなわち,土地改良事業は,その隠された機能として,農村ないし農業部門から人口の流出に歯止めをかけるような効果をもっていたというのである。これはまことに示唆に富む判断である。紙幅の制約もあるので,ここでは,この離農抑止仮設に的を絞って,それがどこまで検証に耐えるものであるか,検討を加えてみることにしよう。
先ず,離農抑止ということがそもそも政策目的たりうるか否かを考えてみる必要がある。いうまでもなく,政策目的というからには,それは何らかの意味で望ましいと判断される状態の実現にかかわるものでなければならない。そのような望ましいと判断される状態として,ここでは適正農業人口といったものを考えることができよう。つまり,人口のなかの一定割合が農業に従事していることが,一定水準の食糧自給率を維持するうえから,望ましいと考えられるわけである。
これに対しては,もちろん,反論の余地がある。たとえば,国際分業論の立場から,日本は第二次産業と第三次産業に特化すべきであって,食糧については全面的に輸入に頼ればよいという議論が考えられる。しかし,常識的——自給率がどうあるべきかについて十分に説得力のある理論が未だに存在していない以上,われわれとしては常識的に考えざるをえない——にいって,これは極論であろう。日本と類似の状況にある欧米の先進諸国がいずれも70%を上廻る食糧自給率を維持している事実に着目するならば,日本もそれにならうのが望ましいと考えることが常識的である。すくなくとも,40%前後という現状——これはもちろん農業生産性の低さに起因するものであろうが——は望ましいものではない。
問題は,それだけの自給率を維持するためには,どの程度の農業人口——適正農業人口——が必要であるかを見定めることである。これは,容易なことではない。それは,とくに農業の場合,生産を制約する条件が国により大きく異なるからである。たとえば,表3は先進諸国における産業部門別の就業者の割合を比較したものである(総理府統計局『就業構造基本調査報告(解説編)』,昭和49年版,54頁による)。だが,ここから日本の適正農業人口を推定することは難しい。地理的環境,細分化された土地保有形態,さらには兼業農家の増大といった耕作条件の相違を考慮するならば,アメリカやイギリス並みの低い線に設定することには無理があろう。強いて線を引くとすれば,ドイツ連邦共和国とフランスとの中間8-9%辺りということになるであろうか。
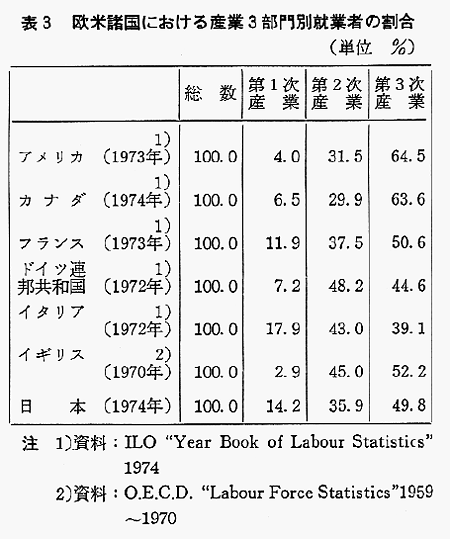
ただ,どこに線が引かれるにせよ,ある適正農業人口を維持することが望ましいという点については,それほど異論はないであろう。そこで,次の問題は,日本においてそれが実際に維持されていたかどうかである。表4は同じく総理府統計局『就業構造基本調査報告(解説編)』,昭和49年版,49頁からとったもので,昭和31-49年の期間における産業別有業者の推移を表わしている。ここから明らかなように,この期間を通じて,農業に従事する者の数は著しい減少を示した。もっとも,この減少分がすべて農業以外の産業分野に転じたわけではない。表5から読みとれるように,減少分の多くは無業者——主として家事——への異動であって,他の産業分野に転じた者はその1/4から1/3の範囲にとどまっている。
だが,それにしても,農業人口の減少は——すくなくとも昭和40年代の半ばまでは——すさまじいものがあった。もしこの傾向がそのまま続くとすれば,農業人口は早晩適正ラインを割ることになろう。だとすれば,農業からのこれ以上の人口の流出を抑止することは望ましい状態の実現に寄与することになる。言い換えれば,離農抑止は「隠された目標」としての意味をもつことになるのである。
では,土地改良事業は実際にそのような効果を発揮していたであろうか。上述のごとく,土地改良事業が本格化するのは昭和40年代に入ってからであるから,その効果が現われるのは40年代後半以降ということになろう。おかしなことに,昭和50年代に入ると,『就業構造基本調査』の解説編から表5のような農林業を中心とする就業異動の細やかな分析が消えてしまう。その代りに出てくるのは,表6に見られるような就業異動に関するより一般的な分析である(総理府統計局『日本の就業構造(就業構造基本調査の解説)』,昭和57年版,166頁による)。これでは,厳密な意味での時系列比較を行うことはできない。だが,それでも大雑把な比較を行うことは可能であろう。その結果は,明らかに,40年代後半以降離農が減少の方向にあることを示している。たとえば,表5によると,昭和43年を除き,昭和46年まで高い水準にあった農林業から非農林業への流出は,昭和49年にはゼロになっている。また,表6によると,40年代を通じて高い水準にあった農林業からの流出は,50年代前半に流入とほぼ均衡し,50年代後半になると逆に流入超過に転じている。つまり,農業人口が適正ラインを割ることになるのではないかという惧れは,ひとまず解消されることになったのである。
この変化は,数字の上では,表1に示された土地改良事業費の増加傾向と符節を合わせている。もちろん,ここから直ちに,土地改良事業は農業からの人口流出を抑える方向に作用したといった結論を導くことはできない。人口流出が止まったのは,たんに,流出しうる——または流出すべき——人口が流出し尽くしてしまったからにすぎないのかもしれない。かりに流出し尽くしていなかったにしても,流出が止まったのは土地改良事業以外の要因——これには各種の農業補助金や税制上の優遇措置のような政策的要因のみならず,地価の高騰から脱工業化の風潮にいたるさまざまな非政策的要因も含まれる——に因るものであるのかもしれない。
土地改良事業と離農の減少との間に因果関係があるかどうかを確かめるための,考えられる一つの方法は,事業費の増減と離農者の増減を県別にブレークダウンしたうえで,両者の間に有意な関係があるかどうか,クロスセクション分析にかけてみることであろう。これは,理論的には十分意味のある試みである。すなわち,事業費を県別にブレークダウンした数字は自治省の官房地域政策課が作成した『行政投資実績』から拾うことができる。たとえば,表7は昭和49年度版の『行政投資実績』(96頁)から拾い出したものである。これに対し,就業異動を県別にブレークダウンした数字をつかむことは,それほど容易ではない。『就業構造基本調査報告』の解説編には,そのように整理された数字が載っていないからである。しかし,その地域編に散在している数字を拾い集めて必要なデータをととのえることは可能である。
だが,実際には,こうしたクロスセクション分析から因果関係の有無に関し明確な結論をひき出すことは難しい。細かい計算結果の紹介は差し控えるが,それはおそらく事業費の県別配分が農業人口に比例してほぼ「平等主義的」に行われているからである。もしこれが地域特性等を考慮して「重点的」に配分されていたならば,重点的な配分を受けた地域とそうではない地域との間で就業異動に有意な差があったか否かをみることにより,因果関係の有無を判定することが可能になったであろう。現実には,この可能性が閉ざされてしまったのである。
このように見てくると,土地改良事業の「隠された目標」は離農抑止にあるのではないかという実務家の直感的な判断を分析的に裏付けることは,いまの段階では,難しいということになろう。それをするためには,おそらく,具体的な事例をいくつかえらび出し,それらについてヒアリングを含むインテンシブなケース・スタディを行うことが必要である。だが,他方,実務家の直感的な判断が誤りであることを示す証拠も見当たらない。ケース・スタディの結果がその正しさを立証するということは,大いにありうるのである。だとすれば,ここで話を一歩先へ進めて,土地改良事業にとって意味のある政策目的は離農抑止であると仮定してもあながち不当ではないであろう。いうまでもなく,これは,その検査結果——あるいは調査結果——に基づき,検査院の側で新たな政策目的を設定することが可能である,また望ましいことでもある,ということを意味する。
Ⅳ 会計検査における「後知恵」の効用
離農抑止が土地改良事業の政策目的として設定されたとすると,次の問題は,では,この政策目的を実現するうえで土地改良事業は最適の政策手段であったのか——もしそうでなければ,他にどのような代替手段があったのか——を検討するということであろう。これは,いわば政策評価のイロハである。ただ,この検討作業は実際にはそれほど容易ではない。それは,とくに代替手段を見つけ出すためには,当該問題——いまの場合,離農問題——に関する専門知識が必要だからである。したがって,それは第一次的には当該問題を担当する事業官庁がなすべき仕事であろう。会計検査院としては,さしあたり,当該官庁に対してそのような仕事に取り組むよう促せばよいということになる。
ただ,もしドゥワー氏も述べているように,「優先順位の決定を左右するような諸々の環境,意思決定一般および検査対象になった特定の分野に関する意思決定に影響を及ぼすような諸々の要因について,十分な理解をもっている」とすれば,会計検査院としても自ら代替手段を見つけ出し,土地改良事業との相対的な効果比較を行うといった方向に進んでいくことが考えられる。つまり,政策評価の面で,会計検査院が事業官庁に代位するわけである。このとき,会計検査は政策形成の次のサイクルに接続し,フィードバックの環は完結することになろう。
だが,飜って思うに,これは一種の「後知恵」(hindsight)である。そして,「後知恵」,とくに第三者のそれには,当事者が下した決定に対する批判の意味合いがこめられている——すくなくとも,批判の意味合いがこめられていると当事者に受けとられる——ことがすくなくない。たとえば,決定を下すにあたっては,これこれしかじかの要因を考慮に入れておくべきであった——といったような議論は「後知恵」に付きものなのである。さまざまな制約条件の下で決定を下さざるをえない当事者の立場からすれば,このような議論はアンフェアなものに聞こえるであろう。のみならず,客観的にみても,それは非現実な,たんなる繰り言にすぎぬ場合がすくなくない。
しかし,それならば,「後知恵」を無用のものとして片付けてしまうことができるか。ドゥワー氏は,この点について,次のような含蓄に富んだ言葉を残している。いわく——「いうまでもないことだが,検査院は,経済性・効率性・有効性の検査を行っているからといって,政策決定にたずさわる者が下した判断を"後知恵で批判しよう"(second guessing)としているわけではない。検査院は,たしかに後知恵を働かせることができるという利点をもっているけれども,それをたんに検査対象機関が困難な活動条件の下で,限られた情報に基づき,しかも厳しい時間的制約のなかで下さなければならなかった決定を批判するために用いるといったことはしないものである。……だが,そうはいっても,後知恵を働かせることが良い意味での刺戟(legitimate stimulus)を与えることになったり,どこか改善の余地がないか,あるいはこれまでに試みられたコントロール・システムのなかでとくに効き目があったのはどれかを教えてくれる指針として役立ったりすることがある。要するに,検査院の仕事というのは,学習過程(learning process)ができるだけ拡まるようにするとともに,それから得られる諸々の便益が他の活動分野にも及んでいくよう努めるところにあるのである」(注11)。
注:
1)David A. Dewar, The Auditor General and the Examination of Policy, in State Audit and Accountability, State Comptroller's Office, Israel, 1991, p. 95.
2)ibid., pp. 96-7.
3)ibid., p. 98.
4)ibid., p. 99.
5)ibid., pp. 97-8.
6)行政管理庁『行政作用の本質と機能に関する調査研究報告書』,昭和58年度,行政管理研究センター。
7)上掲書,149-51頁。
8)会計検査問題研究会『業績検査に関する研究報告書』,平成2年,110頁。
9)上掲書,115-6頁。
10)上掲書,120頁。
11)Dewar, op. cit., pp. 101-2.