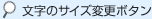第5号 巻頭言
"公共価値"と財政民主主義
深谷 昌弘
深谷 昌弘
(慶応義塾大学教授)
1943年生まれ。慶応義塾大学大学院博士課程修了。日本経済研究センター研究員,成蹊大学教授を経て1991年から現職。財政学および社会秩序形成論専攻。主要著作に『テキストブック財政学』,『公共財と社会システム』,などがある。近年の専らの関心領域は,合意形成であるが,これについての論文は,『成蹊大学経済学部論集』,『公共選択の研究』などの雑誌に数編を掲載。
はじめに
1986年から4年間にわたった本院「会計検査問題研究会」の一員として,検査院活動に関心をもって以来,"公共性"や"公共価値"を社会的に認定することと会計検査との関係をどう考えるか,という問題意識が心のなかにくすぶり続けていた。巻頭言を依頼されたとき,よしこの問題を少し掘り下げて考えてみよう,という気持ちを抱いてしまったのが,筆者にとっても,また,読者にとっても,不幸の始まりであった。なかなか整理がつかず,さんざんな苦しみを味わってしまった。あげくの果て,巻頭言としては,常軌を逸するほどの長文を寄せる仕儀となってしまった。さりとて,論文としては,まだまだ整理すべき点が多いし,完成度が低いと自認せざるを得ない。そんな本稿を読者にお読みいただくのはまことに心苦しい。しかし,合意形成という新しい視点を政策評価に取り込んだ意欲に免じて,以下,お読みいただければ幸いである。
Ⅰ 伝統的検査から政策評価への進展と財政民主主義
現代の市民社会において,政府は"公共価値"(Public Interest:公共の利益;ここで利益という言葉を使わないのは,その質的性格を考慮するからである)を追求すべき主体であると考えられている。"私の利益"や"貴方の利益"などの"私的利益"(Private Interest)と異なる"公共価値"とはどのような価値か。あるいは,価値の身分を規定している"公共性"(Publicness)とはどのような性格か。先進諸国の会計検査機関の業務が,伝統的検査から政策評価へと観点のウエートを移しつつある今日的状況において,このことを改めて問うことは極めて重要だと思われる。
近年,とりわけ,1960年代以降,アメリカ,カナダ,オーストラリア,イギリスなどの先進諸国の会計検査機関の活動は,個々の会計経理が予算や法令等に従って適正に処理されているかを問う最も伝統的な「合規性」検査から,より広い観点に立つ活動へと重点を移しつつあるといわれる。すなわち,個々の事業が経済的,効率的に行われているかを問う「経済性・効率性」検査へ,さらに最近は,政策そのものを評価するプログラム評価へと観点が拡大され,次第に,検査から評価ヘと重点を移しつつある。もちろん,このことは伝統的検査が不必要になったとか,重要性を低下させたとかいうことを意味するわけではない。それ以上の任務が要請されるようになったということである。
合規性検査は,個々の費目について予算・法令等の基準に照らして"非違"を検証し,非違があれば財務会計責任を追及する。経済性・効率性検査は,個々の事業について,より少ないインプットで同じアウトプットが可能であったのではないか,また,同じインプットでより大きなアウトプットが可能であったのではないかを検討する。不経済や非効率があった場合,それが規則違反によるものでなければ法的責任を追及するには至らないが,その指摘は事業主体の経営努力を問うていることになる。合規性の判定基準は規則であり,非違の検証はそのまま非難と制裁に直結する。経済性・効率性の判定基準はインプット・アウトプットの数量関係である。後者の場合,アウトプットの定義・測定に関して問題が発生しないわけではないが,ひとたび,この点について異論ない定義・測定が確立すれば判定は極めて明確であり,不経済・非効率の指摘は非難を意味することになる。したがって,合規性検査および経済性・効率性検査は,ともに,管理・統制機能を主たる任務としているということができる。
プログラム評価は,事業ないしカテゴライズされた事業群を政策プログラムとみなし,その政策の目的に照らして評価を試みるものだとされている。しかし,実際になされる評価活動の内容をみると,評価の視点は,その政策が目指す直接の目的に限定されていない。また,評価対象となる事象も,個々の事業や事業群のインプットとそれによって直接制御されているアウトプットとの関連に限定されていない。プログラム評価は,そのようなインプット・アウトプット関係を包摂する一般的相互依存関係から生じるアウトカム全体をさまざまな複合的視点から吟味する。すなわち,検査ではなく,"政策評価の試み"だということができる。"政策評価"とは,まさに,冒頭で述べた政策がもつ"公共価値"の評価であり,その政策が,公共部門が追求することに値するかどうかを問う,という意味である。また,その"試み"だというのは,事柄の性質上,検査機関はそれを試みる最も重要な立場にいる者の一人であるが,その評価を最終的に認定する特権的立場にいるわけではないという事情による。さらにいえば,民主主義社会においては,この特権を有するのは集合としての市民,つまり,国民であるが,"公共価値"の本来的性格がそのコミュニケーション的規範性にあるため,市民による認定は常に暫定的であり,たえず改変の可能性を潜在させているということを,ここで強調しておきたい,また,それゆえに,複合的視点からの評価にならざるを得ないし,そうあるべきだということも強調しておきたい。
「財政民主主義において,"公共価値"とは市民の合意によって形成されるものであり,そして,たえず形成され続ける可能性を確保されていなければならないものである」という主張が本稿の立場であり,この立場から,伝統的検査から政策評価への進展の意義を論ずることが本稿の目的である。
わが国の検査院にも最近似たような動向は認められる。すなわち,「合規性」検査から「経済性・効率性」検査へと検査の重点の移行が起こり,さらに,事業が所期の目的を達成し効果を上げているかを問う「有効性」検査がなされるようになった。しかし,有効性検査は,所期の目的があらかじめほとんど反論の余地がないほど明確な概念として把握できるものに関連して客観的事実をあげ有効性に関する問題提起をしている。プログラム評価と比較すれば,複合的評価視点の幅および評価対象となるアウトカムの領域を,ともに,狭く自己規制する一方で,それとの見合いで評価認定の確定性に固執する傾向がある。
政策評価としてのプログラム評価を会計検査機関が試みるとき,検査機関が担う機能は,合規性検査や経済性・効率性検査において担う管理・統制機能とは著しく異なってくる。結論を先取りしていえば,"公共価値の形成を巡る言論の自由広場"において"基調報告者"の一人として,また,主要パネリストの一人として任務を果たすということである。このような任務が検査機関に要請されることは,実は,論理的にみて財政民主主義の発展の当然の帰結なのであって,少しも不思議ではない。しかし,この任務機能がもつ他の検査機能との著しい性格上の違いは,いまだ充分理解されているとは言いがたい。わが国の現状は,先進諸国がすでに踏み出した検査から評価への進展過程における一つの過渡的姿であろう。しかし,わが国もまた何らかの形で上述したような意味の政策評価が必要になることは,民主主義的予算循環プロセスの発展の方向性から明らかである。検査院活動の新展開が健全に進行する上でも,政策評価を財政民主主義における公共価値の形成として理解することは極めて重要だと思われる。そこで,以下では筆者なりの試論的見解をまとめてみたいと思う。
Ⅱ 民主主義において"公共価値"は幻想か?
市民と国家との直接の経済関係を示すのが予算であり,財政である。西欧先進諸国において,君主支配から民主主義への移行における重要課題の一つが財政民主主義の確立であった。それどころか,この移行過程で起きた政治的重大事件の多くが租税や予算に絡んでいたことを思えば,ある意味で,民主主義の歴史は財政民主主義の歴史であったとすらいえなくもない。近代民主主義国家の予算・財政制度の発展はこうした財政民主主義の歩みとして理解することができる。
もちろん,近代民主主義国家が成立する以前にも統治機構としての"公け"は存在したし,その"公け"の活動を経済的に担保する"財政"も存在した。また,会計検査の中心概念である"アカンタビリティ"も存在した。しかし,かつて,君主制における"公けの利益"とは,専ら君主が追求する利益であり,それは,被統治者たる人民からみれば,君主の恣意的性格を免れないものであった。したがって,君主の領土経営にまつわる君主の経済である財政の運営も,君主の恣意的運営を免れないものであり,君主の私的利益が混入することも珍しくはなかった。財政のアカンタビリティは,徴税吏が徴税した税収と徴税に要した費用とを明らかにし,君主への財務会計責任を証明することであった。
ところで,ハーバーマスによれば,市民的"公共性"(パブリックネス)の概念は君主支配の恣意性に対抗する新興ブルジョワ市民のアンティ・テーゼとして出現したという。公共性は,当初,王権の恣意性に対する人民のチェック機能を担うものであった。民主主義勃興期における財政民主主義とは,財政におけるこの市民的公共性の発現であったといえる。その時期,財政民主主義は,君主の経済たる財政の恣意的運営,とりわけ財政の恣意的拡大とそれに伴う負担増大に対する人民のチェックとして機能した。課税や公債発行による資金調達および支出,すなわち,予算が議会の承認を要するようになった段階で,アカンタビリティのなにがしかは,君主支配下の統治機構で働く官吏の君主に対するアカンタビリティから,君主の側からの議会に対するアカンタビリティヘと移行したと考えられる。しかしながら,このようなチェック概念としての市民的公共性は,市民自身が自ら追求すべき"公共性"を積極的に指示しようとするものではなかった。
やがて主権在民の政治体制として民主主義国家が成立し,市民が政府をわがものとし,予算を掌中に収めるや,原理的には,政府は市民たちが自分たち自身のウェルフェアを追求する一つの重要な手段機構へと転化し,予算はそれを実現する集合的行動,すなわち,政策一覧の経済的表示へと転化する。ここでは,"公共性"や"公共価値"の認定を行うのは,究極において,市民たち自身でしかあり得ない。しかし,われわれ市民はわれわれ自身でこのような認定をできるのだろうか。また,仮に認定できるとして,その認定は確定的性格をもち得るのであろうか。
かつての"公けの利益"は君主が目指すものであり,君主が"これが公けの利益だ"といえば,ともかくもそれがそうであった。また,"私的利益"であれば,当の本人が"これが私の利益です"といえばそれですむ。しかし,民主主義社会において"集合的行動"として政府という"強権機構"を通じて行う政策について,市民たちは"公共価値"を認定できるのであろうか,一人ひとりの市民は,"≪私≫はこの政策を政策に値すると考えます"と述べる,または,その否定や不充分を述べることについて,平等の権利を有しているけれども,誰一人として自らの判断を自らを含む市民全体に強制する特権的地位にあるわけではない。にもかかわらず,"公共価値"は,市民たちによって,何とか認定されるほかない。市民たちは,何とかして,"≪私たち≫はこの政策を政策に値すると考えます"という共有命題を形成しなければならない。
市民たちによる"公共価値"の認定について二つの代表的考え方があるように思われる。一つは,"数の論理"であり,典型例として多数決をあげることができる。もう一つは,"経済の論理"であり,功利主義に立つ費用・便益分析はその代表例である。しかしながら,どちらの考え方も,重大な欠陥がある。このことは以下の事例で明らかである。
村はずれに一人の男が養豚業を営んでいたとする。ところが地域が都市化して,近在に移住して来た住民たちが悪臭を嫌い,移転を迫る住民運動をおこしたところ,皆が賛同したので村人たちは立ち退きを要求した。この要求は"公共性"に適っているだろうか。否である。何故ならば,この要求はたんなる私的要求にすぎないからである。養豚業者はその要求を受け付けなかった。そこで,村人たちは強制力をもつ公的決定が必要と考え,村議会を開催し,賛成多数で移転勧告を可決した。男は,私にも生活権があり,それを奪うことは公権力といえどもできないと答え,勧告を拒否した。確かに,補償もない移転勧告は不当であり,このような勧告は"公共性"に反している。"数の論理"は,投票のパラドックスで知られるように,首尾一貫した社会的選好順序を導かないことがあるという欠陥をもっているが,それだけでなく,多数性そのものが"公共性"を保証しないことは明白である。
男は立ち退きを承諾しない。そこで,村議会は彼に補償を申し出たが,なお決着がつかないので裁判にもちこまれた。裁判所は,養豚業者の損失額を算定し,村が申し出た補償額はそれに見合っていると認定し,結局,補償金付き移転勧告をした村当局は勝訴した。しかし,後に,村議会で,この移転勧告政策が妥当だったかどうか問題となったので,改めて経済学者に費用・便益分析を依頼した。経済学者は,当事者が自発的に支払ってもよい最高金額および代償となり得る最低金額という概念に照らして,費用・便益計算をした。彼は苦心の末,何とか村人一人ひとりの悪臭から解放されることの便益を算定し,その総額を便益とした。またこれも苦心の末,養豚業者が立ち退いてもよいと考えていた額を算定し,これをマイナスの便益とした。さらに,政策経費である,補償金,弁護士費用,諸経費の合計を費用に計上した。差し引きプラスの純便益が発生していたので,費用・便益分析ではこの政策を肯定できる旨を議会に報告した。また,この報告には,「この評価には,"分配の公平性"についての評価は含まれていません。これは価値判断なので,私の仕事というより皆さんご自身が判断すべきことです」という但し書きがついていた。分配への配慮いかんによっては結論が異なり得るので,ここでも,費用・便益分析だけでは"公共価値"が保証されていないことは明白である。
多数決という"数の論理"による"公共性"の認定も,利益集計という"経済の論理"による"公共価値"の認定も,ともに,容認できないとすれば,"公共価値"とは幻想にすぎないという結論に到達するのだろうか。
Ⅲ コミュニケーション的規範概念としての"公共価値"
この例において,"数の論理"も"経済の論理"も"公共性"や"公共価値"認定の決定的理由にならないことは明らかである。まず,村議会の承認,対立したときの裁判,そして,既存の法律・規則との整合性,などの手続き的正当性が充足されていなければ,どんなに多数の支持が得られようとも,どんなに費用・便益分析による純便益が大きかろうとも,"公共性"や"公共価値"が正当化されるものではない。村に検査役がいれば,彼はこれら諸々の"合規性"検査をしたことであろう。また,弁護士や経済学者が高すぎる報酬率を請求していたとすれば,あるいは,もっと手際よく仕事をしていたとすれば,純便益はもっと大きいので,政策の価値はもっと大きかったであろう。検査役は,これらの"経済性・効率性"検査も実施したかもしれない。上の事例において,合規性も経済性・効率性も問題なかったと仮定しよう。また,経済学者が見落とした経済的外部効果もなかったと仮定しよう。
さらに,村当局は分配効果についても考慮することにした。経済学者が有能だったので,養豚業者も含めた全員の正負の便益および負担がわかっていたとしよう。すなわち,政策の分配効果そのものはわかっている。そこで,村議会は,経済学者のアドバイスに従って,各人のウェルフェア・ウェイトを決定し,加重純便益を算定することにした。どのようなウェルフェア・ウェイト表が妥当か,どうやって決めればよいのか。幾つかの候補表を作成し,多数決で一つを選択することにした。幸い,循環選好を発生することなく,一つが選ばれ,無事"公共価値"(?)が決定された。かくして,修正純便益がプラスなので,この政策はジャスティファイされた。ここでは,一見,"数の論理"と"経済の論理"との併用で"公共価値"が認定されたかのようにみえる。だが本当にそうだろうか。
養豚業者への補償金付移転勧告に関する費用・便益分析やウェルフェア・ウェイト表による修正費用・便益分析の結果が,プラスの純便益発生を保証しているにもかかわらず,この政策の"公共価値"が否定されるべき反例を挙げよう。村人のうちの何人かは,風向きの関係からみれば,それほど悪臭の被害を受けていないにもかかわらず,かなり高額の負担を進んで申し出ていた。調べてみると,この人たちと養豚業者は日頃から仲が悪く,彼らは,この際少々余計に負担してもこの嫌な隣人が村から出て行くならそれにこしたことはないと,考えたのであった。彼らは,当然,ウェルフェア・ウェイト表の採択でも養豚業者のウェイトが低いウェイト表に投票していた。もしこのような個人的好悪という恣意的理由をもつ人たちがいなかったとしたら,純便益や修正純便益はマイナスに転じていたかもしれない。そうだとすれば,彼らは公的権力を利用して不公正をなしたことになる。しかし,高額の負担申し出の理由が,特別臭気に敏感な体質にあったとしたらどうだろう。大きな集団をとってみれば,必ず,そうした体質の人が何人かはいるものだから,この額を恣意的というわけにはいかないだろう。その人たちの悪臭から解放される便益は,別の敏感な人たちの便益と交換され得るし,そのような体質の存在自体は容認されるべきだろうから,恣意的というよりそれなりの普遍性を備えている。しかし,個人的好悪の感情によってある人を社会の構成員から排除してもよいという考えには,普遍性がない。
この反例が明らかにしているように,政策価値に"公共性"を付与するのは,認定の論拠の妥当性と理由の正当性である。上の事例では有能な経済学者が,当事者たちが自発的に支払ってもよい最高金額および代償となり得る最低金額という概念に忠実に便益算定したと仮定されているけれども,調査において虚偽の申告がなされて,便益算定が歪められていることが明らかになれば,この認定に疑問符がつく。また,不当な理由による便益が混入していたとなると,価値額の大きさばかりか,政策の"公共性"そのものすら疑問視されることがあり得る。"数の論理"や"経済の論理"などの"数量の論理"の限界は,これら数量の背後にある論拠や理由について何も語ることなく,結果としての数量しか提示しないことにある。それだけでは妥当性や正当性を判断するのに不充分である。"数量の論理"は妥当性や正当性という"質の問題"に充分な判断材料を提供しない。
"公共性"や"公共価値"という概念は"≪私たち≫はこの政策を政策に値すると考えます"という命題を,人々が,政治空間において形成し得たときにそれと認定されるコミュニケーション的性格を帯びた概念である。それぞれの人はそれぞれなりに政策の意味や価値を考慮して,それが政策としてふさわしいかどうか判断する。しかし,そのような個人的見解はそれだけでは公的見解にならない。政治的コミュニケーションを経て,しかるべき手続きを通して,≪私≫の見解が≪私たち≫の見解へと合意されたとき,公的見解が成立する。しかしながら,公的見解が公的であるがゆえに政策の揺るぎなき"公共性"の証しとなるわけではない。仮想した村の政治決定が,"公共性"に反する政策を採択したように,われわれ市民が参与する民主主義政治も,"公共性"に反する政策を採択しないとも限らない。
実は,"公共性"や"公共価値"は,もともと合意形成という人々の政治的コミュニケーション行為によって成立する規範概念であって,現実の合意そのものではない。"政治的コミュニケーション"によって成立する"規範概念"だということは,ここで大いに強調しておく必要がある。確かに,多くの人が賛成しなければ社会的合意とはいえないし,発生する便益が犠牲を上回らなければ賛成する人もいないだろうから,多数の支持や,純便益の発生は,"公共性"や"公共価値"にとって考慮すべき重要事項にはちがいない。しかし,その規範的性格は,それが,多数性というたんなる形式性の充足や,たんなる便益アルゴリズム条件の充足に還元されないことを意味する。また,仮に満場一致の合意が形成されたとしても,その事実が,"公共性"や"公共価値"を保証するわけでもない。政策の"公共性"や"公共価値"は,"≪私たち≫はこの政策を政策に値すると考えます"という共有命題として公的見解が成立し,それが妥当性と正当性を備えているとみなされるとき,初めて認定されるであろうような規範概念なのである。
そこで問題になるのは,政治が,そのような"公共性"や"公共価値"を追求し得るどれだけの可能性をもっているかということである。数に支えられた権力にせよ君主の権力にせよ,権力の恣意性をチェックし,権力のふるまいに妥当性と正当性を要求するのは,"コミュニケーションとしての政治"の役割でしかあり得ない。何故ならば,妥当性や正当性とは,社会的に調整された人の"フレーム・オブ・レファレンス"によってなされる判断だからである。各個人の判断の背後には,そのような判断を導いたその人なりの現実世界に対する認識や評価の内的仕組みがある。人がものごとを知覚し,感じ,思考し,行動を導出するそのような内的仕組みのことを,ここでは,"フレーム・オブ・レファレンス"と呼んでいる。対立を克服し一定の秩序を形成するには,力による制圧とコミュニケーションによる判断の調整,あるいは,その背後にあるフレーム・オブ・レファレンスの調整,とがある。社会秩序の形成および維持という政治の機能は,秩序に対する社会的合意と反秩序に対する強制的権力とによって果たされる。政治における合意の調達を巡る諸現象が,ここでいう"コミュニケーションとしての政治"である。また,権力を巡る諸現象が,ここでいう"権力としての政治"である。妥当性と正当性を備えた合意を欠いた権力は,パワー・バランスの変化によって容易に崩壊する。また,権力による担保を欠いた合意は,たとえそれがある程度の妥当性と正当性を備えていたとしても,あまりにも脆弱である。政治は,いつの時代においても,この二つの政治の相補的結合であった。
民主主義の政治体制において,この政治的コミュニケーション・プロセスを構成するのは,いうまでもなく市民たちである。民主主義では,一人ひとりの市民は自らの見解を主張する平等の権利を有するが,誰一人として自らの判断を市民全体に強制する特権的地位にあるわけではない。一人ひとりの市民は,"権力なき君主"である。この権力なき君主たちは,果たして妥当性と正当性を備えた政治的合意に到達し得るのか。この問題は,政治的コミュニケーションとフレーム・オブ・レファレンスの自己再編成に関するいま少し踏み込んだ理解の後で,検討することにする。
Ⅳ コミュニケーションと合意形成
これまで政治学は,主として"権力としての政治"を取り扱ってきたが,"コミュニケーションとしての政治"については,必ずしも,充分な注意を払ってこなかった。それは,合意形成という現象が,ありふれた現象であるにもかかわらず,学問的研究の対象として極めてやっかいな性格をもっていることによるところが大きい。しかしながら,本来,民主主義という政治体制にとって,"コミュニケーションとしての政治"は,とりわけ重視されるべき政治の側面である。民主主義が,少数派の意見の尊重や討論の重要性をことのほか強調するのは,"コミュニケーションとしての政治"に期待をかけているからである。たんなる"数の支配"が民主主義ではない。それゆえ,合意研究の視点からの"コミュニケーションとしての政治"論が発展する必要がある。
しかし,目下のところ合意研究の蓄積は大きくない。われわれも,研究会を組織して,われわれなりの『合意学』の研究を開始したところである。それでも,われわれの『合意学』の視点は,従来にないさまざまなインプリケーションをもたらしつつある。以下では,われわれの『合意学』の思考枠組みによって,コミュニケーション的性格をもつ規範概念としての"公共性"や"公共価値"について,さらに考察を進めよう。
"コミュニケーションとしての政治"は,互いが自己の見解の妥当性と正当性を主張して,他者に見解の変更を求めたり,賛成を求めたりする場であり,たんなる情報交換の場ではない。われわれの『合意学』は,次のような,一組のコミュニケーションおよびフレーム・オブ・レファレンスに関する仮説的命題から,研究を出発させる。(1)見解の変化や賛否の変動がコミュニケーションによって生じるのは,各個人のフレーム・オブ・レファレンスが再編成されるためである。(2)フレーム・オブ・レファレンスにどのような再編成が生じるか,あるいは,生じないかは,コミュニケーションの内容に依存するであろう。(3)しかし,この再編成過程の重要な性質として,不確定性がある。そのためにコミュニケーションが行き着く先は不確定である。(4)とはいえ,フレーム・オブ・レファレンスの再編成に伴う不確定性は,決してデタラメな不確定性ではない。人間の資質に基礎付けられた幾つかの志向性をもつ不確定性と考えられる。
それぞれの仮説的命題は,さまざまな学問分野の経験的研究によってそれなりの裏付けをもっており,決して,アド・ホックな仮説ではない。(1)のフレーム・オブ・レファレンスの再編成可能性の承認,および,(3)の不確定性の承認は,合意形成に関する公理・演繹系としての定式化を特殊ケ—スに妥当する極めて限界的性格の接近として位置付ける。合意研究に対するわれわれの基本姿勢は,理解ないし解釈という立場である。この点で,経済理論や情報理論におけるコミュニケーションの取り扱いをわれわれは不充分と見なしている。効用関数所与の前提に依拠する経済理論や,情報空間構造を所与と前提するシャノン流の情報理論は,原理的に,対立状況から出発して合意に到達する可能性をもたない。経験・学習によってフレーム・オブ・レファレンスが再編成されるからこそ,各個人の見解が変化し,対立から合意が生じる余地が発生する。
人間行動の分析に当たって,常に,フレーム・オブ・レファレンスの再編成を考慮すべきだというわけではない。通常の,市場における選択や,その集積としての市場のふるまいを扱う場合,効用関数所与の前提は大いに有効性を発揮する。しかし,互いの政治的見解の変更を目指す政治的コミュニケーションにこの前提を持ち込むとき,分折結果の含意は制約されざるを得ない。例えば,費用・便益分析の便益は,コミュニケーションによって変化するかもしれない。そうなると,ときとして,どのようなコミュニケーションの後のフレーム・オブ・レファレンスによって人々の便益が算定されたかが問題になる。養豚業者への移転勧告の便益評価は,不仲な隣人を排除しようとする不当な動機によって歪められていることが分かったとき,心ある人は評価額は引き下げられるべきだと主張するであろう。この主張は,村人たちに受け入れられることもあれば,そうならないこともあろう。しかし,この場合,政治的コミュニケーションの評価額に対する中立性を予め仮定することは不適当といわねばならない。
しかし,(3)および(4)によって,コミュニケーションの行き着く先は不確定である。それゆえ,政治的コミュニケーションが,政策評価の質を改善する保証はない。むしろ,対立が一層激化したり,より"公共性"に反する帰結を導くことすらある。フレーム・オブ・レファレンスの再編成における不確定性には,実存的不確定性とでもいうべき根源的不確定性が含まれている。
フレーム・オブ・レファレンスは,さまざまなレファレンス・アイテムからなる複雑な自己組織系である。この自己組織系を全体として不可逆的発展の系として性格付けているのは,記憶というアイテムの蓄積である。記憶は経験・学習の神経組織網への定着である。そのメカニズムについては,現在,研究がめざましい勢いで蓄積されつつあるが,まだ分からないことの方が多い。記憶には性質の異なる2種類の記憶,すなわち,出来事(エピソード)記憶とさまざまなアイテムを処理する手続き記憶とがあることが知られている。また,記憶には,その存在が容易に突き止められないような種類の記憶がある。すなわち,"暗黙知"や潜在記憶である。言語化されていないという意味で覚知されていない知識,すなわち,マイケル・ポランニーのいう"暗黙知"や,フロイトやユングによって示唆され神経生理学的傍証を獲得しつつある潜在意識ないし無意識の記憶,あるいは,長期記憶として蓄積されていながら,容易なことでは呼び出されなくなってしまった記憶が存在する。これらは,工夫をこらした研究や偶然によって,ときに,存在の一部が知られるだけで,その全貌は全体として不可知である。その量は膨大だと考えられているが,どれだけ膨大かは確定しようがない。
したがって,フレーム・オブ・レファレンスは,記憶の蓄積とともに自己組織化を続けるシステムとみなされる。しかし,そのアイテムには個人の履歴に依存した,しかも,本人も観察者も知り得ない不可知なものがあるために,システム全体としての作動を定式化不可能ならしめている。われわれは,われわれの内部に実存不確定性を抱えているのである。われわれは,このようなフレーム・オブ・レファレンスによって,知覚し,感じ,思考し,判断し,行動し,環境と相互作用しながら生きている。そして,この生きる過程で,フレーム・オブ・レファレンスもまた再編成を続ける。
この生の実践において,さまざまな課題が解決されなければならない。課題と密接な関連をもつ,言葉,概念,イメージなどのアイテムや,それらを結合し配置する手続きに関するアイテムなどが励起され,このアイテム・セットによって認識・評価空間が構成される。こうした認識・評価空間のうち繰り返し適用されるパターン構造は,取り替え可能な変項アイテムの場所を準備したシェーマとして保存されよう。例えば,経済学者によって効用関数として定式化されるのは,こうしたシェーマの部分と考えられる。しかし,これとても,経験による再編成を免れるものではない。そして,このアイテム・セットである認識・評価空間とそれを包摂するフレーム・オブ・レファレンスの残余部分との関係で重要なことは,両者がゲシタルトの図柄と背景の関係をなしていることである。このことは,最近の認知意味論の研究が明らかにしたことである。したがって,言葉や命題のもつ主体にとっての意味・価値は,認識・評価空間内部の配置で確定するわけではなく,背景にも依存している。それゆえ,言葉や命題の主体にとっての意味・価値は,解釈によって理解を深めることはできても確定することはできない。
主体間のコミュニケーションは,このようなフレーム・オブ・レファレンスの間での言語を中心とするメッセージ交換である。とりわけ,政治的コミュニケーションは,"私の見解こそ正しい,貴方はまちがっている,改めなさい"といったメッセージが飛び交うことからも明らかなように,お互いのフレーム・オブ・レファレンスの再編成自体を目指すコミュニケーションである。コミュニケーションの展開に応じて,当事者たちは,さまざまに認識・評価空間を再構成し続け,この過程で,主体にとってのイッシュウの意味・価値は変貌する。しかしながら,この過程の行き着く先は,不確定である。この不確定性には,われわれのコミュニケーションや合意形成に関する知識の不足に由来する不確定性もあるが,フレーム・オブ・レファレンスの実存不確定性に由来する不確定性があるということが,特に,銘記されなければならない。何故ならば,このことが"自由"や"平等"の観念と密接に関連しているからである。
しかし,このような不確定性があるとはいえ,フレーム・オブ・レファレンスの再編成がデタラメだということにはならない。人が環境との適応を図りつつ生きていかなければならない生物である以上,その再編成の基本方向は適応的である。環境に関する知識は現実適合的に整序されるであろう。また,通常の人は誰も,"正義感覚"を"暗黙知"として発達過程で習得する。おそらく,この正義感覚の生物学的基礎は,共存を志向するヒ卜の遺伝的資質であろう。現実適合的でかつ正義感覚にかなったコミュニケーション行動は,現実の根拠の適格性,論理的整合性,価値判断の普遍性,などの要請を満たさなければならないから,判断の妥当性や正当性をより高める方向ヘフレーム・オブ・レファレンスの再編成を導くであろう。
もちろん人のフレーム・オブ・レファレンスの再編成をリードする志向性はこれらだけではないし,さまざまな志向性は互いに矛盾なく両立するとは限らない。個人的資質の差と履歴の差とによってそれぞれのフレーム・オブ・レファレンスは個性的発展をする。ときには好ましくない歪みを生じることもある。しかし,こうした適応や共存への志向性は,"他の事情にして等しければ",妥当性や正当性のより高い判断を導出するような方向へ再編成をリードするであろう。それゆえ,コミュニケーションの帰結が不確定とはいえ,コミュニケーションによるフレーム・オブ・レファレンスの再編成は,蓋然性において,肯定的機能を期待し得るように思われる。
Ⅴ コミュニケーションとしての政治と権力としての政治
人はさまざまな市民生活の局面において,その人なりに現実を認識し評価して自らの行動を決定している。私的領域においては,その人の行動決定はその人自身の判断に委ねられており,その人がどのような認識に基づきどのような判断を下そうとも,そのことの帰結に責任を負う覚悟さえあれば自由である。その人のフレーム・オブ・レファレンスが私的領域をどのように把握していようと,他者がとやかく介入する権利はない。その人の行動をこころよく思わない他者がいたとすれば,関係を断つなり,それなりのリアクションを自己の判断でとればよい。私的領域では,ある行動選択の説明として,"≪私≫がそうしたかったからです"という説明が承認される。それ以上の説明をもって他者の諒解を得る責務が課されるわけではない。また,他者は,その人にそのような説明を強制する権利をもたない。ここでは,≪私≫という固有名詞性に帰着するしかない恣意的説明が,その恣意性ゆえに排除されるわけではない。
しかしながら,強制的権力行使を伴う公的領域においては,政治的決定は全員に影響を及ぼす。個人はそれから逃れられない。ある人の政治的見解を,誰かが承認するとすれば,それは,その人なりの「妥当性」と「正当性」とに照らした自発的承認でしかあり得ない,というようなある種の理想化されたコミュニケーション空間を想定してみよう。ここでもし全員一致の合意が形成されるとしたら,それは,まさに,妥当性と正当性を備えた合意であろう。ある人の見解を誰かが自発的に承認する。その自発的承認を別の人が承認するとすれば,また,その別の人の自発的承認でしかあり得ない。個々の発言に対して,反対者は,説明を求める。全員の自発的承認が得られるまで,コミュニケーションは続けられる。このような政治的コミュニケーション空間において,もし"≪私たち≫はこの政策を政策に値すると考えます"という命題について全員の相互承認,すなわち,全員の合意が成立するとすれば,それは,根拠に適格性を欠いていたり,論理的に不整合だったり,価値判断理由に普遍性を欠いていたりする恣意的説明にいっさい依拠しない。妥当性と正当性を備えた合意であろう。そして,その政策こそ"公共性"にかなった政策であり,この政策に人々が進んで支払ってもよいと考える支払い総額こそ,この政策の"公共価値"である。
しかしながら,前述したフレーム・オブ・レファレンスの実存不確定性のために,このような完全な合意は,原理的に不可能である。個々の主体なりの「妥当性」や「正当性」の意味・価値をはじめ,コミュニケーションで交わされるそれぞれの言葉の意味・価値が主体間で厳密に一致することはあり得ない。コミュニケーションによるフレーム・オブ・レファレンスの再編成はこれらの言葉の意味・価値についてもある程度の社会的合意をもたらすだろう。だからこそわれわれは話し合える。しかし,それでも,完全な一致はあり得ない。このような意味・価値の不確定性を含んだまま,われわれは,言語命題について合意を形成することができる。もっとも,合意が形成されるかどうかは不確定である。また,仮に合意が形成されたとしても,合意命題の意味・価値は,不確定性を含んだままだし,個人間で厳密に一致しているわけではない。さらに,合意後の経験・学習がまたフレーム・オブ・レファレンスの不確定な再編成を起こすかもしれないので,合意の持続性も不確定である。
われわれは,前節で,"公共性"や"公共価値"はコミュニケーション的性格の規範概念だと規定した。実は,"妥当性″,"正当性","公正性",など同じ性格の規範概念が数多く存在する。これらの言葉には,"これにかなったことは全員に強制されてしかるべきだ,そして,これに反することは排除されるべきだ"という意味がこめられている。"かなったこと","反すること"に具体的に何が含められるかは主体によって解釈が異なるし,強制や排除に用いられる力の種類についても解釈が異なり得るとしても,これらの解釈について社会集団にコンベンションが確立していれば,その確立した解釈に従う力の行使が容認される。解釈の変更は,長い時間を経てコンベンションが変わることによってか,政治的コミュニケーションによる新たな合意の形成によってなされる。
このコミュニケーション的性格をもつ規範概念をもつからこそ,われわれは,政治的コミュニケーションによって,政策を形成できるし,社会秩序を形成し維持することができる。権力がたんなるむきだしの暴力にすぎず,その妥当性や正当性を人々が認めていないならば,暴力的勢力バランスの変化は権力移動をもたらし,政策は権力者の恣意のままに変化して安定しない。しかし,権力や政策についてなにがしかの妥当性や正当性が認められていれば,対抗的暴力の行使はその分抑制されるし,権力移動があったとしても妥当性と正当性を付与された政策部分は継承され,政治はずっと穏やかなものになる。この妥当性や正当性は,"≪私たち≫はこれこれについて妥当かつ正当と認めます"という合意として人々に観念されるものである。合意としての性格をもたない妥当性や正当性はあり得ない。
一方,政治が合意のみによって機能しないことは,フレーム・オブ・レファレンスの不確定性から明らかである。意味・価値が厳密に一致した合意は原理的に不可能である。意味・価値の不確定性を含んだままの言語命題についての全員一致の合意も,わずかな命題についてしか成立しないであろう。その上,政治的コミュニケーションには時間の制約がある。どこかで打ち切らざるを得ない。したがって,政策は反対者をかかえたまま実施されなければならない。また,合意命題の意味・価値の厳密な一致があり得ないので,政策の実施において解釈に紛れが生じて,紛糾するかもしれない。さらに,政策の遂行中にもフレーム・オブ・レファレンスに変化が生じ,合意が崩壊するかもしれない。したがって,時間の制約のなかで政策や秩序を成り立たせるのに充分な命題集合を,合意として認定するためには,権力的認定がなければならない。また,政策の実行は,権力の裏付けによって担保されている必要がある。権力と合意という,一見,二律背反的相補関係を,討論と多数決の併用によって折り合いをつけようとする政治形態が民主主義である。民主主義は,討論と多数の支持とによって権力に妥当性と正当性を付与し,また,討論と多数の支持によって権力のふるまいから恣意性を排除しようとする。
Ⅵ 民主主義と良質な政治的コミュニケーション空間の必要性
われわれは,前節で,コミュニケーションのもつフレーム・オブ・レファレンスの再編成機能を,蓋然性において,肯定した。もちろん,不確定性ゆえに,コミュニケーションの結果,ますます,対立が激化したり,かえって新たな紛争を引き起こしたりすることもまれではない。蓋然的に肯定し得るのみである。しかしながら,コミュニケーション一般はともかく,政治的コミュニケーションについては,そう楽観的になれない。人には自分の利益を拡大したいという志向性があり,ときに共存への志向性と衝突する。政治空間では,この衝突がないほうが例外である。自己利益の追求はそれ自体不当だとはいえない。むしろ,自己利益追求の自由と"公共性"や"公共価値"との両立可能な社会秩序をいかにして形成するかは,民主主義政治の最も重要な課題の一つである。とはいえ,この衝突を回避し得る解決策がつねに発見されるとは限らないので,合意そのものが不可能となり,対立・紛争が続くかもしれない。その結果,コミュニケーション努力を軽視するようになり,"数の論理"だけに頼る民主主義の形骸化が起こるかもしれない。また,自己利益動機が政策の妥当性や正当性の吟味を妨げるかもしれない。
しかし,民主主義は討論に期待をかけた政治形態である。討論が機能しない民主主義は,衆愚政治に陥るか,強権的政治に移行する危険をはらんでいる。政治が妥当性や正当性を欠いた恣意的利益の実現手段に堕落し,ペテン,駆け引き,脅し,騙しが横行するようになると,正直で誠実なものほど割りを食うようになる。この経験・学習は,政治不信を助長し,正直で誠実だったものまでもペテン,駆け引き,脅し,騙しに走らせかねない。そうなると政治的コミュニケーションは,一層,逆機能を発揮しだす。これとは逆に,良質な政治的コミュニケーションが政治的決定の妥当性や正当性を高めるような実績を蓄積すると,結局において,良質なコミュニケーションが望ましい帰結をもたらすという信念を強め,一層,政治的コミュニケーションがよく機能するようになる。したがって,政治的コミュニケーションをよりよく機能させるためには,良質な政治的コミュニケーション空間を構築する禁欲的努力が必要である。
良質な政治的コミュニケーション空間の条件を網羅する余裕はないので,若干のことだけ指摘しておこう。まず,個々の政治的言論そのものが良質でなければならない。ペテン,駆け引き,脅し,騙しに頼って一時的合意を得ようとするような言論は論外である。そのような不正が直ちに排除されフェアネスが回復されるような慣行なりルールが確立されていなければならない。虚偽が含まれているかもしれないと絶えず注意深く疑いながら展開しなければならないコミュニケーション空間は,殆ど,機能しない。何故ならば,信頼性を前提できない場合,言葉や命題の意味・価値が厳密に一致していることはあり得ないから,たとえ発言者には矛盾がない発言のつもりでも,聞き手には不一致が矛盾と受け取られ,虚偽の証拠ともなりかねないからである。そうなると,建設的だったかもしれない発言も無視されたり,非友好的反論を受けたりして,ネガティブな反応がさらにネガティブな反応を招く悪循環に陥る。
政治的コミュニケーションは,妥当性と正当性を追求する共同の営みだから,個々の発言もその営みに貢献すべく,論理的斉合性や証拠の適格性や理由の普遍性に気配りされた良質な言論であることが要請される。また,より高い妥当性と正当性を求めて,自己の見解を修正する心構えがなければならない。これは代議制政党政治ではなかなか困難なことかもしれない。与野党対立の構図のなかでは,相手の見解に従うことは,相手の得点,すなわち,自分の失点,とみなされがちである。相手の美点を率直に認めることが,むしろ美徳として評価されるような政治文化を醸成できないものだろうか。批判すべきことを批判し,称賛すべきことを称賛することは重要である。何が妥当で正当なことかをポジティブに探求しようとする場合,称賛や積極的賛同の意見表示は,良質な言論への努力を力づけるので,特に,重要である。
このような良質の政治的コミュニケーション空間が確保されれば,政治的合意形成にまつわる不確定性は,総体として,幸福なことである。何故ならば,この不確定性は"創造性"の源泉だからである。また,個人が自由を確保できる論拠となり得るからである。もし"公共性"の具体的意味内容が確定するならば,これらを巡る自由は必要なくなる。これらのことを知る特定の人だけが支配者となればよい。あるいは,全員が知れば,これらを巡る対立はなくなってしまう。一見素晴らしい社会のようだけど,独裁が支配する悲惨な社会か,あるいは,極めて退屈な社会にすぎないではないか。新しい共有価値を創造し得る自由な社会のほうが,はるかに素晴らしい。
自由な社会は少数派の自由を尊重する。少数者派は,何らかの意味で異質な人々である。だからこそ,多数派の人々にはない見方を提供して,より妥当で正当な,自由とよりよく両立するような政策を創出する契機となり得る。多数派の横暴が少数派の言論を抑圧すれば,多数派もまた,このような機会を失う。多数派の意向ならば,どんなことでも強制できるという"数の論理"の暴力性が支配すれば,自由の領域は縮小する。良質な討論に支えられた民主主義こそが,自由主義との両立を可能にする。そして,自由もまた人間の本来的志向性だとすれば,良質な討論を伴ってこそ,民主主義は,政治体制として安定的に機能できる。
良質な政治的コミュニケーションを伴う民主主義でも,合意の不確定性そのものが削減されるとはいえない。それどころか,良質な討論はさまざまな知恵の創発を促すから,不確定性は増しさえするかもしれない。まず,合意が形成されるか否かは依然不確定である。しかし,合意しないことの弊害が少なければ,合意しないことへの合意が形成される可能性がある。この場合,紛争を競争に転化するルールについてだけ合意が形成され,自由と共存の両立が図られる。ともかく合意するほうが望ましければ,早急の改定の道を残す暫定的合意を形成する可能性もある。したがって,良質な討論は,合意命題のバリエーションを大きく拡大する。合意がどのような共有命題として形成されるか,それがどれくらいの期間安定的に維持されるかも依然として不確定である。しかし,このような良質な討論によって形成される合意は,より多くの人々が妥当性と正当性を認める合意である。
Ⅶ "公共価値"の形成と検査院活動の役割
これまで述べた"民主主義"と"コミュニケーションとしての政治"そして"公共性"の互いの関係に関する見解は,まだまだ粗削りなものである。それを承知の上で,以下に,この見解にそって,政策評価と財政民主主義との関係に関する所見をとりまとめてみることにしよう。
確立された民主主義体制において,アカンタビリティは完全にパブリック・アカンタビリティとなる。それは,直接には,政府の市民に対するアカンタビリティであるが,政府そのものが市民の付託を受けた機構であるから,究極のところ,集合としての,市民の市民に対するアカンタビリティという,一見すると,奇妙な構造をもつ概念になる。しかし,それは少しも奇妙ではない。なぜならば,集合としての市民とは結局一つの意志をもったユニットではない。一人ひとりは,恣意的であるかもしれない,いやその可能性が大いにあるような,政治主張をする平等の権利を保有した,いわば,"権力なき君主"たちの集合でしかない。その市民たちが政府をわがものとし予算を掌中に収め,それを自分たちのウェルフェア追求の手段へと転化するや,論理的には,その瞬間すでに,"公共性"や"公共価値"に照らして市民たち自身の恣意性をチェックする制度的仕組みの必要性が発生していた。しかし,政府を手段として広範に自らのウェルフェアを積極的に追求しだすまでは,政府活動の規模も内容もそれはど大きくなく多様でもなかった。しかし,完全雇用の維持が政府の役割に追加され,さらに,社会保障を中心とする社会サービスの提供が加わり,国民のウェルフェア実現に積極的に取り組むことが政府の役割だと市民たちが認知するようになると,政府活動の規模は大きく拡大し内容も極めて多様となった。この段階で,国民負担率も上昇し,政府がなすべきことの内容を改めて問い直す必要が実際に生じた。すなわち,"公共性"や"公共価値"のネガティブな指定ではなく,その具体的内容を可能なかぎり選別するポジティブな指示が必要となった。検査機関の検査から評価への重点移動は,その財政面での現れの一つと理解される。
しかし,検査機関の政策評価は,究極の認定権限が集合としての市民にあって,検査機関にはないから,"政策評価の試み"に留まらなければならない。また,"公共価値"は,財政民主主義において,市民の合意によって形成される規範概念であるため,たえず形成され続ける可能性が確保されていなければならない。なぜならば,合意の成立可能性がフレーム・オブ・レファレンスの再編成によって開かれており,それは暗黙知や潜在記憶にも訴えかけるコミュニケーションに依存した不確定な再編成だからである。民主主義のまっとうな機能が,この不確定性からくる不碓定な合意に依存しているがゆえに,政治的コミュニケーション空間に良質な討論が展開されなければならない。
検査機関が政策評価を試みるとき,期待される役割は,何よりも,予算循環プロセスの一角において良質な"評価の試み"を発信し続けることによって,財政に関する良質な政治的コミュニケーション空間の一つの"核"となることである。正確なデータに基づく誠実で着想豊かなさまざまな評価の試みとそれらを巡る良質な討論こそ,市民たちの"公共価値"ある"公共価値"形成を促進する。財政データに精通し,行政府や党派からの中立性を確保した検査院は,この役割を担い得る最適格者である。
伝統的検査において,検査機関が担う役割は管理・統制者,つまり,"検非違使"としてのそれである。しかし,ここでは"公共価値の形成を巡る言論の自由広場"で"基調報告者兼パネリスト"を演じることである。もちろん,基調報告者もパネリストもただ一人に限定する必要はない。しかし,検査院が不可欠な主要メンバーとなるべきことは確かである。また,データをできるだけ公開し,多くの報告者や討論者が出現するように努めること,ときに自らそのパネル・ディスカッションの設営者になることも期待される。
最後に,プログラム評価について付言して本稿を終わらせよう。"公共価値"という概念が,民主主義過程において市民たちの合意形成によって形成される不確定な規範概念であるということが理解されれば,プログラム評価は,複合的な幅広い視点から試みざるを得ないだけでなく,また,そうあるべきである。そうせざるを得ないのは,"公共価値"が一元的尺度に還元できない概念だからである。無理な一元化はかえって恣意的になる。市民たちは"公共価値"を多様な捕らえ方をする。その解釈に矛盾や恣意性がなければ,そのような捕らえ方を一概に否定すべきではない。プログラム評価は,そのような市民の多様な"公共価値"の捕らえ方を代弁するものである。したがって,複数の見解があってしかるべきである。実際に評価を試みる検査官たちすら一元的視点から評価するとは限らない。それを無理に統一して,公的機関の公式見解として権威付ける必要はない。
検査官たちによる評価の試みが価値があるのは,それが専門知識と適切な分析技術に裏付けられた良質の見解である可能性が高いからである。複数の良質な評価が議論の出発点で準備されていることは,"公共価値"の形成を巡る言論の質を高める重要な条件である。"公共価値"は,その性格上,常によりよい"公共価値"への合意の可能性を潜在させている。良質で複眼的な評価が競い合うコミュニケーション空間こそが,そのようなよりよい"公共価値"概念を創造する舞台である。だからこそ,プログラム評価は,複合的な幅広い視点から試みるべきなのである。
(注) 筆者たちは,合意形成一般について,「合意形成研究会」を組織して研究を続けているところだが,これまで公理・演繹的理論によっては説明できないさまざまな社会現象の多くにまずまず納得し得るような理解を導く潜勢力を発揮し出している。本稿もその試みの一つである。筆者らの基本的考えは,
合意形成研究会,「『合意形成研究会』マニュフェスト」,『創文』,1992年1・2月合併号および3月号,さらに,それに続く号の連載からなる特集,「合意学のアゴラ」,創文社,1992年,を参照されたい。
また,プログラム評価については,
金本良嗣,「会計検査院によるプログラム評価」,本誌,第2号,会計検査院,1990年7月,山谷清志,「プログラム評価の二つの系譜」,本誌,第4号,同上,1991年9月,を参考にさせていただいた。