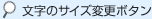第12号 巻頭言
収益費用差額はなぜ利益なのか
江村 稔
江村 稔
(東京大学名誉教授)
1923年生まれ。東京大学経済学部卒業。経済学博士。日本会計研究学会,日本監査研究学会,国際会計研究学会等に所属。
地方公営企業法の制定に伴う当該企業の会計基準の作成に,企業会計審議会幹事として参画したことが,公企業会計研究の発端。その後,多くの公企業(公社,公団,公庫など特殊法人)の会計問題に関係。現在,財政制度審議会特別委員。とくに「特殊法人等における会計処理基準」の作成に参画。
主な著書は,「企業会計法」(編著)中央経済社,「企業会計総論」森山書店,「企業会計と商法」中央経済社など。
企業会計の「常識」によれば,或る事業年度の損益計算書において,期間収益から期間費用(特別損失をも含む)を差し引いた差額,すなわち,収益費用差額は,当然のこととして,期間利益(マイナスの場合は期間損失)であるとされる。しかし,収益費用の差額が,何故に,利益又は損失であるといえるのかは,私にとって,長い間の疑問であった。たしかに,期間収益は企業の期間中における各種事業活動の価値成果であり,他方,期間費用は成果をあげるために必要とされた価値犠牲を主体とするすべての出費であるから,期間利益は疑いもなく企業の活動余剰ではある。しかし,本来,利益(もうけ)とは資本(もとで)を維持したのちに存在している余剰であるはずだから,いわゆる活動余剰といわゆる資本余剰とを,どのように関連づけて説明すべきかが,実のところ,私の理論的課題であったのである。
私のたどりついた結論を簡単に述べてみよう。株式会社の場合,株主が出資した資本金は名目的貨幣資本概念として理解されるが,この投下資本は既に回収を完了した部分(例えば販売債権)と今後回収を予定される部分(例えば商品や設備)とに分かたれる。したがって,両者の差額は,現時点において資本を維持したのちに存在している余剰と解されることとなり,しかも,このプロセスは貸借対照表により示されるとともに,複式簿記技術を通じて,損益計算書の収益費用差額は貸借対照表上の利益と同額をもって示されるのである。更に重要なことは,株主拠出額は株主の出資持分をあらわし,その故に,資本余剰は株主の分配可能持分あるいは処分可能持分たる性格をもつということであろう。
公企業あるいは特殊法人における「資本金」あるいは固有資本の性格は,名目的貨幣資本概念に属するものではない。それは実質的実物資本概念をもってとらえなければならないと断言するだけの勇気はないが,俗に,「トンカチ」がらみの金額は出資金であるといわれるように,公企業会計における資本概念は,限りなく,実物資本のそれに近付いているのである。そのうえ,公企業に対する国や地方自治体の出資額は株主出資持分のように,有限責任の限度ないし会社解散のさいの要返却限度を示すものでない以上,資本余剰には全く別個の性格が与えられなければならないはずである。
私見では,収益費用差額(プラス)を含む資本余剰は,公企業ないし特殊法人の場合には,これを資本造成額あるいは自己資本造成額と解すべきであると考える。かって,国鉄が公社であった時代,しかも,単年度決算で黒字を計上したとき,期間利益に資本造成額と添えがきしたことがあったが,やがて,国鉄は赤字決算を余儀なくされ,われわれの冒険的試みは長続きすることがなかった。
たしかに,資本あるいは自己資本の造成という考え方は,多数の人々の共通的な理解は得にくいであろう。しかし,地方公営企業たる上水道事業の場合,いわゆる料金の一部に将来の設備建設費が含まれていることから,自己資本造成引当金の費用計上が行われたこともあったのである。筆者はかかる会計処理を,今日でも採用すべきだとは主張しないが,公企業もしくは特殊法人による「資本造成」という考え方は,もう一度,再評価されてしかるべきであると信ずる。