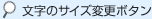第11号
大学における評価とアカウンタビリティ
−日米の現状を比較し−
潮田資勝
潮田資勝
(東北大学電気通信研究所教授)
1941年生まれ。ダートマス大学理学部卒,ペンシルバニア大学大学院理学研究科博士課程修了。Ph.D.(理学博士)。カリフォルニア大学アーバンイン校理学部物理学科教授等を経て85年より現職。北陸先端科学技術大学院大学材料研究科教授(併任)。物性物理学,表面物性論専攻。日本物理学会,応用物理学会,日本分光学会,アメリカ物理学会,アメリカ光学会,民主教育協会等に所属。
主な著書・論文は「科学英語論文のすべて」(日本物理学会編,第2章)丸善1984年,
"Progress in Optics Vol.19", edited by E.Wolf (North-Holland,Amsterdam,1981),ch.3等のほかに,"Physical Review","Surface
Science","Japanese Journal of Applied Physics"等の学会誌に専門論文多数。
1.はじめに
2.カリフォルニア大学における研究・教育の評価
−日本の大学との比較
2.1 教官の自己申請による業績評価
2.2 学生による教育評価
2.3 評価結果のフィードバック
2.4 学科,学部の評価
3.日本の大学における評価とアカウンタビリティ
−どの様なシステムが可能か?
4.まとめ
1.はじめに
「会計検査院」とかかれた封書を受け取った時は一瞬,「最近何か悪いことでもしたかナ」と我が身を振り返ったが,実は中身はこの原稿の依頼であった。私は物性物理学が専門なので,研究費の不正使用でもしないかぎり私と会計検査院との間にはあまりかかわりはない。しかし原稿の依頼状によると大学の活動に関する評価とアカウンタビリティについて何か書いて欲しいというこだとわかって安心した。
普段あまり意識していないことだがあらためて考えてみると,少なくとも国立大学の活動は税金を使って行っている国の活動であるから,大学の人間としては「国費を確かに正当かつ有効に使っていることを示すことができる必要」がある。すなわち我々大学の人間に対してもアカウンタビリティが要求されるのは当然である。
このaccountabilityという言葉はここでは「国費を正当かつ有効に使っていることを示すことができる能力」という意味の名詞だが,これに対応する日本語の一語の単語は存在しないようである。Accountabilityと関連の深い言葉には,responsibilityという言葉があるがこれは責任という言葉に近く,accountabilityとは少し違っている。
Accontという言葉は動詞として使うと"会計計算する,説明する,記述する"という意味になるから,accountabilityとは「自分の行動を正当化して説明できる能力」ということになる。確かにこれらの意味を含んだ一語の日本語の単語は思いつけない。原稿依頼の時にお送りいただいた「会計検査研究」の既刊号に載せられたいくつかの論文を拝見しても,多くの著者の方々がこの単語だけは英語で済ましておられる。よい日本語が思いつかないのは私の日本語素養の不足のためだけではないらしい。
「アカウンタビリティ」のような抽象的な単語は特定の社会で共有されている概念が一つの単位として結晶化したものだから,ある単語が存在するということはその単語に対応する概念が集団の意識上に一つの単位となって存在するということである。逆に単語が存在しないということはそのような概念がはっきり意識されていないということだと考えられる。人がアカウンタビリティを必要とするのは法を基盤とした契約社会においてであり,例えば絶対制君主は誰にも(おそらく神以外には)accountableである必要はない。反対に完全にarbitraryであることも可能である。このように考えると,日本語にアカウンタビリティという単語が存在しないこともある程度理解できる。比較的短い日本の民主的法治国家としての歴史の中で,アカウンタビリティという概念は未だよく成長していないのではないだろうか。実際私が経験する日常でも,国民は政府に対してアカウンタビリティを強く要求しないし,お役所もアカウンタブルであろうと努めているようには見えない。大学においては,教官は積極的にアカウンタブルであろうと努力はしていなそうだし,学生も大学にそれをあまり要求せずにのんびり暮らしているように見える。したがってアカウンタビリティといった単語が存在しないのも故ありと思われる。
しかしわが国でも最近数年間の中に政府機関における情報公開の制度化,あるいは大学の活動に対する自己評価の要求など,アカウンタビリティの追求につながる一連の動きが見られるようになってきた。このような新しい傾向はわが国の社会を一方的なお上による統治ではなく,納税者によって雇われた公僕によるサービスの提供を指向する社会に移行する過程の一段階だと考えられる。これは非常に望ましい傾向であるが,このような新しい動きは大学における研究,教育に対してどの様な影響をおよぼすであろうか?逆にどのようなアプローチで大学のアカウンタビリティを追求することが社会に役立つ大学を育成するために必要となるであろうか?「会計検査研究」第9号の巻頭言で北陸先端科学技術大学院大学の慶伊富長学長が述べておられるように,英国における大学に対するアカウンタビリティの追求はあまり建設的な方向には進まなかったようである。大学に対するアカウンタビリティの追求といった動きがわが国でもいずれ本格化するであろうが,その前にこのテーマについて慎重な検討をしておくことが必要である。今まではほとんど社会から放って置かれていた大学に,突然その機能にそぐわない性質のアカウンタビリティを求めたりすると,大学の創造性や学問研究の自主性を損ねるようなことになりかねない。角を矯めて牛を殺すような事態が起こればわが国にとって大きな損失となるであろう。したがって大学の目的と活動形態によく整合した建設的なアカウンタビリティの求め方を検討しなければならない。
「はじめに」の最後に私自身のバックグラウンドを少しご紹介して,以下に述べることがどのような経験から来るものなのかおわかり頂く参考にしたい。私は日本で高等学校を卒業した後,学部はダートマス大学という米国のニューハンプシャー州にある大学に留学し,その後大学院はフィラデルフィアのペンシルバニア大学で物理学を専攻した。専門分野は個体物理,表面物性の実験である。博士課程を終えた後はカリフォルニア大学のアーバイン校に,助手から始めて教授まで16年間勤務した。結局はアメリカには25年間住んだ勘定になる。現在は東北大学電気通信研究所に勤め,北陸先端科学技術大学院大学の教授を併任している。もう日本に帰ってから10年近くなるが,まだ時々日米社会の違いに驚かされたり,フラストレーションを感じたりしながらカルチュアショックの大きさを実感している。そこでそのようなバックグラウンドの人間から見た日米におけるアカウンタビリティの捉え方の違いといったことについて述べてみたい。アメリカ社会はアカウンタビリティを常に追求し,また追求される社会である。単純にアメリカといっても土地ごとに考え方も違い,また時間とともに速い速度で変化している。もうアメリカには10年も住んでいないので現状は大分変わっているかもしれないが,私の知っている範囲で経験的な話をお伝えしたいと思う。
本稿では会計責任に対するアカウンタビリティではなく,学問研究,教育に対する大学のアカウンタビリティについて考える。アカウンタビリティを求めるためには,まず大学の存在目的である研究,教育活動においてどのような成果を挙げたか,それが効率よく行われているか,などの事項を分析,評価することが必要である。ここでは大学における教官の業績評価,特に科学・技術の分野における評価とアカウンタビリティに焦点を合わせて考えてみたい。日米の大学における現状を比較することによって,これからわが国における研究,教育の評価とアカウンタビリティの関係をどうすることが望ましいのか,どのようなシステムが可能か,といったことも含めて考えたい。ここで一つお断わりしておきたいことは,アメリカと日本の社会はある側面では世界の異なる社会の中で両極端の性格を持った社会であって,この両者を比較すること自体に無理があるかも知れないということである。私にはその知識がないが,本当はヨーロッパの国々の状況と比較して考える方が有益かもしれない。
2.カリフォルニア大学における研究・教育の評価
−日本の大学との比較
アメリカの大学では,よく"Publish or perish."(論文が書けない者は破滅せよ)などと言われているように,研究業績を挙げて論文を書けない研究者は切り捨てられるというのが現実である。私は16年間カリフォルニア大学に勤務して助手から教授まですべて普通のアメリカ人と同じキャリアーを経験したが,確かにアメリカの研究者,教育者に対する評価とその結果のフィードバックには非常に厳しいものがある。これに比べると日本の大学あるいは一般の研究者の置かれた環境は相当楽な世界である。あとで詳しく述べるように,日本式環境は良い研究を生み出すために悪いとばかりも決めつけられないし,アメリカ式研究評価体制が理想的とも言えない。そこで日米の大学における評価のやり方とその結果に対するアカウンタビリティの関係を比較してみたい。
比較の前にまず,アメリカの大学における教官の研究・教育業績の評価とその結果のフィードバック機構(アカウンタビリティ追求機構といってもよい)について説明しておこう。私が実際に経験したことのあるカリフォルニア大学における教官の業績評価とそのフィードバック機構について説明する。
2.1 教官の自己申請による業績評価
カリフォルニア大学では教官の業績は研究,教育,大学運営,社会貢献の4つのカテゴリーに分けて評価する。建前上はこれらのカテゴリーの活動を等しいウエイトで評価することになっているが,昇格,昇給などの上で最も重要なのは当然のことながら研究と教育である。業績評価の資料として各教官は毎年7月の学年度末に「年間活動報告書」と呼ばれる年間の活動の総括レポートを学科主任に提出する。以下に示すのはこの報告書の様式を直訳し,分かりやすいように注を入れたものである。
年間活動報告書
I.教育(Teaching)
1.教えた講義科目(講義番号をあげる)
2.新しく企画して教えた講義科目(最新のテーマ導入に対する努力)
3.教育効果向上のために組織的に行った活動(例えば実験マニュアルの改訂)
4.指導した修士および博士論文(学生名と論文題目をあげる)
5.指導(supervise)したポストドクトラルフェロー,リサーチアソシエート(名前をあげる)
6.指導した学生数(学部の場合はアドバイザーとして指導した学生,大学院は修士又は博士論文の指導教育官として指導した学生)
II.発表論文,研究,その他の創造的活動(Publications,Research,and Other Creative Activities)
研究およびすべての創造的成果をリストする。芸術作品,作曲,演奏,その他のこれに準ずる成果。すでに印刷され文献として引用できるもののみ記入。準備中,印刷中のものは含めない。自身が共著者でなくても指導者(supervisor)として関与した論文は別記して本人の役割を示す。(ここに業績リストを添付する。)
III.委員会活動(Committee Service−サービスという言葉は貢献という意味)
1.メンバーであった評議会の委員会名(これは教官としての学内活動)
2.メンバーであった行政的委員会(これは大学運営のための学内活動。例えば学長選考委員会など)
3.メンバーであった学部,学科内および他の委員会
IV.研究者としての活動(Professional Activities)
1.招待講演,学会誌の招待論文,その他これに準ずる活動
2.学術誌の編集その他の学術出版活動に対する貢献
(ここにレフリーをした学会誌,編集した本などをあげる)
3.学会活動(ここに学会の役員,国際会議の組織等の活動をあげる)
4.教育団体,政府機関,民間会社等における活動(ここに政府諮問委員会,国立科学財団(NSF)の助成申請の審査委員などをあげる。また民間会社のコンサルタントなどをした場合はここに会社名をリストする。後で述べるconflict of interestに対するチェック)
Ⅴ.特別な役職
(ここに学部長,学科主任,外部から受け入れたリサーチグラントの管理者等の一般の教官とは違う職務をあげる。リサーチグラントを持つとこれの管理者としての地位がつくので,どの機関からいくらグラントをもらったかを書く。)
Ⅵ.受賞
1.賞,表彰等
2.フェローシップ,学外グラント等
この年間活動報告書に盛られた事項からわかるように,教官のすべての活動が評価対象になっている。これらの報告事項の中で後に述べる昇級や昇格の審査で重要になるのは,発表論文の数と内容,招待講演,学術誌の編集などの研究者としての活動である。学生の教育に関する事項については後に別に説明する。多くの項目はすぐ理解できると思われるが,いくつか説明を要すると思われる項目について解説を加えておく。
リサーチグラントというのは日本で言うと文部省の科学研究費のようなもので,国家機関や民間の機関に研究プロジェクトの計画(プロポーザル)を提出して採択されると必要な研究経費が支給される。理工系の研究の場合,このようなリサーチグラントを出すのは,NSF(国立科学基金),NASA(航空宇宙局),国防省(陸,海,空,三軍が各々独立に研究グラントを提供している),エネルギー省,NIH(国立保健機構)などの政府機関である。リサーチグラントには設備費,消耗品費,旅費,オーバーヘッド(overhead−後に説明)の他に,研究助手(リサーチアソシエート)のサラリー,学生(リサーチアシスタント)のサラリー,秘書のサラリー,また研究者自身の夏のサラリーまで含まれている。アメリカの多くの大学では教授のサラリーは1年の中9ヵ月分しか支給せず,夏の3ヵ月分は自分で収入を見つけることになっている。したがって,夏休み中に研究を続けるために多くのリサーチグラントにはサマーサラリーといって研究者の3ヵ月分のサラリーが含まれている。このような給与のシステムなので研究活動を活発に行ってリサーチグラントを確保しないと年俸の25%がなくなってしまう。あまりリサーチグラントを得る機会が多くない文科系の教官と理工系の教官との間ではこのサマーサラリーの分だけ差が付くことが多い。
教授の業績評価において外部からどれだけリサーチグラント等の形で研究費を導入しているかは非常に重要な事項とみなされている。これは次に述べるようなアメリカの大学における研究運営のやり方のためである。アメリカの大学には日本の大学の講座費に当たる予算がない。教官が自分で外部から研究費を調達しない限り,研究はおろか,電話もかけられず,コピー機も使えないという状態になる。したがって研究費の獲得は必須の第1条件である。人に関しても同様で,日本の大学のように講座に所属する助手は居ないので,教授も助教授も自分の持ってきたリサーチグラントからサラリーを払って助手を雇う。ここでもやはり自分で研究費を調達してくることが必須である。このような意味では教授は大学の場所を借りて研究のための小企業を経営しているようなもので,「製品」は研究成果,その製品を売って次の研究契約をとってきて,また次の研究成果につなぐという自転車操業を一生続けている。だからアメリカの理工系の大学教授というのは本当に疲れる職業である。常に2〜3件の研究プロジェクトを動かしていないと,突然助手や学生のサラリーが払えないという事態が起こる。いきなりワシントンから電話がかかってきて,予算節約のため来年は1万ドル減らすなどと言ってくるのはそう珍しいことではない。
リサーチグラントに対して大学は運営費としてoverheadという料金を取る。このオーバーヘッドの割合は大学と研究費提供元(国立科学財団,エネルギー省,NASA,国防省,など)との契約で決めている。これが50〜100%にも及ぶので,大学は研究成果を挙げてリサーチグラントを多くとってくる教授が多いほど財政が潤うことになる。したがってそれに見合う高給を払うというわけである。アメリカの大学のこの側面は,真に小研究企業体の集合と言ってもよい。
上に示した報告書の中にコンサルタントをした相手をリストする項目があるが,これは各教官が持ってる会社などの民間団体との関係を公明正大にしておくためで,アカウンタビリティとはつながりの強い事項である。例えば,ある教授が政府の諮問機関などの委員になって,コンサルティングをしている特定の会社の利益になるような発言をしたとする。すると,どの会社とつながりがあるかはすでに報告してあるのでconflict of interest(利害関係)があることがすぐにわかってしまうわけである。要するにこのような事項は教官がアカウンタブルに行動することを保証するために入れてあるのである。
このように集めたデータをどのように分析してフィードバックし,アカウンタビリティを追求するかについては後に詳しく述べる。
2.2 学生による教育評価
前述の業績評価用のデータは教官自身によって準備されるものであるが,教育面での教官の業績評価は主に「教育評価(Teaching Evaluation)と呼ばれる学生に対するアンケートの結果に基づいて行う。学生による教育評価は講義内容,教育技術及び講義をした教官自身に関する評価である。
私が最もよく知っているカリフォルニア大学アーバイン校の物理学科をまた例にとると,学科内に教官と学生が委員を勤めるTeaching Evaluation Committee(教育評価委員会−Teachingを教育と訳すともとのニュアンスが失われるが一応こう訳しておく)という委員会がある。この委員会は教官評価のために学生に記入させるアンケートを作る作業と最後のデータの集計を受け持っている。アンケートの内容はすべての講義科目に共通で,大学院と学部の区別はしていない。以下にカリフォルニア大学アーバイン校の物理学科で使っているアンケートの具体例を示して,どのような調査をしているのか説明する。具体的なサンプルとして教育評価に使われる事項と内容を紹介しよう。
学生の講義評価
質問1から3までは対応する答えの数字で答えてください。
質問4から20までは1から7までの数値で答えてください。1=反対/低い点;7=賛成/高い点。あなたの履修した科目に関係のない質問には答えを空けておいてください。
1)学年:1.1年生, 2.2年生, 3.3年生, 4.4年生, 5.大学院生
2)この科目は自分の:1.専門分野, 2.専門関連分野,3.専門と関連のない分野
3)この科目をとった理由:1.興味があるから,2.必須科目だから,3.専門分野に関連するから,4.Breadth Requirement(注1)を満足するため。
講義担当教官について(1から7のスケールで答えてください。1=賛成,2〜6=中間,7=反対。)
4)学期始めに科目の目的及び成績の付け方の基準をはっきり伝えた。
5)科目内容に対する熱意と興味を示した。
6)概念,理論,事実など分かりやすく説明することができた。
7)クラス外でも親切に教えてくれた。(学生が教授室に質問に来ることのできる時間が設定してあり,これをoffice hourと呼んでいる。)
8)学生がクラス内の討論に参加することを奨励した。
9)私の達成したことを評価するに十分なデータを持っていた。(成績をつけるための)
10)私の仕事に対して建設的なフィードバックをくれた。
11)教え方が効果的であったかについて総合的評価を1から7で表してください。
(1=悪い,7=非常に良い)
講義科目の内容について
12)最初に発表した予定の内容と実際に教えた内容がよく対応していた。
13)講義はよく準備され,よく整理され,しかも科目内容と良くマッチしていた。
14)教科書,課したレポート,宿題は,講義とよい相補関係にあった。
15)実験/討論のクラス(注2)は有用かつ有効であった。
16)強調されたのは暗記ではなく概念の理解であった。
17)科目内容に対する思考と興味を誘起した。
18)この科目は非常に面白かった。
19)必要だった勉強の量。(1=軽い,7=多すぎる)
20)科目の総合的価値。(1=低い,7=非常に高い)
科目名:
教官名:
学生の専攻:
この科目に対するコメント:
(注1)Breadth Requirement 広い教養を身に付けるためにいくつかの専門外の選択科目をとることが要求されている。
(注2)科目によっては実験コースが付属している。また講義のほかに問題の解法などを討論する時間がある。
このアンケートからわかるように,教官は講義要覧に載せられた内容の講義をすることが要求されており,自分の好みで勝手な内容の講義をすることは許されない。(時々そのような講義をする教官もあるが,評価は低くなる。)学期が始まる前に教科書を決め,講義内容の要旨(syllabus−シラバス)を作って講義計画を決め,試験日程,採点方法なども最初の講義でアナウンスすることが期待されている。学生はそれによって1学期の勉強計画を立てる。すなわち,プランを最初に示し,学期中にそれを実行し,学期末に評価するというパターンが完結するように設定されている。これはまさに教官に対して教育者としてのアカウンタビリティを要求しているということである。
「オフィスアワー(office hour)」というのは,講義担当教官が教授室に居て訪ねてくる学生の質問に答えたり相談にのったりする時間で,こんのような予約された1週間に2〜3時間はアナウンスしてとっておくことが期待されている。この予約された時間には学生は自由に教授室を訪ねて個人的に教官のアドバイスを受けることができるようにしてあり,学生が訪ねていった教官にどう扱われたかを評価するのが上のアンケートの質問7)である。
各教官は学期の最後の講義の時にこの用紙を学生に配り約20分で記入させてすぐに回収する。回収した用紙は教育評価委員会の手で統計処理され,その結果が学科主任と教官本人に報告される。学科主任は各教官の総合評価の順位を知らされるので,誰の講義の評判がいいかを常に知っており,次年度の講義担当依頼の参考にする。教官によって低学年の科目を教えるのが得意な人,高学年の科目がよい人など色々な違いがわかるので,教官のタレントを有効に利用する資料としても重要である。非常に有名だが本気で教えないので学生の評判の悪い教授の中には,研究業績は高いのに教育評価の結果が悪いので昇級を止められた例もある。
このような評価の結果は人柄にも大きく影響されるし,教えた講義科目の性格にも依存する。もちろん学生の質にも大きく依存するので,結果は慎重に吟味される。私が居た物理学科では医学校志望の学生が嫌々ながらとる物理概論3ABCというシリーズはだれがどう教えても低い評価が出るので有名で,この科目を教えて高い評価を得た教官にはしばしばベスト・ティーチャー賞が与えられている。余り大したことは教えず面白おかしく内容の乏しい講義をして人気を上げる人も時には出てくる。しかしこのような人が大学院や高学年の講義を受け持って内容の乏しい講義をすると,学生に馬鹿にされて高い評価は得られない。学生は教官が思っているよりはるかに高い判断力を持っているものである。各講義科目の担当教官は原則として3年で交代するので,5〜6年間このような評価を続けるとおおよそ妥当な評価ができてくる。
2.3 評価結果のフィードバック
以上に説明したことから教官の業績評価のためにどのようなデータが集められるかについてはおわかりいただけたと思うので,次にこれらのデータをどのように分析し,その結果をフィードバックして大学運営に役立てるのかについて説明する。
各教官が提出した年間活動報告書は学科主任のもとに集められ,学科主任はこの報告の内容と教育評価の結果を分析してその教官に対する昇格,昇級等の人事異動提案の資料にする。ここで昇格というのは助教授から教授というようなランクの異動で,昇級というのは日本の国立大学の教官の俸給表の号の間の異動である。
教官の業績評価の基礎データとなるのは年間活動報告と教育評価を集めて作られる個々の教官の「人事ファイル」と呼ばれるファイルである。ここには過去の年間活動報告と教育評価が総括されており,昇格や昇級を考慮する時期になると各教授は主任教授が準備した人事ファイルを閲覧して教授会で該当教官の人事に関してどう投票するのかの態度を決める。すなわち集められたデータの分析は個々の教授の頭の中で行われる部分が多い。しかし助教授から準教授への昇格人事のように特に重要な決定の時には,外部の専門家の意見書を求め,その意見書も人事ファイルのデータの一部となる。(助教授から準教授への昇格が特に重要なのは,助教授には身分の保障がなく,多くの場合2年毎の契約制であるが,準教授以上ではテニュア(tenure)といって終身雇用が保障されているからである。)
学科内での討論と投票の結果,昇級あるいは昇格推薦が決まると,学科主任は学科としての評価文書と自分自身の意見書を付して人事ファイルを学部長に回す。学部長はこれにさらに自分の意見書を付して全学人事委員会に提出する。全学人事委員会は提案された昇格や昇級の妥当性を議論して結論を学長に報告し,最後に学長決裁で昇格,昇級などの人事が決まる。これが評価結果のフィードバック機構の概要である。このようなプロセスを通じて人事ファイルに集められた業績評価のためのデータは各段階で多くの人によって分析・判断される。少数の人間だけによる判断を避けることによって公平な結果を保証しようとしているのである。また全学の委員会で人事を議論することによって学内の部局間のレベルの整合性を維持することを目指している。
教官の業績の評価で日本の大学と大きく異なるのは昇級に関する取り扱いである。日本では普通に勤めていれば大体毎年1号俸ずつ上がっていくが,カリフォルニア大学では教授の場合,標準的には3年毎に上記の事項を評価して全学人事委員会が認めたものだけを昇級させる。したがって業績があがっていると認められない人のサラリーはいつまでも変わらないという事態が実際に起こる。つまり教官の業績に対するアカウンタビリティは本当にお金でカウントするのである。同じ年令や経験年数であっても教官のサラリーの間には業績次第で大きな差がでてくる。このように教官のアカウンタビリティは業績をサラリーと直結させることによって得ているのである。
逆に,非常に業績の高い人には定期以外の時期にも昇級を行い,加速した昇級がなされる。アメリカの大学間ではよい教官を確保することに関しても自由競争があるので,優秀な教官を低いサラリーで放っておくと,他の大学からリクルートされていい人を失うという事態が生じる。そのようなことが重なると教官の質が落ちるし,大学の評判も落ちる。したがって競争原理のもとで需要と供給のバランスによってサラリーも決められるのである。このように,評価,フィードバック,アカウンタビリティ,といったことはアメリカ社会の自由競争の原理と有機的に連動して有効性を発揮している。
2.4 学科,学部の評価
上で述べてきたのは教官個人の業績評価であるが,大学の中の各種の単位(学科,学部など)の評価はどう行っているか,またこのような集団に対するアカウンタビリティはどのように追求するのかについて次に述べたい。
学科や学部などの単位が効率よく機能し業績を挙げているかを評価するためには外部の有識者に依頼して評価委員会を構成する。この委員会は各学科あるいは学部ごとにその分野の著名な専門家に依頼して構成し,大体5年程度の周期で各単位の評価を行う。評価委員には学科(学部)内の各教官の業績リスト,担当講義表,講義内容の要旨,学生数,学生による教育評価の結果,リサーチグラントの契約先と金額などのデータを前もって送付して,よく検討しておいてもらう。多くの場合,5〜6人の評価委員がキャンパスを訪問し,手分けして教官と学生の両方とインタビューして学科の活動状況を調査する。評価委員会は大体2〜3日キャンパスに滞在し,最後の日には委員全員が集まって報告書を書き上げる。この報告書は学科の場合は学部長に,学部の場合は研究・教育担当副学長に提出される。
報告書の内容は,教官の研究教育活動の活発度,学生の満足度,人事の妥当性,専門分野間のバランス,予算配分の妥当性,など多岐にわたる。外部者による評価でしばしば学科の特に優れた点,弱い点などが指摘され,将来の計画に役立てられる。この評価報告書は外部の有識者の意見の総括なので客観性が強いと認識されており,そこに盛られたアドバイスには大学本部は真剣に対応することが要求される。
このような評価は学科あるいは学部全体の評価であると同時に,それらの単位の長の指導力の評価でもある。例えば学部内で人間関係がうまくいかず,望ましい協力体制がとられていないような事態が判明すると学部長の責任が問われることになる。もちろん学部長にはそのような責任を追及できるだけの権限も持たせてあるから,このような責任を問うことができるのである。すなわち上にも述べたように,例えば人事に関しては学部長は学科の意見に関わらず自身の意見を述べ行動するだけの裁量権が与えられている。
このようなアメリカの大学の状況と日本の大学の状況を比較すると,日本の多くの大学では学科主任や学部長には充分な権限が与えられていないので(あるいは形式的には与えられていても,実際には行使できる状況ではないので),いくら評価されてもその結果に対する責任の取りようがないように思われる。権限が与えられていればそれに対応する責任を追及しアカウンタブルであることを要求できるが,日本の場合権限も無しに責任を追及されてはかなわないということになるのではないだろうか。
これに関連してよく思うことは,日本の大学では教授会とか委員会とか会議が非常に多いことである。これは管理職者に充分な裁量の自由度を与えていないためで,何でもみんなで集まって決めなければならないようなシステムである。そのかわり何かまずいことが起こっても責任は特定の個人に集中していないので(形式上は別として心理的には),誰も責任をとらなくても済むというメリットがある。このような日本の大学のシステムでは西欧式の概念に基づいたアカウンタビリティを追求するのは無理なのではないだろうか。
3.日本の大学における評価とアカウンタビリティ
−どの様なシステムが可能か?
日本の大学でも最近自己評価の必要性が盛んに言われているが,大学内の現状を見ると,現在はまだ外部からの要求が強くなってきたので仕方無しに動き出したという段階である。残念ながら,大学のレベルを向上するための必要性という内部的動機で自己評価,点検をしようという機運になっているようには見えない。しかし動機はどこにあるかに関わらず,これからは評価とその結果に対するアカウンタビリティの要求,といった動きが活発化することは明らかである。大学にいる人間としては,不適切な評価方法やその結果のフィードバック機構を外部から強制される前に,一般社会に受け入れられしかも大学にとって建設的な効果のある評価とアカウンタビリティ追求の方法を考えて実行することが重要である。それではどの様なアプローチが日本の現状に即して有効かつ実行可能であろうか。
上で見てきたアメリカの大学における業績評価の仕方,又その結果のフィードバックの仕方はそのまま日本の大学に適用できないことは明らかである。これまで所々で言及したように,アメリカの大学における評価,フィードバック,アカウンタビリティの追求,といった一連の機能はアメリカという社会の構造の中で有効かつ必要なものであり,全体の環境の中の有機的構成要素として成り立っているのである。したがってその一部だけを日本に移植しても本来の目的である業績,サービスの向上という目的を達する役に立つとは考えられない。
実際,アメリカの大学においてさえも今使われている評価・フィードバックシステムが完璧だとは考えていない。明らかな問題点は,評価の周期が短すぎるために何年も結果の期待できないような息の長い研究をあえて進める人が少なくなり,短期勝負の研究が多くなってしまうことである。同様なことはビジネスの世界でも言われてきており,終身雇用と長期計画性が日本の産業が強くなった原因の一つに数えられている。日本のようなシステムの方が確かに長期的な考えで学問的に意味がある研究を進める上では優れている。実は私が日本の大学に移ったのもそこに理由がある。日本の大学の方が(少なくとも教授にとっては),周囲の状況に惑わされずに独創的な研究を進める環境がそろっている。それでもノーベル賞級の成果があまり出てこないのは,実験系の分野ではしっかりした設備が整いだしてから末だ時間が浅いことも一つの理由だと思われる。もちろんもっと大きな理由は研究者の意識構造にあるのだが。
アメリカ式の評価とフィードバックを通したアカウンタビリティの追求メカニズムの中にも,日本の大学で取り入れることが望ましい要素もいくつかある。そのひとつは,すべての評価が専門の学者によって行われる点である。これはピアーレビュー(peer review)方式と呼ばれており,学問の成果を評価するためには今の所最善の方式だと考えられている。このような学者による学者の評価の原則はアメリカの大学では始めから受け入れられていたわけではなく,長い間の試行錯誤の結果この方式が学問の自由,大学の自主性,創造性などを維持するために最もよいと判断されたのである。今でも非専門家の理事などが教官人事に介入する大学もあるが,そのようなことの起こる大学は一流校とはみなされていない。日本でもピアーレビューの原則を取り入れることは学問の自由と独創性を保証する上で非常に重要である。
次に業績評価が一ヵ所に集中して行われるのではなく,数段のレベルで行われる点も取り入れられる価値がある。上に述べたカリフォルニア大学の例では教官の業績評価は,学生アンケート,学科の教授会,学科主任,学部長,全学人事委員会の各段階で行われる。このような複数レベルの判断を用いることによって公平な評価が行われるようにしてある。このシステムの一つの難点は人事のために多くの時間とエネルギーを割かねばならないことで,実際アメリカの大学では人事考査の活動は大学の質を維持するための重要な活動として位置づけされている。
評価の結果をサラリーに反映させることによってアカウンタビリティを求めるフィードバック方式は日本の大学ではあまり効果的ではないだろうと思われる。実際,日本の大学の教官達は昇級などということとは無関係によく働いている。アメリカ人に言わせると,業績に無関係に昇級のある環境でなぜみんなよく働くのか理解できないということになる。日本の大学に残っている人たちはもともと研究が好きでやっているので,経済的動機は必要としないらしい。日本の場合,大学教授のサラリーはもともと低いからよほど研究が好きでもなければ大学には残らない。つまり経済的動機はもともと教授達の頭にあまりないのである。したがって評価の結果をサラリーに反映させるようなことをしても誰もそのために業績をあげようなどとは考えないだろう。私自身,カリフォルニア大学から東北大学に赴任した時は,当時の換算レートで年収が半分くらいになってしまった。それがわかっていても来たのは,東北大の方が研究環境がよいと判断したからで,サラリーは人並みにもらえれば生活はできるはずだと考えた。このように考えると日本の大学ではサラリーに差をつけることでアカウンタブルな行動を期待するのは無理だろう。むしろ研究費や,研究スペース,設備などの研究環境に評価の結果を反映させる方がアカウンタビリティを求める上で効果的だと思う。
日本の大学の先生方は心理的プレッシャーや社会的プレッシャー,あるいは評判といったことに対して非常に敏感である。(実はこれは日本人一般に当てはまることであり,日本人の美点でもあるのだが。)そして,評価,判断,差別などという言葉に嫌悪感を持っている人が多い。みんな公平に,平等に,評価,判断はせず,されずというのが大好きである。だから予算でも,研究スペースでも,学生数でも,何でも判断はせずにみんな同じにしたがる。そのためには委員会を作ってあらゆるケースに対応できるルールを決めて,個々の場合の判断はしないで済むようにつとめる。このような環境下では,ただ業績を評価すると言っただけでも相当な心理的プレッシャーになる。いわんや結果をはっきりとした形でフィードバックする,あるいは公表するということにでもなれば,反対論が猛然とわき上がって,業績向上の奨励という本来の目的とは逆の効果になるのではないだろうか。いずれは相当厳しくアカウンタビリティを追求することになるにしても,まずは緩やかな段階を経て実行に移すことが望ましいだろう。アメリカ流の評価,フィードバック方式を実行しようとしてもそれを業績の向上につなげるための社会環境の準備がない。
例えば,日本で業績評価をして余りよい業績のあげられない人をどうするかという問題を考えてみよう。アメリカの場合は,そのような人は自身の実力に応じた他の職場に移動する。しかし日本の場合,人事交流があまり盛んではないからそれほど移動が容易ではない。すると,低い評価を受けた人もそのまま同じ場所で不愉快な思いをしながら暮らす結果になるだろう。(こういう立場の人たちが多数いることの証拠は「窓際族」という単語が存在することである。)日本の場合いったん組織を作ってしまうと,効率の高い部分と低い部分を取捨選択する機能が存在しないのではないだろうか。特に国家公務員に関してはこのような選択機能は実質的には全くないと言ってよい。それならば始めからあまりはっきり評価をせずに,今まで通り曖昧な評価にしておいて,あまり効率の良くない部分もそれなりに機能する程度にしておく方が賢明ではないか。
最近,評価というと言葉と並んで「センターオブエクセレンス」(COE)という言葉が大学の人間の間でよく使われている。これは全部の大学をエクセレントにしようとすると金がかかりすぎるので,いくつかの中心となる大学や研究機関を決めてそこに集中的に投資しようというアイディアらしい。現存の機関で今居る人たちがみんなエクセレントになるまで待っていてはとても間に合わないから,センターオブエクセレンスを作るためにはエクセレントな人を集めてこなければならない。しかし定員が決まっている以上新しい人を集めてくるためにはあまりエクセレントでない人が移動しなければならない。現状ではこれは非常に難しいから,要するにCOEとは言っても設備がエクセレントな場所を作るだけに終わるのではなかろうかという懸念がある。
上の二つの考察からわかることは,人事交流を活発にして流動性をまず確保しなければ評価,フィードバック,アカウンタビリティといったことを議論してもあまり効果は期待できないということである。つまり人事においても市場の自由化と自由競争原理の導入が必要である。今までのように,文字どおり「一所懸命」で一つの職場に定年まで大過なくはりついていることが名誉だと考えるような日本の精神構造から変えていかなければ,世界中の大学と競争して優位を占めることは難しい。アメリカの一流大学の場合,新しい教授をリクルートする時は人種,国籍を問わず,最も業績の高い人を採用しようとする。英語がわかってしかもエクセレントな人は世界中に沢山居るから,このことだけを取ってみても日本の大学は不利である。日本語がわかるという条件を付けただけで,リクルートできる対象のプールが小さくなってしまう。世界を相手にしたCOEを作ろうとするならば,少なくとも研究所の場合は日本語はわからなくても我慢するぐらいの覚悟が必要となるだろう。日本でもせめて国内の出身大学などは問題にせず,公募して最適な人を採用するようなシステムにもっていかなければならないと思う。
4.まとめ
昔私がダートマス大学の学生だった頃「哲学の諸問題」という講義科目を取ったことがある。この科目には「哲学1」という科目番号がついていたのだが,最後の講義でユーモアたっぷりな教授が言ったのは,「科目名通り今学期は哲学にはどのような問題が存在するか教えました。答えの方が知りたかったら次の科目の哲学2を取りなさい。」このエピソードを今思い起した理由は,本稿では大学における評価やアカウンタビリティについて述べてきたが,色々な問題点はわかっていても,これだといえる解答が私にはないからである。アカウンタビリティということを特に意識して大学における評価とそのフィードバック方法について考えてみたが,大学の本来の立場から言うと業績の評価はアカウンタビリティを求めるのが目的で行うのではない。大学における評価の本来の目的はそれによって大学の質を維持あるいは向上することにある。しかし外部から見れば,大学がきちんとその任務を果たしているかチェックするという意味でアカウンタビリティを要求する必要があることは言うまでもない。結論のはっきりしない文で申し訳ないが,ここに述べたことが関係する方々が大学のアカウンタビリティについて色々お考えになる時にいくらかでも参考になれば幸いである。