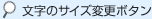第11号
日本における監査について
伊東 光晴
伊東 光晴
(京都大学名誉教授,放送学園大学教授)
1927年生まれ。東京商科大学(現・一橋大学)卒業。東京外国語大学教授,法政大学教授,千葉大学教授,京都大学教授等を経て91年より現職。早稲田大学客員教授,復旦大学名誉教授(上海),日本学術振興会学術顧問。この間,京都大学経済学部長,郵政省電気通信審議会委員等を歴任。理論経済学,経済政策専攻。
主な著書は,「保守と革新の日本的構造」,「現代経済学を考える」,「ケインズ」,「生活のなかの経済学」,「経済学は現実にこたえうるか」,「君たちの生きる社会」,「現代のなかの経済学」,「技術革命時代の日本」などがある。
1. 日米株式会社のトップ・マネジメント構造の違い
「自己監査は監査にあらず」−これは監査論のABCである。だが日本の企業の監査に関するかぎり,このABCが実現されているとは思えない。理由は明白である。株式会社の会計監査を第三者として担当する公認会計士が,会社の日常経営の責任者である社長によって,日本では任命されている。社長によって任命された者が,社長以下の日常経営者が行った業務を監査するのであるから,この業務の問題点を洗い出し,その誤りを指摘し,これを正すことは極めて困難である。これを強行する時は,辞任を覚悟しなければならない。
一定規模以上の株式会社の会計監査を行う公認会計士の制度は,日本では戦後,アメリカの占領下において,アメリカの制度にならい1948年に導入された。有価証券報告書に記載された決算の内容が,正確で妥当であるかどうかを公認会計士に監査させ,その意見を監査報告書として添付させ,投資家が正確な判断を下すことができるためのものであった。それはアメリカにおいて,投資家保護のための制度として機能していたところから,日本への導入がはかられたといってよい。
だがアメリカで機能を発揮したといっても,日本で同じ効果を持つとは限らない。株式会社といっても,その構造はアメリカと日本とでは異なるからである。
アメリカは連邦国家であり,法の内容は必ずしも一様ではなく,州によって異なる場合もある。しかし,巨大企業のトップ・マネジメントの構造は二層構造である。それは株主から委託された「受託経営層」と日常の経営を行う「一般管理層」とからなっている。受託経営層は株主総会で選ばれた取締役(Director)が取締役会(Board of directors)を構成しており,その議長をつとめるのが取締役会長(Chairman of the Board)である。
取締役会のなすべき仕事は,企業経営の基本的方針を樹立し,日常経営を行うのに最適の社長(President, Chief executive officer)以下の経営者−副社長(Vice president),役員(Executive officer等)を選任する。つまり人事権を所持している。そして,日常経営が基本的方針にそって成功しているかどうか,経理内容が適正であったかを監査する。つまり,基本的方針の樹立,人事権,監査権の3つを所持している。これに対して,社長以下の経営陣は,日常経営を行い,業績いかんによっては,解雇され,時に成功報酬をうる。
この構造は,最近のアメリカの経済学のエイジェンシー理論の現実的基礎である。株主は,自己の利益を推進してくれる取締役という代理人(エイジェンシー)を選ぶ。この取締役は,非常勤の社外重役が多く(取締役会長は常勤)その一部が業務執行委員会(Executive Committee),財務委員会(Financial Committee)等を構成し,自己の職務を遂行するための代理人を選ぶ。日常経営では自らにかわってより適切にその職務を遂行する代理人として社長以下の経営技能者を任命し,その結果の監査には,公認会計士,経営コンサルタント等の専門人を代理人として,監査を行わせるのである。
このように,株式会社のトップ・マネージメントが二層構造になっている結果−会計監査に例をとれば−公認会計士は取締役会からゆだねられ,企業会計を監査するのであって,その報告書は取締役会に提出され,その報告いかんで,社長以下の日常経営者は入れかえが行われるとともに,のちにその監査に問題があることが明らかになれば,株主ないし取締役会から損害賠償の訴えを受けることになる。そのため,その監査は専門人としての職業倫理にもとづき,厳格に行わざるをえないのである。その構造は,ちょうどわが国のプロ野球のトップと同じである。
プロ野球では,日常の試合を指揮し,選手を動かす監督以下の首脳陣と,経営陣ともいえるフロントと二分されている。フロントはオーナーによって選任され,いわば,アメリカの企業の取締役会を構成している。フロントの行う第一の仕事は,基本的方針の確立である。ドーム球場を建てるか,どの程度の資金を投入するか,そして何よりも適切な監督をスカウトすることである。
選ばれた監督は,ちょうど,社長が,信頼できる事業分野の責任者を任命するように,コーチを選ぶ。そして結果の成績いかんによって,フロントは監督との再契約を行うかどうかを決定する。フロントは野球のプロである必要はない。それと同じように取締役は必ずしも経営の専門家ではない。それゆえに,業績の評価は,専門人に委ねるのである。
このようなアメリカの株式会社に対して,日本の株式会社は,法的には二層構造,実質は一層構造である。
法的に二層というのは,わが国の商法は,昭和25年,戦後のアメリカの大きな影響のもとで大改正を行い,取締役会を新設し,アメリカ的二層構造の体系をととのえたからである。したがって日常経営を行う組織は社長以下の一般管理層であり,この社長を任命する権限は取締役会にゆだねられているのである。
だが現実はこのようにはなっていない。社長の部下である営業部長とか,総務部長とか,工場長とかが,取締役に任命されている。そしてこれらの取締役の頂点に立っているのが,取締役社長なのである。
それは多くの場合,一社員として入社したものが,業績を積み,しだいにその地位をあげ,従業員から経営者に進みその中の一人が社長となったものである。しかも企業の株の過半数は関連企業が保有しているもの,つまり相互持合いであるため株主の力は企業経営にほとんど影響するところがない。この結果,日本の大企業は社長以下の日常経営を行う経営者層を監査する取締役が社長の部下であり,受託経営層と一般管理層とが一体化しているという意味で自己監査組織なのである。
たしかに法律によって,一定規模委譲の株式会社には,公認会計士による会計監査が義務づけられている。しかし,この公認会計士を雇用するのは受託経営層の代表としての取締役社長であり,それによって監査を受けるのも一般管理層としての社長以下が行う日常経営である。それゆえ,その監査はアメリカの株式会社のように文字どおりの外部監査とはならないのである。
2. 監査は組織にしたがう
なにゆえ,アメリカにおいて二層構造の株式会社が生まれたのであろうか。私は寡聞にしてその理由を知らない。もちろんアメリカはその建国の歴史をたどるまでもなく,イギリスの強い影響下にあった。法律そのものも英米法であって,日本のように大陸法の影響下の国とはその構造を異にしている。しかし,イギリスの株式会社はアメリカと異なり,そのトップ・マネージメントの構造は伝統的には一層構造なのである。つまり,株主総会によって取締役が選ばれ,それが取締役会(Board of Directors)を構成し,取締役の中から日常経営の責任者であるManaging Director(業務執行取締役=専務取締役)を一人ないし数名選んでいる。わが国の代表取締役である。
国際的に著名な会計学者である高寺貞男京都大学名誉教授によると,アメリカにおける公認会計士制度の発達は,アメリカの歴史と深くかかわっており,アメリカに企業を設立したイギリスの資本拠出者たちが,日常経営を行う一般管理層をコントロールし監査する組織をつくり,イギリスから会計監査を行う会計士を派遣し,その報告いかんで日常経営を行う責任者の入れかえを行ったことに源を発しているという,これがアメリカにおいて公認会計士制度の発達をうながした理由であり,アメリカ的トップ・マネージメントの組織を生むことになったものと思われる。
たしかに,イギリスにおいて会計士の歴史は古い。しかし,株式会社においては多くの場合株主総会において1名以上の会計監査役(auditor)から選ばれており,アメリカのように外部の人間(公認会計士)による監査が行われてはいなかった。その意味ではわが国の監査役に類似しており,ちがいは,イギリスではそれが会計についての高度の技能と経験を必要とするところから,1948年の法律によって公認された職業会計士団体の会員であることが要求されるようになったことである。また最近では経済の国際化にともなって,外部監査がふえ,企業内部の会計監査人との間でやりとりが行なわれる場合が報告されている。
アメリカの経営学者チャンドラー(A. D. Chandler)は『経営戦略と組織』(Strategy and Structure, 1962.)において有名な"組織は戦略にしたがう"という言葉を論証した。この言葉をもじるならば,「監査は組織にしたがう」ということができる。アメリカ企業のトップ・マネジメントの二層構造は,公認会計士の監査を精査とさせている。ここで精査というのは,企業の元帳簿を洗い,元伝票まであたることをいう。もちろん企業内のすべての部門を精査することはできないので,特定部門を選び,これを行うのが普通である。このようなことを行うのは,万一,不正,不適切な会計処理が行なわれていたことが発見されず,それが株主ないし投資家に不利益をもたらした時,その責任を負わなければならないという受託経営者層の存在ゆえである。
これに対して,わが国の場合には,法的に公認会計士の監査は義務づけられているけれども,それは会社が作成した財務諸表やその基礎資料を調査し,それが企業会計原則に則して処理されているかどうかを判定するものとなっている。例えば,減価償却が従来と同じ定額法(定率法)をとっており,継続性の原則にしたがっているかどうか,減価償却法を変更し,利益操作が行われていないか,在庫を含めた資産評価が適切であるかどうかを判定していくのであって,元伝票まであたることをしないのは,受託経営者層と一般管理層が一体化している自己監査の組織構造によるところが大きいのである。
この日米の株式会社の組織のちがいが監査のちがいを公衆の前に示した一例が,わが国においてロッキード事件として政治スキャンダルとなり,首相を辞任させた一連の事件である。
1972年アメリカの巨大航空機メーカー,ロッキード社の監査を担当していた,アメリカ八大監査法人(八大は当時,現在は集約されている。)のひとつ,アーサーヤング会計事務所のウィリアム・フィンドレー公認会計士は,奇妙な伝票を発見した。ピーナッツ何個と記載されたものである。これは直ちに調べられ,それが日本,イギリス,イタリーをふくむ海外各国の政治家への献金であることが判明した。事態を知ったアーサーヤング会計事務所は受託経営層に注意を喚起した。
問題はそれでおさまらなかった。
1975年,海外の政治家への献金は100人をこえるものであることが判明した。フィンドレー公認会計士は,本来の受託経営層からなる取締役会の招集を要請した。アメリカの大企業においては基本的方針を樹立するために,一般管理層の中から取締役を兼任させている場合がある。ロッキード事件で,丸紅や児玉に接して献金を指揮していたとして,しばしば新聞紙上に登場したコーチャンがそれである。かれは,当時社長として,一般管理層の長であると同時に,取締役として受託経営層の副会長を勤めていた。ロッキード社は,コーチャン等をはずし,本来の受託経営層からなる取締役会でこれを議している。これについて,私はかつて次のように書いた。
「多国籍企業小委員会に呼ばれたアーサーヤング会計事務所のウィリアム・フィンドレー会計士の証言を記録で見るかぎり,かれは,帳簿にない資金,つまり海外のかくし金のありかも,海外のコンサルタントの存在も,ピーナッツ等の領収書の意味も,ほとんどすべて調査していることがわかる。米上院銀行・住宅・都市問題委員会(プロクシマイヤー委員会)の記録によるとロッキードの取締役会会長D.J. ホートンは,SEC(証券取引委員会)の記録によると,ロッキードの公認会計士から詳しい内容を入手したこと,自分がSECから聞かれ答えなかったことでも,公認会計士を通じてSECは知っていたこと等を証言している」(伊東光晴『経済学は現実にこたえうるか』岩波書店P.84)
ここで注意しなければならないのは,ロッキードのこの問題は,日本で問題になった多国籍企業小委員会(チャーチ委員会)で,はじめて取り上げられたものではなかったことである。それよりはるか前に,銀行・住宅・都市問題委員会(プロクシマイヤー委員会)への資料としてSECから提出されたものである。SECは,公認会計士から得た資料のうち,外交上の問題を考え,政治献金を受けとった外国人政治家の名前を消して委員会に提出し,もし法案作成上,外国人政治家の名前が必要であるならば,裁判所の判断を求めてほしいことを申し出ているのである。チャーチ委員会はこのすでに知られている資料をプロクシマイヤー委員会からうけとり,これを取り上げたのであって,たまたまそれを傍聴していた日本人新聞記者によって日本に報じられ,大きな事件へと発展したのであって,もし,プロクシマイヤー委員会に日本人記者がいたならば,より早く問題となったものにすぎないのであって,一部政党人や週刊誌が言うように,政治的意図がアメリカ側にあったわけではない。問題はアメリカの株式会社の組織構造とそれにもとづく企業監査のあり方ゆえなのである。
これに対して日本の場合は対照的である。
「日米間の企業監査のちがいは,公認会計士の人柄や能力のちがいではない。制度のちがいにもとづくものである。であるから,いざ企業が倒産したとなると,日本では過去の経理が明るみに出,これを監査した公認会計士が問題になることが多い。
一例は,1974年に倒産した『日本熱学』にも見られる。事前の公認会計士の監査の結果では,無限定「適正」−つまり100%適正であった。しかし倒産後,大阪地裁が等松,青木監査法人に調査を要請したところ,経理は乱脈で,粉飾決算は1971年ごろからはじまり,153億円の損失をかくし,別に子会社等のための148億円があった。しかも公認会計士は一方でこうした監査を行いながら他方で社長から増資のさい株を時価より安くもらうということをしていたのである。」(伊東光晴『経済学は現実にこたえうるか』P. 82)
このようなことは,たんに日本熱学の事例だけではない。古くは大同製鋼をはじめ,多くの企業にみられるところである。
これに対して,「商事会社としてトップ五社(三菱商事,三井物産,丸紅,伊藤忠,住友商事)につぐ位置にありながら,アメリカの子会社のために事実上倒産した安宅産業の場合には,逆にアメリカの公認会計士の厳しい不良債権指摘に端を発し倒産した。つまり安宅の子会社,アメリカ安宅がカナダの製油会社NRC(ニュー・ファウンドランド・リファイニング・カンパニー)に多額の債権を持っていた。他方,NRCと取引関係にあるアメリカの会社があり,この会社の公認会計士が,NRCに対する債権は不良債権だと監査報告書が指摘した。その波がアメリカ安宅のNRCへの債権にも及び,アメリカ安宅の経営がおかしくなって,それが安宅に飛び火したのである。アメリカの公認会計士のきびしさが粉飾決算を許さなかったといってよいだろう。こうしたちがいが,同じ資本主義の企業でありながら,トップ・マネージメントの組織のちがいによって,生まれてくるのである。」(伊東光晴『経済学は現実にこたえうるか』P.82〜P.83)
問題は,公認会計士の監査だけではない。
わが国にはアメリカの株式会社にない監査役制度が戦前から存在している。それはイギリスのauditor(会計監査役)と同じように株主総会によって選ばれている。本来的にこの監査役は,企業の経理を監査し,経営全体について株主にかわって監査すべきものである。もちろんそのような職能を遂行するためには,自らの権限下にある事務局を持ち,専門スタッフをかかえていなければならない。こうした制度の背後にある考えは,ちょうど政治における三権分立の考えと同じように,株主総会を立法府である議会に,社長以下の経営陣を行政府になぞらえ,監査役は司法にあたるものと考えられていた。
私は昔,朝日新聞に"監査役は企業にとって盲腸のようなものである。あってもなくても良い。それは機能していない"というようなことを書いた。その後,商法が改正され,世上では監査役と公認会計士の権限が強化されたといわれている。だがはたしてそうかどうか疑わしい。イギリスとはちがい,いぜんとして,監査役の多くは,経営の専門人でない人が多い。独立したスタッフも持っていない。それは機能していないのである。
日本は海外に学ぶことにかけては他に類をみない。監査役制度も学んだ。それに加えて公認会計士制度も導入した。監査は二重である。ではそれによって正確な有価証券報告書が提出されているが−それはきわめて疑わしい。日本における株式会社の構造がそれを不可能にしているのである。
3. シティ・マネージャー制−行政におけるトップ・マネージメントの二層構造−
監査は株式会社だけのものではない。公企業の場合にも,行政体の場合にもある。この場合,注意しなければならないのは,行政体においても,その監査がどのような意味を持つかは,組織によるところが多い。この点で,日本にとって興味深いのは,アメリカのシティ・マネージャー制であろう。
アメリカは人々が集まって都市をつくり,都市が集まって国家(州 States)をつくり,州が集まって合州(衆)国をつくったといわれているように,法律も州ごとに違う場合が多く,自動車の排ガス規制ひとつをとっても,NOxがカリフォルニア州では0.25g/km以下,連邦では0.62g/km以下と,カリフォルニア州が厳しいのに対して,COはカリフォルニアでは4.38g/km以下,連邦は2.13g/km以下と逆に連邦が厳しくなっている(1991年)。地方税にしても,そこに住む人たちが決めるのであって,税率は地区によって異なっている。都市行政の形態も,その地域が選ぶものであって,異なる組織が並列しており,俗に"アメリカは地方自治形態の見本市である"といわれている。
もちろん,日本と同じように住民が選挙によって市長を選び,これが市行政を指揮し,また住民が選ぶ議員が議会を構成するという場合もある。しかし興味深いのは,シティ・マネージャー制をとっている都市である。
シティ・マネージャー制をとる以前は,選挙で選ばれる議員は,都市によってちがうが,日本と同じように45人と51人とか,かなり多数であった。まずその削減が行われた。少ない場合は5人,多い場合が9人,7人のところもある。この少数の議員が市議会を構成し,その中の一人が議長となり,市を代表する者(市長)になる。市議会がまずなすべきことは,市の日常行政を行う責任者であるシティ・マネージャー(City Manager 市支配人)を選ぶことである。シティ・マネージャーは,市行政の専門家で,専門人としての知識と経験を持っている人である。他の市の行政で業績をあげた人,またはそうした人のもとで手腕を発揮した人をスカウトする−これが市議会の第一の仕事であり,その任命権とともに業績いかんで解雇する権限を持っている。
市議会の第二の仕事は,市行政の基本的方針をたてることである。政策の決定,それにもとづく市条例の議決,税制と税率と起債の決定等である。議員は日常いくつかの委員会に所属し,週一回程度ないし隔週に会合を開き,各分野の行政がどのような形で遂行されているかを把握し,必要に応じて市議会の意志をシティ・マネージャーを通じて行政に伝える。
これに対して,シティ・マネージャーは行政についての責任者であり,それを遂行するための行政組織をつくり,自らが信頼し任命するスタッフを要所に配置し,基本的方針にもとづき,もっとも効率的に成果を収めるよう努力する。職員の任命権はシティ・マネージャーが持っている。またシティ・マネージャーは市の各種委員会に出席し,行政の専門人として委員会の顧問的役割をはたし,議会と行政との橋わたしをつとめる。
議会がなすべき第三の仕事は,シティ・マネージャー以下が行う行政の監査である。会計,行政について,必要があるならば,専門人に委嘱して監査を行い,その結果いかんで新しい方針をつくり,条例を定め,シティ・マネージャーの変更を行う。
シティ・マネージャー制は20世紀のはじめに生まれ,20年代から戦後にかけて,アメリカの小都市から中小都市に波及し,今日では,3,000に近い都市がこの制度をとり,カナダ,北欧,ドイツなどに影響を与えている。
19世紀末のアメリカは地方政治の腐敗が進行し,一ジャーナリストの告発によって世論が大きく湧きあがった時期であった。こうした背景のもとに1908年にヴァージニア州の人口1万2千人ほどの小都市スタントン市に導入されたのが,はじめであるといわれている。
シティ・マネージャー制は一見して明らかなように,アメリカの株式会社のトップ・マネージメントの二層構造を市の組織の中に導入しようというものであり,スタントン市自身,こうした意図を持って試みられたといわれている。市民が株主にあたり,選挙によって選ばれた議員は,市民の権利を受託された人たちであり,企業の取締役人にあたる。議員は行政については素人であり,それゆえに文字どおり市民の代表であるが,かれらは市行政の専門家をシティ・マネージャーとして選ぶのは必ずしも経営のプロではない取締役が,経営の専門家をスカウトし,これに社長職をゆだねるのと同じである。注意しなければならないのはシティ・マネージャー制は,アメリカ民主主義精神のあらわれだという点である。民主主義−それはデモクラシーであり,権力(クラシー)は民衆(デモス)にあるというものである。シティ・マネージャー制は,市民から選ばれた議員−それは,行政,政治の素人でよい−が人事権をはじめ権力を持っている。しかしデモクラシーが愚民政治に落ちいらないように,専門人(メリットある人間)=行政の専門家であるシティ・マネージャーがこれを支えているというものである。専門人は,その専門知識によって,時に市民代表と議論し,自説を主張する。しかし最後の決定は市民代表がするというものである。シティ・マネージャーをはじめとする行政は,外部監査されることによって,その姿勢を正しうると同時に,ディスクロージャーされ,市民が自治を考える基礎を提供することができるのである。
わが国の地方自治体の監査は,このような外部監査ではない。日本の企業がそうであるように,市長のもとにある監査部門による監査という点で外部監査とはいえないものになっているのでないだろうか。
4. 監査は目的にしたがう
組織は戦略にしたがい,監査は組織にしたがうと書いた。しかし,たしかに監査の質は組織にしたがう。と同時に,監査の種類はひとつではない。どのような監査を行うかは,その目的にしたがうのである。再び企業会計にもどろう。
今日,会計学は大別して二つに分かれる。
第一は株主ないし投資家のための会計であり,第二は経営者のための会計である。前者は古くから存在する会計学が意図したものであって,複式簿記を技術的基礎として,一年間の収入支出をとらえ,損益の計算を示し,同時に企業の資産・負債の現状を示そうというものである。こうして損益計算表,貸借対照表を作成し,それを公開することによって企業外部の利害関係者に対して企業の実情−財政状態と収益状況を公示しようというものである。
これに対して,戦前から戦後にかけて,原価計算論として一般化していたものでは,アメリカの影響のもとに,しだいに管理会計へと発展しだした。それは,行程ごと原価計算を発展させ,その変動を企業内部に公示することによって,原価意識を下部にまで浸透させ,従来の標準原価計算等との比較,効率の測定等を通じて経営管理の手段として会計手法を用いようというもので,経営者のための会計学ということのできるものである。
前者が外部者のための会計であり,現状を正確に表示することを意図したものであるのに対して,後者は企業の内部のためのものであり,あるべき経営を求めるための手段としたものである。
行政体においても同じようなことがいえよう。監査目的が,定められた法規,規則に従って金銭の支出が行われているかどうかを調べるのが,従来の会計監査である。だが行政監査のように,あるべき行政のために,現状が妥当であるかどうかを監査する分野は今後ますます重要性をますものと思われる。歳出削減のための監査−こうした監査の重要性は,その目的達成のためにも,監査担当の主体が,どこに所属し,どのようなスタッフと組織を擁しているかが重要になるのである。
5. 日本での改革のために
私は今まで,日本の企業,自治体の監査体制の現実が外部監査になっていないこと,それゆえに機能を発揮していないことを指摘し,それをアメリカのそれと対比してきた。しかし企業についていうならば,アメリカのように,株主の力が強く,それが監査体制を支えているシステムを日本でも作りあげるべきであると考えているわけではない。なぜならば資本主義の発展は,企業における所有者の力を弱め,経営者の力を強めていくという経営者革命の進展は必然と考えるからである。このことは1932年のバーリーとミーンズの著書『近代株式会社と私有財産』(A.Berle and G. Meanse: The Modern Corporation and Private Property. 1932)以来,多くの人に受け入れられているところであろう。ガルブレイスの言う「経営における権力の所在」は経営者に移ったと。
だが,私が言わんとするところは,同じ所有と経営の分離といっても,アメリカと日本とではその実態が異なっているという点である。たしかにアメリカにおいても日本においても,かつての大陸法のように株式会社における株主総会万能主義ではなく,株主総会は,商法および定款に定める事項についてのみ決議することができるのであり,経営に関する全権限は受託経営層である取締役会に与えられている。こうした法体系の上で所有と経営が分離し,経営者に力の移行がみられている。しかし同じ所有と経営の分離とはいっても両者は大きく異なっているのであって,このことをほとんどの人は指摘していない。所有と経営とが分離しているとはいえ,アメリカにおいては取締役会は株主の権利を無視して行動することはできず,高配当,高株価を維持するために努力し,そのために社長以下の日常経営担当者に監視の目を光らせざるをえないのである。
だが戦後の日本は,アメリカ以上に所有と経営の分離が大きく進行し,逆に株主の力は大きく減退している。株主総会で経営者が制約されることは99%ない。日本は世界でもっとも経営者革命が進行した国である。そのことが,利潤を高配当にまわさざるをえないアメリカ企業とちがって,再投資を可能とし,日本企業の高い成長を支えてきた大きな要因とさせたのである。
問題は歴史の流れであるこの構造が,共同体的日本経営と合して,監査を自己監査とし,それが監査の形骸化をもたらしている点である。かつて,管理社会に対する反対から自主管理が叫ばれた。たしかに,自立した個人からなり,自らに厳しく,かつ自己改革への意欲が強い人々からなる理想の社会であるならば,自主管理は望ましい体制である。だが現実はこのような理想の条件をみたすものではない。自己管理は腐敗を生む。これを防止するためにも,外部監査体制をつくりだすことが必要なのである。
問題はそれだけではない。私はかつて多国籍企業の日本における実情を調査したが,このとき,日本に株主が一人もいない多国籍企業については,株主保護の視点からなる商法,証券取引法の下では,財務諸表を公開する義務を負っていないのをあらためて知った。それゆえ公表資料を通じて,その企業の実態を把握することができないのである。1958年,ヨーロッパ資本自由化とともに,アメリカ資本は国境をこえてヨーロッパに進出し,多国籍企業が生まれてくるのであるが,この時,従来の関連企業を,株式の100%支配の企業にかえることによって企業機密の保持をはかったことは,よく知られるところである。株式の100%支配−それはけして例外ではなく,多国籍企業の現代的形態なのである。とするならば,現行法規の基礎となっている株主保護,投資家保護の基本的視点は改変されなければならない。それは公益の利益を代表するものでなければならず,企業の巨額な使途不明金の存在を許すものでもなく,アメリカの監査が,SECにロッキードの海外支出を具体的に報告したように,大蔵省証券局に,その実態を報告するようなものでなければならず,そのために,元伝票にもあたるものでなければならない。もしこのような監査が行われるならば,わが国のような総会屋の存在は一掃されるだろうし,政治への裏献金問題も解消されるはずである。
プロフェッショナル・フリーダムの上に立つ公認会計士の自主組織をもとにして行われる公的監査は,公認会計士の社会的地位を高める。精査によって仕事量は数倍に達しよう。しかしそれは社会のあり方を正すためのコストである。今日必要なことは,公認会計士の収入を低下させても,その社会的地位を向上させることであると考える。
行政についての監査については,監査結果が生かされるものでなければならない。そのためには,監査主体がアメリカのように,予算決定にリンケージしているか,議会と絡んでいるか−いずれにしても,それによって力を得,外部監査の実をあげることが望ましい第一であり,第二は会計監査をこえて−ちょうど私企業の管理会計のように−あるべき行政を求める行政監査をあわせ持つものへ,であろう。