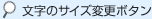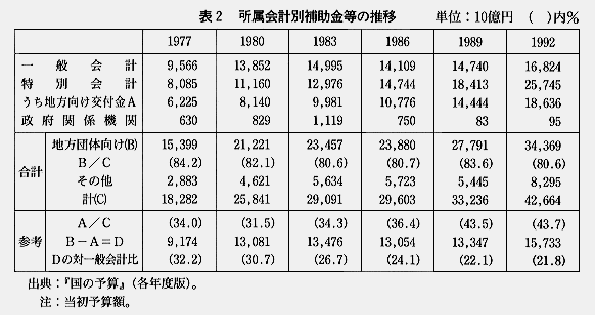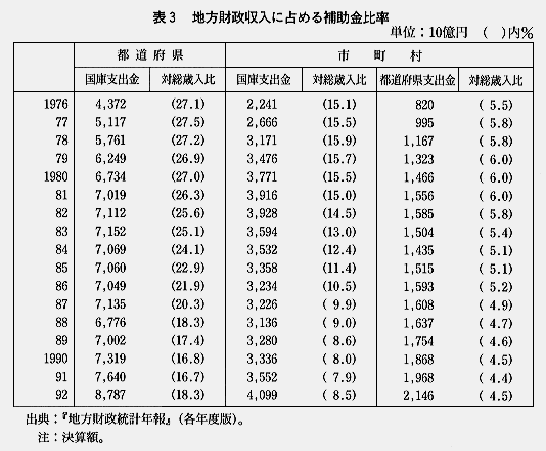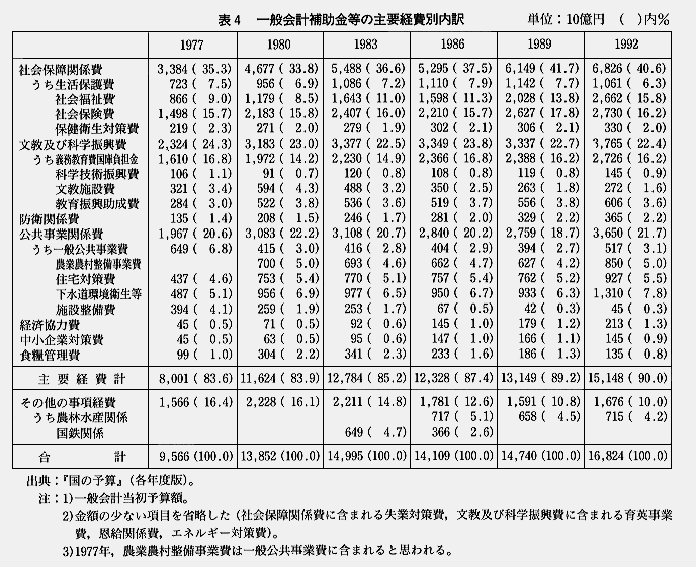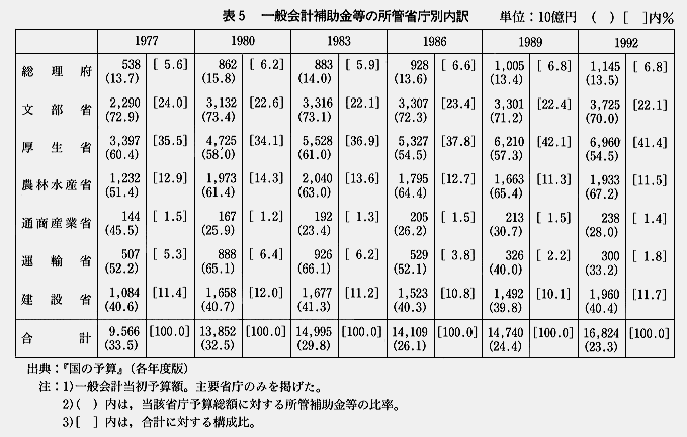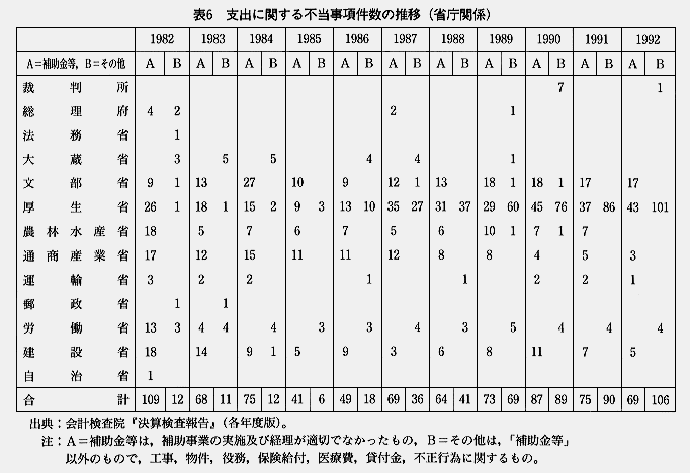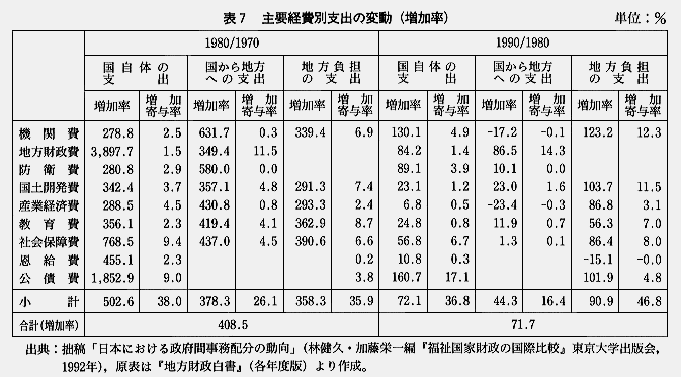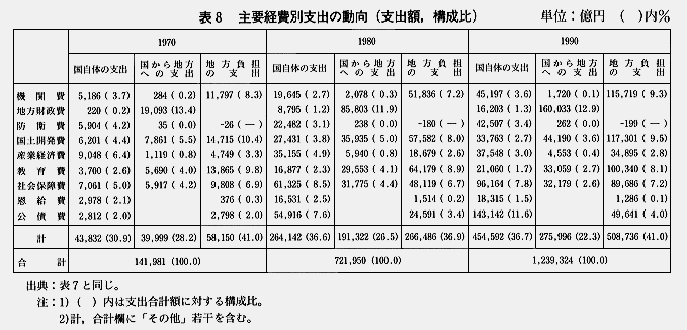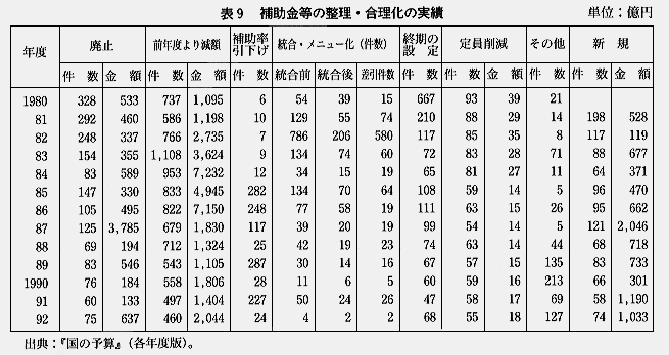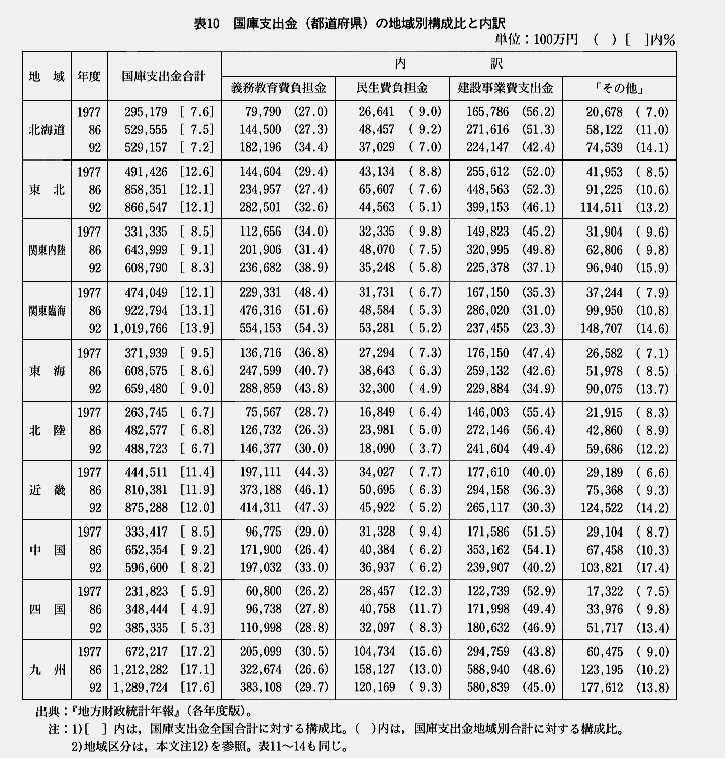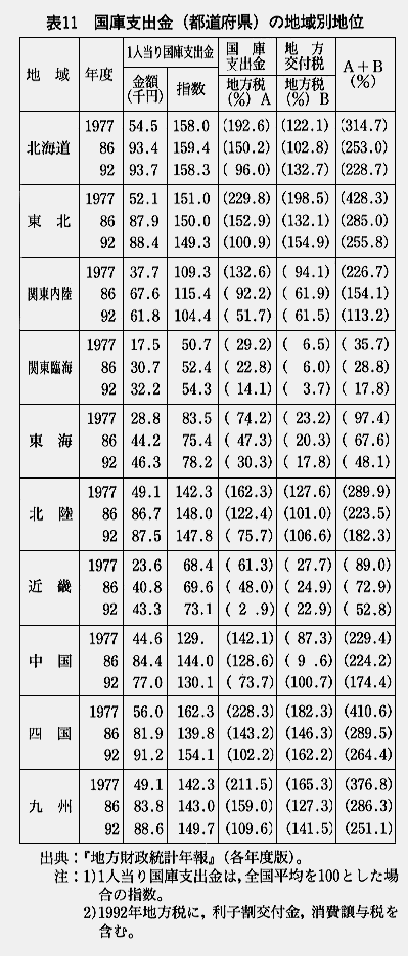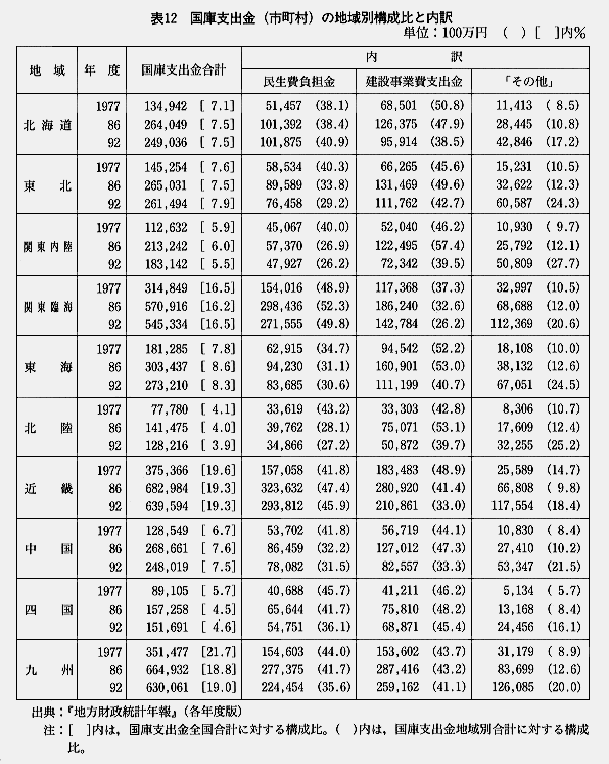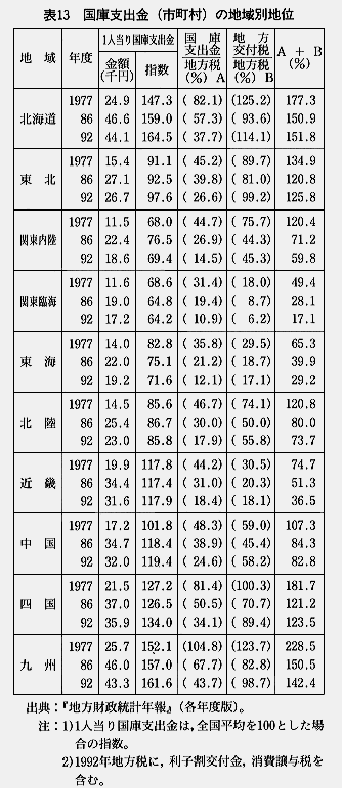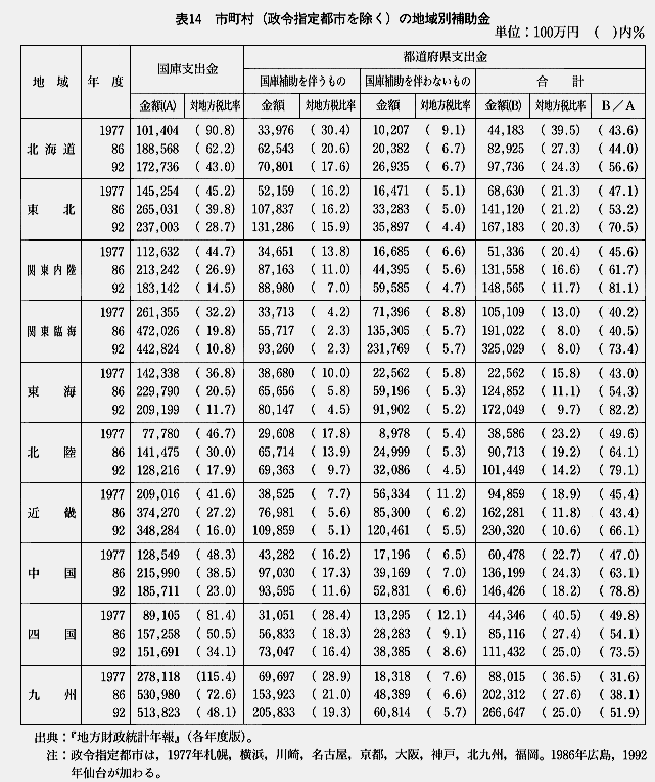第10号
補助金の再編と政府間財政関係
金澤 史男
金澤 史男
(横浜国立大学経済学部助教授)
1953年生まれ。東京大学大学院経済学研究科博士課程修了。90年より現職。財政学,地方財政,地域経済,地域開発専攻。財政学会,地方財政学会,土地制度史学会,歴史学研究会,等に所属。
主な著書・論文は,『先端技術産業と地域開発』(共著)御茶ノ水書房,1988年,『消費税の研究』(共著)青木書店,1990年,「日本補助金論序説」『社会科学研究』第39巻第4号,1987年12月,「日本における政府間事務配分の動向」『福祉国家財政の国際比較』(林健久・加藤栄一編)東京大学出版会,1992年など。
はじめに
世上に「地方分権」を求める声が喧しい。「地方分権論」は,様々な色合いの主張が錯綜し,議論の対象も広範囲にわたっているが,必ずといってよいほどとり上げられているのが,補助金の弊害である。たとえば,地域自立の条件を探ったという日本経済新聞社のリポートでは,自主財源が限られる地方自治体にとって,国の補助金は,プロジェクトを進める「命綱」であり,許認可権や行政指導とあいまって画一的になりがちな中央依存型の地方行政を支えていると指摘している(注1)。また,「若手官僚グループによる政策提言」においても,行政投資配分の抜本的見直しとして,「国で公共事業の枠を定め補助金をばらまく方式をやめ」たり,「個別補助金から包括交付金への切り換えにより,地方分権を進め,究極的には公共事業の廃止をめざす」(注2)などとされている。
日本の行財政システムが大規模な見直しや改革の対象となるとき,広義の補助金(注3)である地方交付税も含めて国から地方への財政トランスファーが問題とされるのは,ある意味で当然といえる。第一次大戦期をへて萌芽的に形成され,昭和恐慌期から戦後改革期にかけて,その骨格が固まった現代日本の行財政システムは,国際的にみても国から地方への大規模な財源再配分を際立った特徴としている。したがって,行財政の総体が見直されるということは,必然的に財源再配分の主要なルートをなす補助金と地方交付税のあり方が俎上にのることを意味するからである。
今日,補助金への批判は,主として以下の5つのタイプに分けることができる。第1は,補助金が既得権化しやすく,政策目的の必要性が消滅したり,そこからはずれたものが少なくないこと,第2に,その規模が零細かつ事務が煩雑で,目的が重複するなど,概して非効率であるという点で,第1,第2については農業や中小商工業向けなどのいわゆる低生産性部門への補助金が標的となることが多い。第3は,道路,港湾など生産基盤への補助が優先・優遇されている点であり,生活関連施設への補助については「超過負担」問題などが焦点となってきた。第4は,政権党が選挙民の支持を獲得するための手段に利用されている点であり,補助金の政治的機能に対する批判である。第5は,強い官僚統制を伴って運用される結果,地方自治を蝕み,地方の中央依存体質を再生産しているという点である。
これらの諸点の多くは,一般的には財政学の教科書が教えるところでもあるが,日本の実態に即して検証した今村奈良臣の研究(注4)(主として第1,第2の点)や広瀬道貞の研究(注5)(主として第4,第5の点)などは,補助金の問題点をリアルに伝える上で大きな役割を果たしたと思われる。
しかし,その後,1980年代から90年代にかけて,補助金への批判は総じてパターン化しているようにみえる。ところが,今村や広瀬が問題にした1970年代後半の時期の補助金と,1990年代前半のそれとは,様変わりといってよいほど構造と機能が変化している。今日,補助金論議を深めるためには,かつての補助金批判を繰り返すだけでは十分ではない。論議の前提として,この10数年間における補助金自体の変容を見極めることが必要である。
1980年代の中葉に本格化する補助金制度の再編について,最も体系的に扱ったのは,宮本憲一編『補助金の政治経済学』(朝日新聞社, 1990年,以下『政治経済学』と略す)であろう。主要な論点をかいつまんで記せば,(1)まず総論では,補助金の日本的特徴として,①産業基盤優先,② 「草の根保守主義」の支柱,③官僚的集権性を挙げ,それが新保守主義に基づいて民営化や規制緩和,新中央集権と歩調を合わせ,福祉国家からの「離脱」志向のもとで,社会サービスの整理の一環として補助金が削減され,他方で民活助成としての補助金政策が強化されてきたことなどが指摘される。さらに,(2)補助金政策の変化として,①社会保障関係補助金の伸びが著しいこと,②抑制基調の公共事業関係費が1987年度を機に再び拡大していること,③政権党と旧中間層を結びつける農業,中小企業対策関連補助金が減少傾向のなかで内容に変化が見られること,④国際化,情報化,サービス化などに対応した新しい補助金が登場していることが摘出され,(3)都市補助金については,補助金カットが大都市圏の自治体をねらい打ちしており,農村重視型の配分構造が温存されていること,(4)農村補助金については,都市新中間層を支持基盤とした農村型補助金政策の転換が現実に進むなかで,経済効率主義を超えた農村保護理念の必要性を対置すべき段階に至っていること,などが述べられている(注6)。
小論が,ファクト・ファインディングの点で,この共同研究につけ加えられるものはそれほど多くはない。同書の検討対象が,補助金の再編政策が本格化した1988年ごろまでであるのに対し,小論では1990年代初頭までを視野に収め,やや長期的視点から再編の局面を2つに分け,国内しかも地方向け補助金に焦点を絞って,その特徴を検出することが,主要な課題となる。
さらに,検討の視点として留意するのは,補助金の本来の役割の一側面をなす財源保障機能およびこれを通じた財政調整機能のあり方であり,同様の機能を備えた地方交付税の動向と併せて分析していく。この点を軽視して,パターン化された補助金批判を繰り返していると,地方自主財源の強化,財政調整資金(地方交付税原資)の増額,権限委譲などが棚上げされたまま,一方的に補助金の削減だけが進み,上の2機能が著しく弱化するおそれをなしとしない。
以上を踏まえて,小論では,第1に,補助金の推移を1970年代後半から90年代初頭までのやや長期間にわたって追い,現段階の歴史的位置を確認し,第2に,そうした動向を規定した補助金政策の特徴を1980年代を中心に検討し,第3に,補助金の地域別配分の動向を検討するなかで財源保障機能,財政調整機能の変化を探っていきたい。
一、補助金の推移と現段階
第二次世界大戦後の日本財政は,一般会計において一貫して30%前後の補助金を擁していた。戦後改革期の末期には復興政策の主要手段である基幹産業への各種補給金,戦後処理経費が縮小し,1950年にはシャウプ勧告に基づき約305億円の補助金削減が断行された。しかし,その数年後「凡百の補助金が中央各省と地方団体との各種の連携を構成した。補助金はいよいよ細分化していよいよ増大し,濫費の弊を強めている」(注7)という状況が進展した。政府審議会で毎年問題となった補助金の整理も,その「重点化,効率化」を課題とするに留まり,結局,一般会計比約30%を占める補助金制度は,戦後日本財政の特質として定着していくことになったのである。
さて,表1は,1970年代初頭以降の一般会計補助金等の推移を示したものである。1972年に対一般会計比31.0%の水準は,75 年から上昇を始め,76〜79年には33%を超えた。しかし82年には30%を割り,84〜87年には連年絶対額で前年度を下回り,1980年から 1990年の10年間,ほぼ一直線に比率を低下させ,その結果,1990年代には22%台にまで落ち込むことになった。1980年代の補助金の再編政策は,一般会計比という量的側面でみると,70年代後半から80年代初頭の補助金の膨張を以前の水準に戻しただけでなく,高度成長期の30%前後の水準から,10%ポイント近く引き下げる劇的な変化をもたらしたのである。
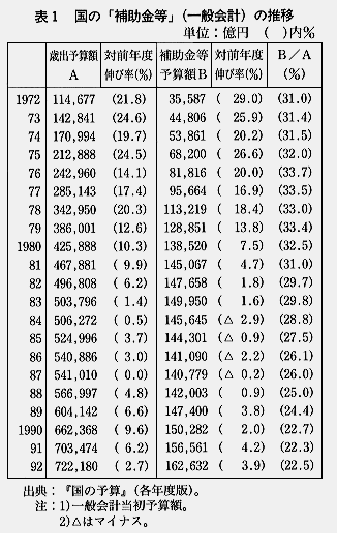
このような動向は,補助金の範囲を一般会計だけでなく,特別会計,政府関係機関にまで広げ,かつ小論が対象とする地方自治体向け補助金に限定しても同様である。所属会計別にみた表2は,1983年から89年にかけて一般会計分が停滞する一方,特別会計分が「地方向け交付金」の増大に支えられて一般会計分を上回っていること,旧3公社の民営化(1985年専売公社,日本電電,1987年国鉄)を契機に政府関係機関分が激滅したことをひとまず示している。「地方向け交付金」のほとんどは地方交付税であり,これが補助金総額(広義)に占める比率は1980年31.5%から89年43.5%まで上昇している。補助金総額(広義)に占める地方団体向け比率が抑制傾向にあっても80%台を維持しているのは,地方交付税の増額によるものといってよい。
逆にいうと,これらの数値は,地方団体向け補助金のうち狭義の補助金が減少していることを示している。各会計分を合計した地方団体向け補助金(B)から「地方向け交付金」(A)を差し引いた(D)がほぼ狭義の補助金を示すが,その額は1980年代を通じて停滞する。また,これが一般会計予算総額に占める比率をみると,1977年32.2%から一路縮小し,89年には22.1%となり,絶対額が上昇した92年でも21.8%となっている。一般会計予算額に対する比率を基準としてみれば,地方団体向け補助金の総体(一般会計,特別会計,政府関係機関の合計)についても,70年代後半から90 年代初頭にかけて10%ポイント近い減少をみてとれるのである。
国家財政サイドからみた以上のような補助金の急激な減少傾向は,当然受け皿となる地方自治体財政の収入構成に変化を及ぼす。表3は,財政収入(普通会計)に占める補助金(国庫支出金)の比率を都道府県,市町村別にみたものである。国の一般会計に占める補助金比率が高原状態をなしている 1970年代の後半は,やはり,都道府県,市町村とも国庫支出金の比率はピークとなっている。都道府県の場合,最高27.5%の水準から81年以降減少を続け,88年には20%を切るに至った。市町村も78年15.9%をピークとし,82年に15%,87年に10%を割り,90年代は8%台で推移している。1980年代を通じて,前者は約10%ポイント,後者は7%ポイント強の大きな落込みをみせている。なお,市町村の場合,都道府県支出金が同じ時期 1.5%ポイントの減少に留まり1985年以降絶対額で着実に増加しているのは看過できない点であり,のちに関説する。
補助金の縮小という量的な変貌の様子は,概略以上の通りだが,その内容はどう変化しているだろうか。まず表4で,一般会計補助金等の主要経費別内訳をみると,社会保障関係費の増大が,1980年代を通じた傾向であることを確認しうる。すなわち,同費は,1980年33.8%から1989年 41.7%まで増大しており,これを引っぱっているのは,社会福祉費及び社会保険費である。他方,これと並んで主要な構成要素をなす文教及び科学振興費,公共事業費は,後者が微減するものの大きな変化はない。社会保障関係費の増大は,食糧管理費,旧3公社の民営化などによる「その他事項経費」の減少と裏腹の関係にある。
こうした特徴は,表5の所管省庁別補助金の動向にも反映されている。すなわち,もっぱら社会保障関係費を管掌する厚生省の比率が1980 年34.1%から89年42.1%まで増大している。国鉄の民営化を進めた運輸省,および農産物の輸入自由化問題を抱えた農林水産省のシェアが1980年からやや目だって減少しており,これが,厚生省分の増大を支えるかたちとなる。
なお,1990年代に入ると80年代とは多少異なる傾向がみられる。社会保障関係費,厚生省所管分がそれぞれ若干減少し,その分公共事業関係費が増大している。1989年から92年にかけて,農業農村整備事業費,住宅対策費,下水道環境衛生等施設整備費,その他の一般公共事業費のいずれもがシェアを拡大している。公共事業を牽引者とした内需拡大を迫る「外圧」と,「平成不況」に対する景気浮揚策という国内事情が重なって,80年代の傾向を変化させたものとみることができる。
当該期における補助金の地位の変動とその内容の変化は,会計検査統計にも顕然と反映されている。表6は,会計検査院が毎年実施する決算検査で指摘した,支出に関する不当事項件数の推移をみたものである。まず,合計欄に着目すると,1982年時点では,「補助事業の実施及び経理が適切でなかったもの」が109件で全体の90.1%を占めていたが,86年には73.1%に減り,1990年代に入ると逆に「補助金等」と直接関係のない事項の方が多くなっている。
不当事項のうち「補助金等」の内訳をみると,1980年代前半には補助金所管省庁として突出する文部省,厚生省,農林水産省,建設省の4省に,補助金比率(対所管予算比)の高い通産省を加えた5省が大宗をなしていた。しかし,80年代終盤以降は,厚生省,文部省,特に前者への集中傾向が強まっている。最近における会計検査のターゲットは結果として,厚生省所管予算,なかでも「補助金等」と直接関係のない医療費負担などに集中しており,これは,これまで述べてきた補助金自体の地位,構成の変化を反映したものといえるだろう。
以上のように,オイル・ショック以降大量の国債発行に支えられて膨張した補助金は,1970年代後半から80年代初めにかけて,農林水産省,建設省などが所管する公共事業費,農林関係費などのウェイト低下を伴いながら減少し,さらに80年代半ばから減少のテンポは速まり,80年代後半には,国,地方双方の側からみて補助金の地位は大きく低下した。そのなかで,社会保障関係が相対的な地位を高め,福祉国家の骨格部分をなんとか支えている姿が,逆に浮かび上がってきている。
二、政策的拝啓−財政組織の再編
以上のような補助金の変貌は,国と地方の財政関係の再編政策のなかに位置付けられねばならない(注8)。いま,その基本線を表7,表8で確認しておこう。同表は,主要経費別に国と地方がどのように経費負担をしているのか示したものであり,1970年代と80年代の動向を対比しうるようになっている。国が最終的に支出するものを「国自体の支出」,地方が最終的に支出するもののうち国庫が負担するものを「地方負担の支出」と分類している。地方財政収入の一般財源となる地方交付税については,「国から地方への支出」では「地方財政費」に分類し,「地方負担の支出」を算出する際には,地方行政事務別支出額で按分し,それぞれ地方負担の支出から差し引く処理をしてある。
さて,これによると,1970年代には,国と地方を通じる財政膨張が「国自体の支出」,「国から地方への支出」,「地方負担の支出」の順で大きく増大し,国から地方への財政トランスファーが,地方財政支出の増加に大きな役割を果たしたことが確認できる。その中身は,地方財政費として示されている地方交付税,狭義の補助金をなすものとして国土開発費,教育費,社会保障費の比重が高い。
これに対し1980年代になると,全体として膨張のテンポが著しく鈍化するとともに,上記3区分は三者三様の動きを示す。まず,「国自体の支出」は,公債費,機関費,防衛費など平均以上の伸び率を示す経費もあり,ほぼ平均的な増加率となる。これに対し,「国から地方への支出」は,最も伸び率が小さく,地方財政費以外は,増加率がマイナスか,プラスでも20%どまりである。要するに,地方交付税は平均以上の増加率を確保し,財政支出総体に占める構成比を1980年11.9%から90年12.9%まで回復したが,狭義の補助金は,1970年,80年に14%台だったものが,90年には 9.4%に縮小しているのである。
他方,1970年代には最も増加率の低かった「地方負担の支出」は,1980年代には逆に相対的に最も増加率が高くなった。経費別にみると教育費が平均をやや下回るほかは,機関費,国土開発費,公債費,産業経済費,社会保障費がいずれも平均以上の増加率をみせている。
以上のように,1980年代において,財政支出面で最も強い抑制傾向がみられるのは,国と地方が実際に「共同」で行政サービスを分担している費目,すなわち,社会保障費,教育費,国土開発費,産業経済費における「国から地方の支出」と,同様の性格の事務における「国自体の支出」である。さらに注目されるのは,これらの費目のうち教育費を除いて「地方負担の支出」部分のウェイトが高まっていることである。「国自体の支出」および「国から地方への支出」という国庫負担部分の著しい減少に対し,地方自治体が自ら負担を増やすことで,これらの行政サービス水準低下の圧力を下支えしていることがうかがえる。
その結果,国から地方への財政トランスファーは,1970年代における国庫補助金と地方交付税をほぼ同規模の2大支柱とする構成から,1980年代には後者へと決定的に比重を移すことになった。
このような再編の基本線は,明確な政策的意図に基づいて具体化されたといってよい。再編の前提をなす1970年代における財政支出の総体的な膨張は,第1に,戦後改革以降拡充されてきた社会保障制度がしだいに成熟化しつつある条件のもとで,いわゆる革新自治体の影響もあり本格的な所得再配分が求められたこと,第2に,70年代初頭以降の「日本機関車論」による「外圧」やオイル・ショック以降の不況対策を目的とする「内圧」の両側面から,国債大量発行によるフィスカル・ポリシーが展開されたこと,第3に,政権基盤がかつてなく動揺する状況のもとで,国民統合の重要な政策手段として補助金などの国庫資金が動員され,農業,中小企業,構造不況業種などを抱える後進地域に厚く配分されたこと,などを主な要因としていた。
1970年代を通じた財政膨張に対し,臨時行政調査会は,1983年最終答申において2つの基本方向から財政組織の再編をめざすことを明確にした。すなわち,行政の新しい2大目標として,「活力ある福祉社会の建設」と「国際社会に対する積極的貢献」を掲げ,第1に「官から民へ」,第2に「国から地方へ」というスローガンを「合理的機能分担」の基本方向とした。
第1の点について臨調はまず国家介入の程度にガイドラインを設けることを提起し,最終答申では,ヨーロッパ諸国の水準(50%前後)よりは「かなり低位にとどめることが必要」とした。そして,新自由主義に基づく公私分担見直し論を基本としながら,民活導入,公社・特殊法人の合理化・民営化,地方自治体の「地方行革」,新しい行政分野拡大の抑制などが次々と実施されていくことになる。
第2の点について臨調第3部会報告は,まず国と地方の機能分担の基本的視点として,①地域性,②効率性,③総合性を挙げ,「地方自治が最も実現されやすい基礎的自治体である市町村にできるだけ事務が配分されるべきである」と述べる。また機関委任事務についても,「地方自治体の事務として既に同化,定着しており,地方公共団体の自主的な判断のみによって処理することとしても支障を生じることがないと認められる事務は,地方公共団体の事務とする」とされている。
このような「事務の他方委譲論」の特徴は,国から地方への財政トランスファーの政策的,制度的な抑制,縮小に主導されて進展していることである。
まず,補助金の削減が企図された。この点について,1981年7月臨調第1次答申は,①社会的経済的実情に合わなくなったもの,②補助効果が乏しいもの,③受益者負担,融資などの措置が可能なもの,④既に地方公共団体の事務として同化,定着又は定型化しているもの,⑤零細補助金,以上の5つに該当するものが合理化の対象とされ,各省庁ごとに「総枠」を設定した一律削減が提言されていた。
実際,1982年には生活保護費などの一部を除いた国庫補助金の補助率一律1割カットが実施された。さらに,1985年には生活保護費,児童措置費,老人保護措置費の負担金など2分の1を超える高率補助率の制度的な一律削減が実施され,86〜88年に補助率の引き下げが暫定的に継続したのち,89年には主に経常経費関係の負担率が85年以前よりも引き下げられた水準で恒久化された。すなわち,生活保護費負担金,結核医療費負担金,精神薄弱者負担金は,10分の7.5(暫定機関中10分の7),児童措置費負担金,老人保護費負担金などは2分の1で固定されることになった。他方,投資的経費については,暫定期間が90年まで延長され,さらに91年には86年の水準まで復元した上で,93年まで暫定期間がさらに延長されることになった(注9)。
1985〜88年における国庫補助負担率の引き下げの影響は(注10),累計で4兆9039億円に及び,その補填措置は,地方交付税の特例が5191億円(10.6%),地方税税率特例3600億円(7.3%),建設地方債4兆248億円(82.1%)となっている。8割を超す部分が地方債の増発で埋め合わされ,約半額を占める臨時財政特例債は,元利償還の全額が地方交付税の基準財政需要額に組み込まれていた。しかし,1989年の恒久化措置では1兆3786億円のうち,2762億円(20.0%)が地方の一般財源負担となり,継続された臨時財政特例債6500億円(47.1%)も補助事業については元利償還費の国庫負担は50%となった。
ところで補助金の削減は,補助率の引き下げだけではない。補助金等の整理・合理化の実績を内容別にみると表9のようになる。まず,補助金の再編政策は,1980年代に入ると,「終期の設定」から始まり,「統合・メニュー化」,「定員削減」も80年代前半にピークがみられる。一方,「廃止」によるものは,1980年代半ばまでは,件数で「新規」を上回っているが,金額では,ほぼバランスしており,この時期に零細補助金の整理が一定程度進展したことを物語っている。さらに1987年に大規模な編成替があって「廃止」の規模が突出するものの,以後は件数ではほぼバランスし,金額ではむしろ「新規」の方が上回っている。
「廃止」に比して大きな影響の出ているのは,「前年度より減額」である。予算編成過程において78年に一般行政事務費に適用されたゼロシーリングが,82年にその他経費にも及び,83年からマイナスシーリングが実施された。さらに,すでにみたように,82年の補助率カット,85年からの補助率引き下げ措置の状況が,「補助率引き下げ」欄の件数の水準に反映されている。「補助率引き下げ」の件数は,暫定措置の恒久化が検討された89年, 91年にも突出した規模となっている。
以上のように補助金の劇的な縮小は,補助金の「廃止」によってではなく,80年代の「統合,メニュー化」,「終期の設定」,「定員削減」を露払いとし,本格的にはマイナスシーリングと「補助率の引き下げ」によってもたらされたものといえるであろう。
次に企図されたのが,地方交付税の抑制である。そのポイントは,周知の通り「選択と負担」の概念の導入に他ならない。1982年5月臨調第3部会報告の「国と地方の機能分担等の在り方について」では,「標準的な施設を維持し,標準的な規模において行う行政」を「基準行政」とし,地方公共団体が,それ以上の水準において行政サービスを実施しようとすれば,まず留保財源,節約財源により,さらに不足する場合は,受益者負担,超過課税,法定外普通税等によるべきだとした。こうした考え方の背景には,同じ報告で述べられているように,次のような認識があった。すなわち,「地方公共団体が擁する財源については,地方公共団体が地域住民から徴収する地方税のほか,地方交付税,地方譲与税,補助金,地方債等により総体として確保されることになっている。こうした地方財政の仕組みを通じて地方行政が運営されてきた結果,今や地方公共団体の標準的な行政サービスについては,全国的にみてほぼ同水準に達したものとみられる」と述べているのである。
こうした見地は,1989年新行革審の「国と地方の関係等に関する答申」においても継承されている。そこでは,「明治以来の区域に立つ都府県,一部の大都市を除き,ほぼ画一的な機能を付与された市町村を前提とし,ともすれば行政の全国的な斉一化,平準化に偏りがちな現行の国・地方を通じた行政システムは社会経済の変容と新たな課題に応えて,変革の時期を迎えつつある」とされている。
いずれにせよ,「基準財政需要額」に反映されるナショナル・ミニマムの水準が従来以上に上昇することを抑制し,それを超える部分は地方の負担となることが当然という見地を制度化することによって,財源保障すべき国家介入の範囲を限定しようとするのが政策意図なのである。
こうした理念は,地方自治体への財政自主権付与との関連もあり,直ちに実行に移されているわけではない。しかし,地方交付税の不足分を補填していた地方財政対策は,1980年代初頭から顕著な減少をみせ,1983年には,いったん交付税特別会計の借入が停止された。その結果,地方財政対策の規模は,ピーク時の対地方財政計画比10.6%から1984年3.1%まで縮小した。1986〜88年には,円高不況への対応を迫られ,86年には交付税特別会計の借入が1年だけ復活するが,地方財政対策の水準は,先の指標で3〜4%の水準に留まった。地方交付税が1980年代の半ば以降,1988年まで相対的に縮小していったのは,上記の意図に基づく政策的な結果であったといえる。
なお,政府間財政関係の再編,好景気などによって地方交付税原資の増加が実現しても,それがそのまま容認される状況ではなかった。 1989年ごろから交付税率の削減が大蔵省サイドから問題にされ,91年には特例減額5000億円が実行されるなど,新たな水準において,上方の制限が制度化されようとしていることは銘記されるべきであろう。
このように,「官から民へ」,「国から地方へ」という基本方向に基づいて,強い抑制政策が具体化されていった補助金と地方交付税であるが,それぞれに留意すべき点がある。まず第1に,補助金削減にあたって地方債に振り替えられた分のかなりの部分について,元利償還費が基準財政需要額に組み込まれる形で補填され,また89年の恒久化の際には,国のたばこ税が地方交付税の対象税目(交付税率25%)に追加されるなどの措置がとられたことである。そこから,補助金削減は地方交付税に振り返られただけであるという議論を生じる(注11)。
そうした側面は軽視できないし,むしろ財政組織再編の重要な柱を1つをなすというのが行論の論旨でもある。しかし,地方交付税の原資に上乗せする地方財政対策は,量的な根拠となる地方財政計画の策定が国の裁量にゆだねられており,同対策の減少は地方交付税の総額抑制の政策的性格を反映せざるをえない。したがって,基準財政需要額に補助金削減分が組み込まれても,他の行政項目が総額の抑制に合わせて裁量的に抑制されれば,振替分の財源保障的な意義はそのなかに埋没してしまう。結局,補助金削減分が個々の自治体ごとに1対1の対応で補填される保証はないのである。
事実,次節でその一端を確認するように,1980年代半ばの時点では,地方交付税の財源保障機能は,重大な限界にぶつかっていた。しかし,地方交付税は1980年代後半に息を吹き返す。その理由は,第1に,1989年消費税導入を伴う税制改革の結果,消費税の19.2%が地方交付税原資に組み込まれることになり,たばこ税をも加えて一挙に原資が充実したことである。第2に,1980年代後半からいわゆるバブル景気が長く続き,地方交付税原資の大宗をなす所得税,法人税が膨張したことである。以上の制度的,経済的条件に支えられ,地方交付税は,総体としての抑制志向にもかかわらず,補助金を大きく凌駕する地位を維持し,89年を画期として財政調整機能を強化したかたちで財源保障機能を復活させたといえるのである。
留意すべき第2の点は,補助率の削減について,産業基盤を優遇する日本的特徴が顕著だった点である。すなわち,一律削減といっても,① 社会保障費に多い高率補助金がまず標的となったこと,②投資的経費部門は,経常経費部門よりも暫定措置の延長が容認され,地方自治体の一般財源への直接的な負担転嫁が回避されたこと,さらに,③地方債の元利償還費の地方交付税の振り替え措置でも優遇されたこと,などである。こうした措置の結果は,補助金額の縮小をくい止めえていないが,80年代を通して,まずは公共事業ないし建設事業関係補助金のシェアの確保をもたらした。さらに,1990年日米構造協議のなかで日本は,公共投資拡大のため今後10年間に投資総額430兆円を確保するという国際公約を受け容れた。こうした「外圧」に加え,バブル崩壊から「平成不況」のなかで,従来型のフィスカル・ポリシー論が勢いを増し,その結果,90年代に入って公共事業関係補助金の総額,シェア両面での上昇につながっている。80年代末から90年代にかけての新しい動向は,主としてこの要因に規定されたものということができる。
三、地域別配分の動向−問われる財源保障機能
(1)都道府県財政収入としての補助金
補助金の地域別配分を検討する際,いく通りかの「地域区分」がありうるが,ここでは,北海道,東北,関東内陸,関東臨海,東海,北陸,近畿,中国,四国,九州という区分(注12)を用いる。また,時系列変化をみるために,1977年,1986年,1992年の3時点の数値をとった。 1977年は,国の一般会計に占める補助金比率がピークを迎えた時期,1986年は,1980年代前半から本格化した補助金削減を中心とする再編成が進展しつつある時期,1992年は,1989年の補助金の補助率切下げの恒久化や消費財導入に伴う政府間財政関係の再編を被り,しかもバブル崩壊の影響が深刻化していない時期である。
さて,まず表10で,地域別構成比と内訳の特徴をみる。シェアの大きいのは,九州17%台,関東臨海12〜13%,東北12%台,近畿 11〜12%台などである。時系列変化では,1977年から86年に,関東内陸,中国の上昇,東海,四国の下落というやや特異な動きがみられるが,全体としては,あまり目だった変化はなく,70年代型のシェアが大枠として維持される傾向が認められる。
補助金の内訳をみると,まず義務教育費負担金は,1977〜86年に地方圏では停滞ないし減少し,86〜92年に軒並み上昇している。一方,関東臨海,東海,近畿の大都市圏では,比率は一貫して上昇し,とりわけ関東臨海,近畿は,それぞれ54.3%,47.3%という高水準に達している。
次に建設事業費支出金をみると,地方圏では1986年にいったん比率が上昇したあと,92年に減少し,その結果77年との比較で10%ポイント前後の大幅な減少となっている。こうしたパターンを示したのは,東北,関東内陸,北陸,中国,九州(ただし92年の水準は77年を上回る)で,補助金の縮減のなかで,地方圏において公共事業費を相対的に厚く確保しようとする企図が反映している。これに対し,関東臨海,東海,近畿などの大都市圏では,その比率は一貫して低下している。
さらに,民生費負担金の中身は,92年を例にとると,全国平均で生活保護費負担金37.0%,児童保護費負担金29.0%,老人保護費負担金21.2%,精神衛生費負担金4.1%となっているが,その全体に占める比率は,全国的にほぼ一貫して低下している。なお,「その他」の増大が目につくが,依拠した資料ではその内訳は不明である。これに上記以外の社会保障関係補助金が少なからず含まれていることが予想されるが,これを勘案しても,都道府県に関しては,社会保障関係補助金を中軸とする構成には移行していない(注13)。結局,都道府県の場合,義務教育費負担金の比重が高い大都市圏型と,減少したとはいえ建設事業支出金の比率が高い地方圏型の対照的なタイプを検出しうる。
次に,都道府県補助金の相対的な地位を表11で検討してみる。国庫支出金の1人当り規模を長期間比較しうるように,全国平均を100とした場合の指数を掲げた。国から地方への財政トランスファーについて,この1人当り規模は地方圏で高く,大都市圏で低くなり,一般に財政調整機能の指標とされる。
数値の変動でやや目立つのは,1977〜86年に構成比の動きと符号して,関東内陸,中国が上昇し,逆に東海,四国で下落している点だが,全体としてそれほど大きな変化はない。また関東臨海,近畿の大都市圏のシェアを微増させているものの,全体の構成を変えるには至っていない。要するに,補助金総体のパイが激しく縮小するなかでも,財政調整機能を具備した地方圏への傾斜構造は維持されたのである。
しかし,そのパイの縮小の量的な影響は,大都市圏,地方圏を問わず激甚なものがあった。その影響をみる指標としては,金額の増減額ないし増減率,総収入に占める比率の変化などもあるが,ここでは地方税に対する比率を用いる。1977年に比率が高いのは,北海道192.6%,東北 229.8%,四国228.3%,九州211.5%などで,総じて地方圏は,地方税の2倍近くからそれ以上の財源が補助金を通じて供給されていた。ところが,以後1986年,92年と全国共通してこの比率は,つるべ落しに減少した。1992年でかろうじて100%台を維持しているのが,東北,四国,九州という状況である。他方,もともと比率の低かった大都市圏も,例外なく一貫して減少した。結局都道府県に対する国庫支出金は,地方圏への傾斜配分構造を維持したものの,地方税に対する比率をドラスティックに減少させ,総体として財源保障機能を著しく弱めたのである。
ところで,国から地方への財政トランスファーのもう1つの柱である地方交付税の動向が,補助金の動向とどのように関係しているかをみることが,小論の重視する視点の1つである。同じく地方税に対する地方交付税の比率をみると,1977年には東北198.5%,四国182.3%,九州 165.3%を初めとして地方圏に厚い配分がされていた。しかし,1977年から86年に,その比率は,四国を除く地方圏で著しく低下した。先に「地方交付税の財源保障機能は,重大な限界にぶつかっていた」と指摘したのは,とりもなおさず,この事実に基づいている。
ところが,1986〜92年に,この比率でみた財源保障機能が地方圏でかなりの程度回復をみせた。その程度は,特に北海道,東北,四国,九州の各地域で大きかった。他方,大都市圏は,関東臨海,近畿,関東内陸,東海で一貫して低下している。以上の数値の動向は,つまるところ,1986 年時点では重大な限界に立たされていた地方交付税が,92年にかけて,地方圏への財源保障機能を回復しながら,全体として財政調整機能を強化する方向で再編されたことを物語っている。
もっとも,以上の動きを規定する地方税の地域別動向にも留意すべきであろう。この間東京一極集中,大都市圏と地方圏の経済力格差の拡大などの変化があり,1人当り地方税収などを指標とした場合に,財政力格差が大都市圏と地方圏で拡大傾向にあるからである(注14)。しかし,ほぼ全国的に画一的な税制のもとで,それぞれの経済状況を反映して必然化する地方税収の地域間格差を是正していくことが,そもそも財政調整制度の目的であるから,上記の分析は有意味と考えられる。
(2)市町村財政収入としての補助金
従来,市町村財政レベルの補助金について,全国的地域区分に基づく検討は必ずしも十分でなかったように思われる。ここでは,都道府県の場合と同様の指標を算出することによって,市町村財政収入としての補助金の特徴を地域別配分の視点から明らかにしよう。
表12に,地域別構成比と内訳が示されている。まず,構成比の絶対的水準に着目すると,都道府県の場合との比較において,関東臨海,近畿の大都市圏は市町村の方が高く,地方圏は,ほぼ同じか少ない水準となっている。ただし九州は例外で市町村の方がさらに高く,地方圏のなかでも特に厚い配分がされていることがわかる。
構成比の時系列変化をみると,1977年から86年に四国,九州の減少,東海,中国の上昇がみられるが,それも1%ポイント前後の変動であり,地域枠が設けられているかのごとく,配分比は安定している。
次に内訳をみると,都道府県との比較において,民生費負担金の割合が高く,そうした傾向は,大都市部で大きい。ただし時系列的には北海道を例外として全国的に比率は減少している。もう1つの柱をなす建設事業費支出金の割合は,1977年,86年に関東臨海を除いて40〜50%と高い比率で推移する。特に地方圏のなかでも,東北,北陸,中国,四国は77〜86年にシェアを上昇させており,都道府県の場合と同様,総額縮減のなかで公共事業費を確保しようとする政策の結果が反映されている。しかしながら,1986年〜92年には全国的に例外なく大きな減少をみせている。
結局,関東臨海,近畿(1986年以降)などが民生費負担金を最大要素とする大都市圏型,北海道を除くその他の地域が,公共事業を最大要素とする地方圏型と類型化できる。ただし,地方圏においても建設事業費のシェアは低下しており,総じて構成要素の多様化が進んでいることは留意すべきであろう(注15)。
表13は,国庫支出金の地域別地位を示す。1人当りの国庫支出金の指数(全国平均=100)は,前表でみた構成比の水準を反映しており,都道府県に比して東北,関東内陸がかなり低い水準,近畿が高水準という特徴を示す。時系列の変化をみると関東臨海,東海,近畿の大都市圏で停滞ないし微減となる一方,地方圏で上昇する。後者の傾向が顕著なのは,北海道,東北,四国,九州であり,1人当りの金額の指数でみる限り,市町村収入としての国庫支出金がもつ財政調整機能はやや強化されつつあるといえる。
もっとも,都道府県の場合と同様,地方税に対する比率は例外なく大きく減少しており,財源保障機能の大幅減退のインパクトの大きさを想像しうる。
一方,地方交付税の地方税に対する比率は,国庫支出金と異なる動きを示す。関東臨海,東海,近畿の大都市圏では,補助金の動きと歩調を合わせるかのように一貫して低下していく。ところが地方圏においては,1977〜86年には大きな減少を示すものの,86〜92年には北海道,東北,中国,四国,九州においてその比率をかなり顕著に上昇させている。
以上の結果を踏まえ,国庫支出金と地方交付税との合計額の地方税比率を算出してみると,大都市圏は,当該期に一貫して低下し,関東臨海,近畿,関東内陸,東海では,1992年には77年の半分以下の水準にまで落ち込んでしまう。これに対し,地方圏では,86〜92年に総体的に持ち直しの傾向をみせ,北海道,東北,四国はむしろ86年の水準を上回るに至っている。
ところで市町村の場合,上位団体からの資金援助は国庫支出金だけでなく,都道府県からの補助金として都道府県支出金がある。最後に,表 14によってその地位を確認しておこう。その際,日常的に都道府県が指導,援助している市町村への財政的裏付けという意味で,ひとまず政令指定都市を除いた数値を算出してみた。
都道府県支出金は,統計上,「国庫援助を伴うもの」と「国庫補助を伴わないもの」に分類されている。前者の金額は,1977〜86年に国庫支出金の減少と同様に減少傾向を免れていないものの,86〜92年には,国庫支出金が引続き減少するのに対し,絶対額では増加している。一方,地方税に対する比率は全般的に低下している。とはいえ,86〜92年には絶対額の増加に支えられて,減少のテンポが大都市圏では関東臨海,近畿,地方圏では四国,九州などで鈍っている点は看過できない。
次に,後者の「国庫を伴わないもの」は,都道府県の独自の政策判断による補助金である。前者と同様,1986〜92年には絶対額が例外なく相当に増大し,その結果,対地方税比率も86〜92年には,関東臨海,近畿で低位ではあるが,ほぼ86年の水準が維持され,また北海道,四国,九州では下げ幅をかなり圧縮することが可能になった。
都道府県支出金の国庫支出金に対する比率が上昇するという現象は,以上の傾向から直ちに予測しうる。事実,1977年には九州の30% を除いてすべて40%台だったものが,92年には関東内陸,東海が80%台,東北,関東臨海,北陸,中国,四国が70%台へと増大した。都道府県支出の役割は,第1に,国庫支出金の削減を財源保障の面から相対的に下支えする役割を果たしつつあること,第2に,対地方税比率の水準が1992年に大都市圏では関東臨海8.0%,近畿10.6%に対し,地方圏では北海道24.3%,四国,九州ともに25.0%というように,全国的な視点からみても,財政調整的機能を担っていることである。いまや,市町村の補助金問題は,都道府県支出金を除いては考えられない段階に到達しているのである。
結びにかえて
以上の検討を小括しつつ,若干の展望を示して結びにかえたい。
第1に,1970年代後半からの補助金増大傾向に対して実行された80年代を通じた再編は,補助金の量的水準に関する新しい段階をもたらした。国の一般会計比で30%前後を占めた補助金は,90年代には20%強に下落した。地方財政収入に占める比率もピーク時には都道府県27%台,市町村 15%台であったが,90年代にはそれぞれ20%,10%を大きく割り込むに至った。補助金の財源保障機能は,大きな落差をもって弱化したのであり,「ポスト戦後」的な日本財政の特徴が生み出されたといって過言ではない。
第2に,こうしたドラスティックな再編が,明確な政策的意図に支えられて現実化していったこと,第2節でみた通りである。補助金問題は,補助の水準を議論する段階から,農業や教育分野で既に手がつけられているように,存立の根拠自体が見直しの対象となっている点に特徴がある(注 16)。これまで当然国が責任をもつべきだと国自身が認めてきた分野からの国の撤退が争点になりつつあるのである(注17)。国と地方の機能分担の基本的な視点は,先にふれたように,①地域性,②効率性,③総合性である。さらに最近では,「国の行政においては対外政策により大きく重点を移し,むしろ国内的問題はできる限り国民に身近な地方で処理できるようにしていくことが望ましい」(1991年7月第3次臨調の第1次答申)というようなラディカルな議論も登場している。
しかし,事はそれほど単純であろうか。高齢化社会へ向けて在宅福祉を中心とした対人福祉サービスを充実させていく上でも,地域格差をいかに是正していくのかは大きな課題となろう。また,「持続的発展」を可能にする環境保全対策や農山村地域の歴史文化を含めた総合的な国土の保全政策,リカレント教育を含めた社会教育政策などは地域ごとにバラバラの水準では必ずしも十分に効果を発揮しえない。いわば,時代の要請に対応した新しいナショナル・ミニマムが求められているのではないか。とすれば,著しい財政力格差の存在を宿命としいる日本経済社会においては,何らかの調整システムが引続き必要とされよう。その手段が補助金である必要はないが,新行政分野も含めた事務事業の拡張に対応して,地方自治体の財源保障のビジョンが明らかにされるべきである。国の「国内政策」からの撤退=「財源保障なき事務委譲」は,かかる視点から各行政内容に即して厳密にチェックされる必要があろう。
第3に,地域別配分の動向については,個々の事実を繰り返す必要はなかろう。以下,補助金の大幅削減が大都市圏と地方圏とで,どちらに深刻な影響を及ぼしたのか,という論点に一定の解答を与えて小括としたい。
いま,補助金再編の過程について,前掲諸表の1977〜86年の変化に示される過程を第1局面,86〜92年の変化に示される過程を第2局面とすると,第1局面における補助金の削減は,さしあたりは,大都市圏,地方圏を通じた大幅なものであったといえる。しかし,その実質的な影響度は地方圏に大きかったというべきである。なぜならば,第1に,1970年代後半の時点で地方圏の地方自治体財政は,国から地方への財政トランスファーに深く依存して初めて存立できる構成となっており,そのなかで補助金は地方交付税よりも大きな財源保障機能を果たしていたのである。第2に,オイル・ショック後の低成長下で多くの不況業種を地方圏が抱えるなかで70年代を通じて地域経済は,公共投資に強く依存した体質を作り上げていった。補助金の大幅な削減は,地方圏における地域・地方自治体のそうした基本的骨格を根底から揺さぶるものだったのである。
ところが,第2局面になると地方税に対する地方交付税の財源保障機能が,財政調整機能の制度的な強化を伴いながら回復してくる。その結果,国庫支出金と地方交付税の合計が地方税に対する比率は,地方圏において第1局面の時と同じようには縮小しなかった。都道府県では,この比率は低下傾向を免れなかったものの,大都市圏に比して相対的に維持された。市町村では,都道府県支出金の相対的な増大もあり,ほぼこの比率が維持された。
一方,大都市圏においてこの比率は,都道府県,市町村をとわず第1局面に引続き,第2局面でも減少を続けた。要するに,地方交付税の恩恵を受けにくい大都市圏の地方自治体財政に対し,直接的な影響が及んだのである。かかる影響は,好景気が長期間継続し,大都市圏の地方税収の伸びが好調であったことから,第2局面では伏在している側面もあった。しかし,バブル崩壊から不況過程が長引くなかで地方税収が落ち込むと,この問題が一挙に顕在化してくる構造をもっていたのである。
注:
(1)日本経済新聞社編『地方分権の虚実−自立の条件−』日本経済新聞社,1994年,特に第2,3章。
(2)二十一世紀研究会『新・日本改造論』プレジデント社,1990年,157頁。
(3)「補助金」の用語は,広義には,一般財源となるものと特定財源となるものを含む。前者は,日本の場合,地方交付税が代表的であり,後者が狭義の補助金となる(国庫支出金,都道府県支出金など)。
(4)今村奈良臣『補助金と農業・農村』家の光協会,1978年。
(5)広瀬道貞『補助金と政権党』朝日新聞社,1981年。
(6)執筆者は,(1)宮本憲一,(2)鶴田廣巳,(3)山田明,(4)保母武彦。
(7)大蔵省主計局『補助金に関する諸見解』1953年2月。
(8)この点について詳しくは,拙稿「日本における政府間事務配分の動向−「膨張期」と「調整期」−」(林健久・加藤栄一編『福祉国家財政の国際比較』東京大学出版会,1992年)を参照されたい。
(9)この間の経緯は,大蔵省と自治省のかけ引きを含めて,沢井勝『変動期の地方財政』敬文堂,1993年が詳しいので参照した。
(10)影響額の試算は,遠藤安彦「平成元年度の国の予算と地方財政対策」(『地方財政』地方財務協会,1989年2月号)による。
(11)たとえば,中井英雄「構造転換と地方財政」(鈴木多加史編『日本の構造転換と地域経済』ぎょうせい,1989年)。
(12)各地域に所属する都道府県は以下の通り。北海道,東北(青森,岩手,秋田,宮城,山形,福島),関東内陸(茨城,栃木,群馬,山梨,長野),関東臨海(埼玉,千葉,東京,神奈川),東海(静岡,岐阜,愛知,三重),北陸(新潟,富山,石川,福井),近畿(滋賀,京都,奈良,和歌山,大阪,兵庫),中国(鳥取,島根,岡山,広島,山口),四国(徳島,香川,愛媛,高知),九州(福岡,佐賀,長崎,大分,熊本,宮崎,鹿児島,沖縄)。
(13)安東誠一は,1980年代半ばの時点で80年代と70年代を対比しつつ「現在は『公共事業主導型』のトランスファーから『社会保障主導型』のトランスファーへの移行過程にある」と指摘していた。たしかに,総体的にはそういえる実態を本稿でも確認できる。しかし,地方自治体への財政トランスファー,特に地方圏の自治体に関してこの特徴づけが可能かどうかについては,結論を留保したい。地方圏は,80年代を通じて「公共事業主導型」の性格を根強く持っているのである。
(14)この点,詳しくは,拙稿「地方税地域格差の動向と税制改革(1)−政府間財政関係再編の背景−」(『エコノミア』第42巻第2号,1991年9月)も参照されたい。
(15)この傾向を押し進めているのが,「その他」の補助金の急成長であり,1992年には,どの地域も20%前後の比率を占めている。ここには,今井勝人が重視する国民健康保険事業への補助金が含まれていると思われるが(今井勝人『現代日本の政府財政関係』東京大学出版会,1993年参照),詳しい検討は,他日を期したい。
(16)この点,鶴田廣巳が『政治経済学』で行っている,法律根拠別補助金の1983年から88年の変化を追った分析が示唆に富む。そこからは,①社会保障関係では「法律補助(義務)」件数が減らず実補助率が減少していること,②農業・教育関係は,金額・件数どちらかで「法律補助(義務)」の整理見直しが進んでいること,③逆に公共事業関係は「法律補助(任意)」,「予算補助」の金額は減少しているものの,「法律補助(義務)」は増加していること,などが読み取れる。
(17)この点については,具体的事例として前掲,拙稿「日本における政府間事務配分の動向−「膨張期」と「調整期」−」で,社会教育費,公共事業費,農林水産費を検討しておいた。