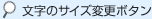第9号
会計事務職員の弁償責任と不法行為責任の関係
甲斐 素直
甲斐 素直(日本大学講師)
1948年生まれ。日本大学法学部法律学科卒業。73年会計検査院へ,事務総長官房上席審議室調査官,第1局司法検査課長を経て,93年より現職。公法学会,全国憲法研究会,財政法学会等に所属。
主な論文は「財政法規と憲法原理」日本法学第55巻第3号,「法律の留保」日本大学司法研究所紀要第3巻,「予算の法的性格」日本大学第59第4号,「憲法第89条後半における『公の支配』の意義」法学紀要第35巻など。
問題の所在
出納官吏については会計法第41条の,物品管理職員については物品管理法第31条の,そして予算執行職員については予算執行職員の責任に関する法律(以下「予責法」という。)第3条第2項のそれぞれ定めるところにより,これら3つの地位にある者(以下「会計事務職員」という。)が,国に対して加えた損害に対する賠償責任が,「弁償責任」という名称の下に設けられている(注1)。これらの行為は,同時に民法第709条以下に定める不法行為責任の規定も充足している場合が多い。その際の,二つの請求権の関係が,本稿の論点である。
1 弁償責任の母法系
わが国財政法制度には二つの大きな潮流が存在する。フランス法系とドイツ法系である。明治初期にわが国は,当時パリ大学法学部長であったボアソナードを顧問として迎え,その指導の下にあらゆる法制度を急速に整備しようとしたが,財政制度もまたその例外ではなかった。ボアソナードの指導したフランス系の財政法制度は,基本的にはナポレオン一世が制定した法体系であり,直接模範としたのは,ナポレオン三世の第二帝政時代のそれである。
それらフランス財政法制度の大きな特徴の第一は,会計事務職員の権限を分割し,その相互の抑制により財政執行の適正を図るという点にある。フランス財政制度の特徴として,よく内部統制が強力であるということが言われるが,それはあくまでも,会計機関内部における相互牽制に止まるものであることに注意する必要がある。近代的な内部監査組織がないということは,今日に至るまでフランス財政法制度の大きな特徴であり続けている。
第二は,外部検査組織もまた設けられていないという点である。その代わりに,官金を扱う者の責任をきわめて重いものとし,事実上無過失の弁償責任として位置付けているわけである。確かに,通常わが国に紹介されるときには会計検査院と翻訳される組織が,同国にも当時から存在していた。しかし,少なくとも第二帝政までの時期におけるCour des Comptesは,今日的な意味での外部検査機関と認められるような性格を持つ機関ではなかった。ナポレオン一世が制定した当時におけるその権限は,官金を扱う者の弁償責任を解除し,あるいは弁償責任額を決定する権限を有する司法機関で,しかも下級審に過ぎなかった(注2)。第二帝政になった段階で,ある程度は一般的な財政検査権限を持つようになるが,それとても近代的な外部検査機関のそれではなかった。すなわち,「会計検査院の機能は,事後検査を通じて行われる計算書の審査に限られる。会計検査院は各省大臣又はその下僚に対して監督を行うものではなく,その活動に干渉することは出来ない。提出された計算書に判断を下し,議会に報告をするに止まっている(注3)。」
このように,内部監査の不存在と無いに等しい外部検査という二重の弱点をカバーするために導入されたのが,フランス法における会計職員の弁償責任ということができる。フランス法では,内部監査や外部検査がない分だけ大蔵省の権限が強化されるところから,明治期における大蔵省は,フランス帰りの留学生を中心に積極的にフランス法系の導入を図った。実際問題として,ボアソナードが播いたフランス法系の法律が,プロイセン憲法思想の導入の下に総崩れになった中で,明治会計法はわが国で実現した数少ないフランス系の法律の一つである。
こうした会計法に対して,会計検査法に関しては平塚定二郎の理論的な支援を受けた会計検査院長渡辺昇の強力な指導の下,プロイセン法が導入され(注4),立法,司法及び行政の三権の,いずれにも属さない独立機関型の会計検査院が設置された。プロイセンでは,というよりもフランス法系以外の法制度の下では,会計事務職員の分立とそれによる相互統制というものはない。したがって,出納官吏が無条件に弁償責任を負うということもない。
ただし,プロイセンにおいても,弁償責任類似の制度がまったくなかったわけではない。フランスを除く欧米諸国では,支出官はわが国の資金前渡官吏の場合のように,一定額の資金の交付を受け,授権された範囲内においてそれを支出し,会計期間経過後に残額があれば,これを国に返納するという事務手続きを採る。会計検査院は決算額の会計検査の一環として,支出が妥当か否かを検査するから,仮に支出行為に問題が認められれば,当然,返納額の当否が自動的に問題になることになる。そこで「会計官吏においてその責めに任ずべき金額があり,補填した証明がない場合において,会計検査院が必要と認めるときは,その金額を収入調定額中に記入し,当該官庁に取り立てを命じる(プロイセン会計検査組織権限法第17条)(注5)」こととなっていた。
要するに,フランス法では,会計検査とは関係のない絶対的な無過失責任で,会計検査院にはその有無を決定する権限しかなかった。これに対して,プロイセン法においては,会計検査院の検査の一環としての行為であり,徴収権限は各省庁の方にあった。また,徴収するか否かについても会計検査院に全面的な裁量権を認めており,事実,小額なものや,徴収するについて大きな手間のかかるものについては宥恕するなどの処置が取られていたという。そして,その弁償責任の法的性格も民事上の責任である点,争いはなかったという。
わが国財政法制度は,フランス系の会計制度とドイツ系の財政監督制度の奇妙な混淆である。そして,ここで問題となっている会計事務職員の弁償責任は,フランス法系のそれに起源を有するものであるが,ドイツ法系の起源を持つ会計検査院にその運用が押し付けられたという点で,まさに二つの交点であったのである。
2 わが国弁償責任の沿革
明治22年に初めて会計法が制定された(注6)。その中に弁償責任の規定も置かれた。それは,母法たるフランス法と同様の無過失責任であったばかりでなく,現金と物品とを区別せず,「現金若ハ物品」と同列に規定している。このように物品についても現金と同列の厳しい弁償責任を定めたのは,母法であるフランス法にも例を見ない珍しいものである。さらに,この弁償責任を確実に確保するため,身元保証金を置かせることとしていた。また,会計規則において,補助者の行為によって発生した損害についても賠償責任があることを定めていた。そして,これらの裁判権は特別裁判所たる会計検査院に与えられた。会計検査院は終審裁判所とされ,他に上告する道はなかったから,コンセイユ・デタの下級審として位置付けられていたフランス法よりも,この点でも厳しい法制となっていた。
なお,大蔵省は出納官吏ばかりでなく,これまたフランス法に例のない,命令系統に属する会計官吏に対しても弁償責任を課するとする制度を導入しようと画策したという。が,各省庁の抵抗が強かったため,その案は草案の段階で完全に消えてしまっている(注7)。この点については,第2次大戦後の一連の改革を待つ必要があったわけである。
しかし,このように厳しい個人責任制度は,売官制度や徴税請負人制度のように,会計事務職員個人に大きな経済力があることを当然に期待できる法制や,ないしは事務執行のうえで裁量の幅が大きく,そこに当然役得を期待し得る法制度の下であればともかく,特別の経済力もないわが国官吏に課するのは,わが国の国情を無視したものということができた。そこで,この制度は,主として会計検査院の手により,創設後間もない頃から骨抜きにされていくのである。すなわち,「明治29年に制定された民法,同じく32年に制定された商法において,賠償責任は,すべて過失原則に基づいて設定されるに及び,会計検査院内部において,会計法による弁償責任は,民法上の損害賠償と同じ性格のものであるのに,無過失原則を適用するのは,両者の間に著しく衡平を欠くものである」との意見が有力になった。
こうして,出納官吏の賠償責任判決制度は,その制定後十数年にして,法文の規定はそのままながら,その運用において大きく補正されるに至った。会計検査院は,実際の判決に当たって,出納官吏に故意又は過失のあった場合に限って,弁償責任があると判決するようになったのであるが,この場合,会計検査院は現金又は物品の亡失毀損の事実があったことにより当然に発生した弁償責任を,判決によって受動的に解除するのではなく,むしろ,判定機関として能動的に当該出納官吏の故意過失の有無を判定し,その判決により,出納官吏の弁償責任が決定されるとしたのである(注8)。」
この中で,当時の会計検査院で主張された弁償責任と民法不法行為責任の同視及び会計検査院の能動的判定機関としての地位にあるとしての立場は,明らかにフランス法系のそれではなく,ドイツ法系のそれであることは,前節に紹介したところより明らかであろう。要するに,明治会計検査院はフランス法系に属する制度を敢えてドイツ法系の立場から解釈運用しようとしたのである。これは本来であれば許されることではない。
しかし,もともと国情の相違を無視してフランス法系の弁償責任を導入しようとした大蔵省の方針の方に基本的な無理があったところから,会計検査院の運用は一般的に支持され,大正10年には,「善良なる管理者としての注意を怠らざりしこと」を会計検査院に証明して責任を免れることができるという過失責任主義が導入される前に,会計法の方が改正されることとなったのである。また,実際にはほとんど徴収されることがなかったといわれる身元保証金制度も,この時正式に廃止された。ただし,責任の発生はあくまでも現金又は物品の亡失の事実によって当然に認められるとする,法の建前そのものは,なお維持されたのである(注9)。この点では,依然として,会計検査院の判決によって初めて責任が発生するという実際の運用とは,乖離した法制度となっていた。このように,フランス流の判決制度がドイツ流の組織により,ドイツ流の法思想の下に運営されるという変則事態が継続した結果,判決手続きが慎重に行われるようになったのは昭和10年代に入ってからであると言われている(注10)。その後も,判例さえも十分に確立しないままに敗戦を迎えるのである。
第2次大戦の敗戦及びそれに伴う新憲法の制定に伴い,弁償責任は大きな転機を迎えた。すなわち憲法第76条第2項は「特別裁判所は,これを設置することができない。行政機関は終審として裁判を行うことができない。」と定めていたので,フランス流の司法機関としての位置付けを会計検査院に与えることを前提としたそれまでの制度は,明らかに違憲となったのである。
そこで,会計検査院からは,この際,弁償責任制度そのものを廃止しようという主張が行われた(注11)。しかし,大蔵省側は承知せず,結局,昭和22年会計法では,会計法からは会計検査院の権限を規定した部分を削除したが(注12),代わって会計検査院法第32条に,同院が検定を行うことの根拠規定を置くことで対応することとなったのである。同条は,裁判所の活動と紛らわしい「判決」という語を「検定」という語に置き換えるとともに,会計検査院が,不正行為者の行動により「国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し,その弁償責任の有無を検定する」と定めることにより,弁償責任の存在を会計検査院が立証する必要のあることを明らかにした。
その後,25年に予算執行職員等の責任に関する法律(以下「予責法」という。)が制定され,会計検査院が弁償責任の有無を検定する対象者の範囲が拡大された。母法たるフランス法でも,出納職員に対象を限っていたのに対して,命令系統に属する会計事務職員にまで弁償責任を及ぼす方向に進んだもので,明治会計法制定時に大蔵省が構想していたと言われる,この世界的にみても珍しい法制度はとうとう実現したこととなる。ただし,責任の構成要件は,軽過失とした会計法と異なり,故意又は重過失とされた。また,この法律によって,国の職員だけでなく,公社等の職員にも国の職員に準じた取り扱いがなされることになった。
ついで31年に物品管理法が制定され,物品に関して現金と同一の責任を負わせるという法制度はようやく廃止されることとなった。その代わり,責任の対象となる物品官吏職員の範囲を,それまでの出納職員に加えて,命令機関である物品管理官等にまで拡大するとともに,出納保管に限っていたものを,取得,供用,処分などの管理行為に関しても弁償責任を負わせることとして,大幅な拡大をしたのである。ただし,責任要件としては予責法同様に故意又は重過失とされた。
3 弁償責任と不法行為責任の競合関係について
同一の事実関係に対して,二つの法体系により,二種類の請求権の発生が考えられる場合,両者の関係としては,次の三者が考えられる。
第一に,両法とも適用になるが,一方が他方の特別法という関係になるため,結果としては特別法だけが適用になる,という場合である。法条競合という。
第二に,一方の法律は別の理論から適用されることがないので,他方の法律だけが適用になる,という場合である。非競合という。
第三に,両法とも同一のレベルで適用になるが,どちらか一方の請求権の内容が充足された場合には,その限度で他方の請求権も消滅するという関係に立つ場合である。請求権競合という。
弁償責任と不法行為責任の競合関係についてもこの三者を考えることができ,事実そのいずれも学説として存在している。以下,現行法の解釈として,そのいずれが妥当か,検討したい。
(1)法条競合説について
前節と前々節において,弁償責任の母法とわが国の今日までの沿革を見てきた。これにより明らかなことは,これら会計事務職員の弁償責任は,決して民法不法行為法の特別法として位置付けることはできないということである。
もともと会計法は,国の会計の基本規範の一つとして制定されたものであって,それ自体,民法と同格の一般法である。なるほどその中には,時効に関する規定のように,条文上明確に民法に対する特別法であるとされているものもあるが,それはそのような明文の効力によるものである。そうした条文の存在を理由として,同法全体を一般的に民法の特別法であると解することが許されないことは当然である。すなわち会計法上の制度について,民法との関連を論ずるには,その一つ一つの規定の意味,特にそれが民法を修正するという意図の下に作られたものか否かを慎重に吟味する必要があるのである。
弁償責任は,ドイツ系の法では民法上の不法行為責任そのものであったから,この法系の制度として会計法等に特別の規定が置かれたのであれば,それをして民法の不法行為に対する特則と見ることは,穏当な解釈ということができる。しかしすでに紹介したとおり,フランス法系の弁償責任は,外部検査の弱体等を補うために制定された特別の公法上の責任であり,それを継受し,強化した形で制定されたわが国のそれは,制定過程を見ても民法の特則として構想されたものではないことは明らかである。また,戦前の会計検査院が,ドイツ流の民事上の責任として強引に運用したにも関わらず,大蔵省は敢えて,戦後に至るまで一貫して法の建て前を崩していない。それどころか,命令系統の職員や公社等の職員にまで拡大している状況であった。こうした沿革的状況もまた,本責任が,民事上の責任とはまったく異なる公法上の責任であることを端的に示しているといえよう。
もちろん,解釈論としては,そうした制度の沿革に関わりなく,本制度は民法の特別法であると解することにより,その適用ある分野での不法行為責任の排除を主張する余地はある。しかし,本制度は基本的には会計事務職員の責任を,一般行政職員に比べて加重することを目的としたものであるが,制度の内容を細かく一つ一つ吟味していくと,その詳細については次節に述べるが,結果として私法上の責任よりも軽減されている場面も現れてくるのである。したがって,特別法説を採用した場合には,私法上の責任を追及される一般行政職員の方が重い責任を追及される場合のあることを的確に説明できないという恨みが生ずる。その均衡という観点からみても,そうした解釈論を敢えて導入することが妥当とは認められない。
したがって,現行法の解釈として法条競合説を採用することはできないものと言わざるを得ない(注13)。
(2)非競合説について
非競合説は,戦前においては通説であったと見てよい。例えば美濃部達吉博士は「官吏は国家に対する義務違反に基づき原則として損害賠償の責任を負うことなし。官吏の国家に対する関係は公法上の関係にして民法の規定は直接には之に適用せらるることなし。唯出納官吏に付いてのみ会計法は其の出納保管に係る現金又は物品に付き一切の責任を負うべきことを定む。」と述べている(注14)。
戦後の会計法の解釈としては,杉村章三郎教授が強力に主張される説である。すなわち「一般に国家公務員はその義務違反に対して身分上の制度である懲戒処分を受ける外は,たといその行為によって国に対して財産上の損害を与えたとしても原則としてその賠償責任を負わない。その理由とするところは,公務員関係について契約説をとるとしてもその契約は公法上の契約であるから,一般私法上の労務者がその使用主に対して損害を与えた場合と同視して私法上の損害賠償に関する規定を適用することを得ない……(中略)以上のように公務員が国に対して与えた損害に対して賠償責任を負わないという原則に対する例外は,会計事務職員について相当広範に認められている。」として,国家公務員は一切私法上の責任を負わないとの立場を鮮明に示されている(注15)。この立場は,弁償責任という特別の制度の必要性を説明するという観点からは非常に明確であり,その限りでは説得力があることは否定できない。
しかし,この説は,その一点を除く多くの点に問題があり,賛成することはできない。第一に,国家公務員が国に損害を与えても私法上の責任を負わないという前提には反対せざるを得ない。特別権力関係説を採用しない限り,国家公務員の雇用契約が一般私法上の労務契約とまったく異質のものであると主張することは困難であろう。現に労働基準法等では公務員を明確に労働者として扱っている。
そして,今日の市民国家において,特別権力関係説のような画一的な論理によって公務員関係のすべてを説明することが許されないことは,もはや自明と言って良い。すなわち,公法と私法の区別が絶対的なものではなく,特に私法の規定でも一般的な原理や技術的な原理については,可能な限り公法分野にも妥当すべきであることは,今日,一般に認められていると言って良い。そして,自己の行為により他人に損害を与えた場合には,これが無過失または不可抗力によるものでない限り,その損害を賠償する責めに任ずるという不法行為の思想は,まさにそうした一般的原理の一つということができるのである。
したがって,今日においてこのような主張をするには,このような単純素朴な議論に代えて,公務員関係の特殊性に起因する個別具体的な論拠を必要とするといえよう。しかし,そうした論拠を教授はまったく示していない。
そこで,論拠となりうるものを私として検討した結果,その一つとしてあり得るのは国家賠償法の類推と考える。すなわち,同法では軽過失の場合には公務員個人に対する損害賠償請求を認めていない(第1条第2項)ので,国として公務員個人に損害賠償請求することも認められないのではないか,という論理である。この主張は,国家賠償法が何故個人に対する国民からの請求を否定したとみるのかという,より根本的な問題に対する考えの如何により答えが大きく異なり,その大きな問題に答えることは本稿の目的を逸脱するので,ここでは簡単に結論の要旨のみを述べるに止めたい。
すなわち,公務員の職務上の不法行為に基づく損害については,戦前は国家無責任の原則が支配し,行政裁判所は訴えを受理しないこととなっていた(行政裁判法第16条参照)ので,国等に対して賠償請求をするには民事事件として司法裁判所に訴える外はなかった。そして司法裁判所は被害者救済の一手段として,官吏個人に対する損害賠償の審理に当たり,官吏が職権を濫用して故意に私人の権利を侵害したときには,もはや官吏としての行為ではなく,私人としての行為であるとして民法の規定を適用し賠償責任を認めるという判例法を形成していた。しかし,国家賠償法が制定され,国という絶対的な資力を有するものが,軽過失でも損害賠償の責めに任ずることが明らかになった以上,それに重ねて公務員個人の責任を追及する実質的な理由は完全に失われているのである。
むしろ,同法が公務員本人に故意,重過失ある場合に国に公務員に対する求償権を認めていることは,同様の条件で国が直接民法上の損害賠償請求権を有することも肯定していると解する方が妥当であると認められる。もし,そう解しない場合には大きな不均衡が発生することは明らかである。
例えば,F刑務所において,刑務官が被収容者に送られてくる手紙の検閲に当たり,その中に入っていた金員を領得するという事件が起きたことがある。この場合,その金員の法的性格は,あくまでもその被収容者個人の私金であるから,当然被収容者として国に対して損害賠償請求をすることができる。そして,これは故意の犯行であるから,国がこの賠償請求に応じた場合には,その賠償額について本人に求償することができる。一方,その金員は,本来国としては歳入歳出外現金として管理するべきものであるから,犯人の行為はその管理権に対する侵害となる。したがって,国としては,民法上,直接損害賠償請求権を有していると考えることができる。しかし教授のように,後者の請求権を国が有することを全面的に否定する場合には,被害者からの請求を待たないで,直ちに領得された現金を回収するという簡易な処理をすることが不可能となる。そのような解釈を要求することは,無用の迂路を強いるものであって,その必然性は理解し難いし,現場事務が大幅に混乱することは否定できないであろう。
第二に,一般行政に関連した不正行為で,国が損害賠償請求権を認められないとすると,国は一般私人よりも不当に弱い立場におかれてしまうことである。例えば,K地方裁判所において,その職員が職務上知り得た知識を利用して金庫を解錠し,その中の現金を領得するという事件が起きたことがある。犯行は二回行われた。第一回の時には,犯人はその現金を管理する出納官吏の地位にあった。第二回の時は人事異動によりその地位にはいなかったが,同一箇所に勤務していた。この場合,教授の理論に従えば,第一回については会計法上の弁償責任を追及し得るが,第二回の犯行についてはいかなる賠償請求も行うことができず,単に犯人を懲戒免職にし得るだけということになる。これは明らかな不均衡であり,民間企業に比べて,国が特にそのように弱い立場になければならないいかなる理由をも見いだすことはできない。
なお,教授は,職務に関係のない行為により,国が被害を受けた場合に限り,民法上の損害賠償請求権を国も有すると主張する。しかし,職務関連性は少なくとも通説判例による限り,非常に緩やかに解されている概念である。例えば,国家賠償法の判例は,警察官が非番の際に,制服を着て強盗を行った場合についても,その行為に職務関連性の存在を認めている(注16)。したがってこのような修正により,不均衡を回復させることは困難であろう。少なくとも上記刑務所や裁判所の事例などでは職務関連性が肯定されることは確実で,このような修正を加えたとしても国の請求権を認めることはできない。
以上のことから,非競合説もまた妥当とは認められない。
(3)請求権競合説について
以上のとおり,法条競合説も非競合説も採れないということになれば,論理的にいって唯—の選択肢は請求権競合説,すなわち弁償責任に基づく請求権と,不法行為上の請求権とが同時に存在し,一方が充足された限度で他方も消滅するという関係に立っていると考えざるを得ない。このような消極的なアプローチからの説明はきわめて歯切れの悪いものである。
しかし,これは通説であり,また実務が採用しているところの説でもある(注17)。いずれの論者も,積極的な論拠を示すというより,せいぜい他の制度との均衡論を論拠として上げる程度に止まっている状況にある。例えば,田中二郎教授は,まったく理由を示すことなく,結論的に次のように述べている。
「その行為が民法の定める不法行為の要件を具備する場合においては,国庫に対する民法上の損害賠償責任を特に否定する理由はないように思われる。右の国庫に対する弁償責任の規定は,一般法に対する特別法で,その規定の適用のないものについての一般法の適用を一切排除する趣旨とまでは解すべきではなかろう。(注18)」
このように,どの論者においても,自説を主張する積極的な根拠を説明ができない理由は,フランス帝政時代の特殊な事情から発生した弁償責任を,今日の市民社会においてなお,不法行為に基づく請求権とは異なる独立の制度として維持しなければならない積極的な理由は,何も見当たらないためであると思われる。少なくとも会計事務職員が通常の官吏よりも俸給的に恵まれているというような特殊の事情でもあればいいのであるが,一般公務員と区別するいかなる利益も有していないのである。そして均衡論は,弁償責任が存在するからこそ必要なのである。仮にすべての公務員が等しく不法行為責任だけを負担している場合には,およそ問題にならないことだからである。しかし,現行法を前提とする限り,もっとも問題のない結論を導く説であることは事実で,そうした実態的妥当性こそが,本説が通説として,また実務を支配する説としての地位を勝ち得ている理由といってよいであろう。
4 請求権競合説の具体的な効果
二つの請求権には主として次の相違点がある。
(1)時効制度
① 民法不法行為法上の請求権:被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年,不法行為のときから20年とされている(民法724条)。前者の3年については民法上の通常の時効である(民法第144条以下参照)が,後者の20年については除斥期間である(注19)。
② 弁償責任による請求権:時効期間が5年,時効の援用を要しないこと,中断できないことという特徴を有する(会計法第30条〜31条)。すなわち除斥期間である。
(2)損害賠償の内容
① 民法不法行為法上の請求権:不法行為と相当因果関係に立つ全損害である。そして金銭債権であるところから,法定利率が適用されることとなる。過失相殺によって負担を一部に止めることが可能である。また相続の対象となるので,相続人は相続権の放棄を行わない限り,国に対してなお賠償の義務を負う。
② 弁償責任による請求権:亡失した現金や物品の限りであり,利息や得べかりし利益を含まない(注20)。賠償額はその全額であって,過失相殺の余地はない。そこで,会計検査院として検定するに当たっては,全額かゼロかの二つに一つを選択する必要がある。この結果,会計検査院として過失相殺の必要性を認識した場合には,請求権はないと検定しないと,当該公務員個人に対して過酷なこととなる(注21)。また属人的な義務であるので,刑事訴訟における罰金や追徴金と同様に,相続の対象とはならない。ただし本人が弁償命令を受けた後死亡したときは,国の債権であるには違いないから相続財産に対して執行することができるとして運用されている(注22)。
(3)過失の水準
① 民法不法行為法上の請求権:国家賠償法第1条第2項では,国が公務員の不法行為に関し第三者に損害賠償を行った場合に,その賠償額を公務員個人に求償できる場合を,当該公務員に故意,重過失があった場合に限定している。このように求償権の要件を限定したのは「すべての場合に求償権を有するものとすることは,公務員に対し酷に失するのみならず,事務執行の停廃をもたらす恐れがあるため,それを避けるための政策的見地から」であると説明するのが通説である(注23)。通常これとの比較考量から,各行政庁では公務員が職務執行に際して行った不正行為については,通常の不法行為と異なり,重過失以上がある場合に限って請求権を行使しているものと考えられる(注24)。求償権と同様の事務執行の停廃の危険は,この場合にも同じように存在すると認められるから妥当な運用と考える。
なお,国として公務員に請求可能なのは,公務員に不法行為を行うにつき故意があった場合に限るとする説がある(注25)。しかし,これは戦前,国家賠償はもちろん,公務員個人に対する賠償請求も,非競合説に紹介したような論理の下に肯定されていなかった時代において,被害者救済のため,判例が,公務員個人に対する賠償請求だけでも肯定しようとして形成した理論に従っているものである。国家賠償法の存在する今日においてなお妥当すると考える必要はない。同法の認める求償権の要件との均衡の上からも妥当とは認められない。そもそも予責法等において導入した重過失という概念は,故意の立証可能性の困難性から導入されたものと見るべきである。すなわち,故意は内心の事実であるから,不法行為者の任意の供述がない限り客観的に立証することの困難なものである。そこでその立証困難性をカバーするために,いわば故意に準ずるものとして重過失が加えられたものと考えられる(注26)。
② 弁償責任による請求権:会計法第41条第1項は,過失の要件について「善良な管理者の注意」という表現を使用しており,これが通常の軽過失を意味するものであることについては疑問の余地がない。この結果,この関係では民法不法行為法上の請求権よりも厳しいこととなる。しかし,出納官吏が物品管理官等よりも俸給的に優遇されている事実はない等,なんら特別事情がないのであるから,全体としての均衡を明らかに失しており,立法論的には妥当とは思えない。が,現行法解釈としては避けることのできない結論である。
おわりに
このように通覧してみると,民主主義の下,国家公務員といえども一般私人と等しく不法行為責任を負担するようになった法制の下で,会計事務職員に限って,不法行為責任とは別に弁償責任という特別の責任制度を法定し,しかも戦前に比べて著しく拡充しなければならなかった根拠を,今日という時点で理解することは非常に困難である。戦後の一連の,弁償責任に関連する法の制定が,美濃部教授等の非競合説が民主主義の下では妥当しないということがまだ十分に理解されていなかった時期に,民主的な責任制度への改善という観点から行われた,いわば間違った改革という印象を持つのは私だけであろうか。純然たる私見ということを改めて強調した上で述べるが,弁償責任は,立法論的には速やかにすべて廃止すべきであり,制度の運営に当たっては,可能な限り不法行為責任を中心に運用し,弁償責任の実質的な空洞化を図ることが好ましいと考える。
[注]
1)参考のため,各法律の条文を以下に示す。
会計法第41条 出納官吏が、その保管に係る現金を亡失した場合において、善良なる管理者の注意を怠ったときは、弁償の責を免れることができない。
2 出納官吏は、単に自ら事務を執らないことを理由としてその責を免れることができない。ただし、分任出納官吏、出納官吏代理又は出納員の行為については、この限りではない。
物品管理法第31条 次に掲げる職員(以下「物品管理職員」という。)は、故意又は重大な過失により、この法律の規定に違反して物品の取得、所属分類の決定、分類換、管理換、出納命令、出納、保管、供用、不用の決定若しくは処分(以下「物品の管理行為」という。)をしたこと又はこの法律の規定に従った物品の管理行為をしなかったことにより、物品を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、弁償の責に任じなければならない。
一 物品管理官
二 物品出納官
三 物品供用官
(四から六 略)
七 前各号に掲げる者の補助者
2 物品を使用する職員は、故意又は重大な過失によりその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、その損害を賠償する責めに任じなければならない。
3 前二項の規定により弁償すべき国の損害の額は、物品の亡失又は損傷の場合にあっては、亡失した物品の価額又は損傷による物品の減価額とし、その他の場合にあっては、当該物品の管理行為に関し通常生ずべき損害とする。
予責法第3条 予算執行職員は、法令に準拠し、且つ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、支出等の行為をしなければならない。
2 予算執行職員は、故意又は重大な過失に因り前項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたときは、弁償の責に任じなければならない。
会計検査院法第32条 会計検査院は、出納職員が現金を亡失したときは、善良なる管理者の注意を怠ったため国に損常を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。
2 会計検査院は、物品管理職員が物品管理法の規定に違反して物品の管理行為をしたこと又は同法の規定に従った物品の管理行為をしなかったことにより物品を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、故意又は重大な過失により国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。
3 会計検査院が弁償責任があると検定したときは、本属長官その他出納職員又は物品管理職員を監督する責任のある者は、前二項の検定に従って弁償を命じなければならない。
4及び5 略
2)神谷昭著『フランス行政法の研究』有斐閣、昭和40年刊,22頁は次のように述べている。
「公会計の管理の使命を有し,公会計についての訴訟事件を審理する権限を有する会計裁判所(Cour des Comptes)がある(1807年9月16日の法律,および同年9月28日のデクレ)。この裁判所は,その決定についてコンセイユ・デタに破毀の請求を提起することが法律上認められている関係上,行政裁判所としての地位を有する機関である。」
3)小峰保栄著『財政監督の諸展開』大村書店,昭和49年刊372頁参照。ここに引用した文章は,本来は第二帝政が崩壊したあとの第三共和制期におけるフランス会計検査院の権限の説明であるが,当時の会計検査制度は長い停滞期にあったから,第二帝政期にもそのまま妥当する。
4)ドイツ帝国予算会計法Reichshaushaltordnungは,近年までドイツ会計検査院の組織を規律していたが,その内容はわが国旧会計検査院法の定める組織及びその権限とほとんど異ならない内容である。
5)小峰前掲書332頁参照。
6)明治22年会計法関係の条文は次のとおりである(ただし,読み易くするため,カタカナをひらがなに直し,送りがなを現代表記に直している)。
第26条 政府に属する現金若しくは物品の出納を掌る所の官吏は共の現金若しくは物品に付き一切の責任を負い、会計検査院の検査判決を受くべし
第27条 前条の官吏水火盗難又はその他の事故に由り其の保管する所の現金若しくは物品を紛失毀損したる場合に於いては其の保管上避け得べからざりし事実を会計検査院に証明し責任解除の判決を受くるに非ざれば其の負担を免るるを得ず
会計規則第84条 出納官吏は其の責任に属する会計に付き、自身に事務を執らざるを理由として其の責任を免るるを得ず
7)小峰前掲書79頁参照
8)引用箇所については会計検査院刊『会計検査院百年史』377頁参照。
9)大正10年会計法の条文は次のとおりである(ただし,読み易くするため,カタカナをひらがなに直し,送りがなを現代表記に直している)。
第35条 出納官吏は法令の定むる所に依り現金又は物品を出納保管すべし
出納官吏は其の出納保管に係る現金又は物品に付き一切の責任を負い、会計検査院の検査判決を受くべし
第36条 出納官吏其の保管に係る現金又は物品を亡失毀損したるときは善良なる管理者としての注意を怠らざりしことを会計検査院に証明し、責任解除の判決を受くるに非ざればその亡失毀損につき弁償の責を免るることを得ず
なお,大正会計規則第132条に,注6に紹介した明治会計規則第84条は移ったが,そこでは「自身に事務を執らざる」とあるその前に「単に」の語を加え,補助者の行為でも責任が免除される余地を作っている。
10)判決制度の問題については中西又三著「会計職員の責任」現代行政法大系第10巻『財政』,319頁参照。
11)会計検査院に,弁償責任廃止論があったことについては,小峰前掲書208頁参照。
12)昭和22年会計法の条文は次のとおりである。
第41条第1項 出納官吏が、その保管に係る現金又は物品を亡失毀損した場合において、善良な管理者の注意を怠ったときは、弁償の責を免れることができない。
13)法条競合説を採用していると見られる論者には次のものがある。
① 中西又三著「会計職員の責任」現代行政法大系第10巻『財政』,328頁
② 小熊孝次,上林英男共編『会計法(下)』184頁
14)引用箇所に付いては,美濃部『行政法撮要』上巻(昭和7年刊),269頁参照。ただし,旧漢字は新漢字に改め,また送りがなをカタカナからひらがなに直した上,現代表記にしている。また,同様の主張は,佐々木惣一著『改版日本行政法総論』(大正12年),221頁などにも見ることができる。
15)杉村章三郎著『財政法』新版,有斐閣法律学全集10,289頁より引用
杉村教授は自説を強調される余り「職務上の業務に対する違反についても,特定の場合には,民法の不法行為等に関する規定の適用を認めるという説もある」として,自説を通説とし,請求権競合説を少数説とすることがごとき口吻を示されている。しかし,筆者の調査した限りにおいては,戦前はともかく,戦後においては非競合説を主張されている論者は少なく,注17に具体的に示したとおり,現在は請求権競合説が通説であると認められるので,同書を読む際には注意する必要がある。
非競合説を戦後において採っているものとしては,他に
(1) 川西誠著『行政法総論(改訂増補版)』312頁
(2) 井上鼎著『体系官庁財政会計辞典』825頁
16)最高裁第2小法廷昭和31年11月30日判決,民集10巻11号1502頁,判時95号11頁参照。
17)請求権競合説の主要な論者は次のとおりである。
① 木村精一著「出納官吏弁償責任釈義」(昭和16年刊)33頁
② 大沢実著「公会計基本逐条注釈(中)」244頁
③ 行方敬信著「財政・会計法新講」87頁
④ 佐藤謙編「債権管理法講義」78頁
⑤ 兵藤広治著「財政会計法」346頁
⑥ 全国会計事務職員協会編「質疑応答式官公庁会計辞典改訂5版」944頁(問1348),977頁(問1375)
⑦ 田中二郎著「行政法(中)」280頁
なお,このうち①から③までは会計検査院の関係者,④から⑥までは大蔵省の関係者が著者等となっている。
18)引用箇所については,田中注17前掲書,紹介箇所参照。
19)最判平成元年12月21日,民集43巻12号2209頁参照。
20)ただし,弁償責任についても利息を課するべきだとする説がある。大沢実者「予責法逐条注釈」314頁参照。
21)検定実例の中には,国の側の過失が考慮された結果,無責検定となった例があるという。岡田康彦著「新訂会計法精解」大蔵財務協会刊,734頁参照。
22)兵藤広治著「財政会計法」346頁参照。
23)田中二郎著「新版行政法(上)」206頁参照。
24)学説としては例えば田中前掲書(中)281頁では,次のように述べている。すなわち,不法行為責任は「特定の者の国庫に対する弁償責任について故意又は重大な過失を要件としていることとの均衡,及び軽過失についてまで責任を負わせることは行政を停廃させる恐れがあること等を考慮すると,解釈上,故意又は重大な過失のある場合に限定すべきである。」
25)例えば,小峰「財政監督の諸展開」134頁は,「故意による場合は,職務外の行為となり,国に対し損害賠償をすることを要するが,過失に基づく場合は,依然国家の代表機関の行為たるを失わないから,その効果は国に帰属し,たとえ損害を発生しても,行政上の懲戒を受けるか否かは別として,その賠償に任ずるの要はないのである。」としている。
同様の説を採るものとして
園部敏著「行政法概論」(昭和15年)419頁
木村精一著「会計法規の理論と実際」(昭和15年)44頁等。
26)重過失の解釈について,軽過失とは単なる量的な差異に過ぎないとする説は当然存在すると思われる。本文のように,故意に準ずるものという質的な差異を認めている例として,注釈民法第19巻27頁参照。